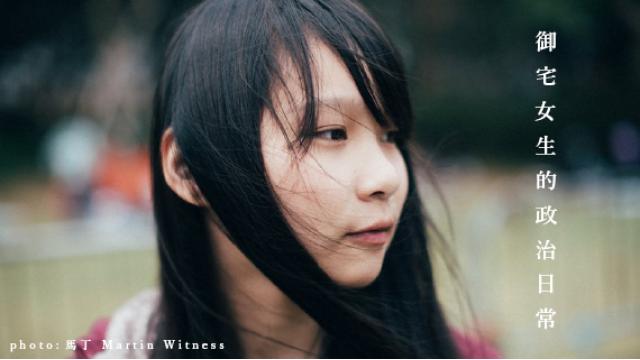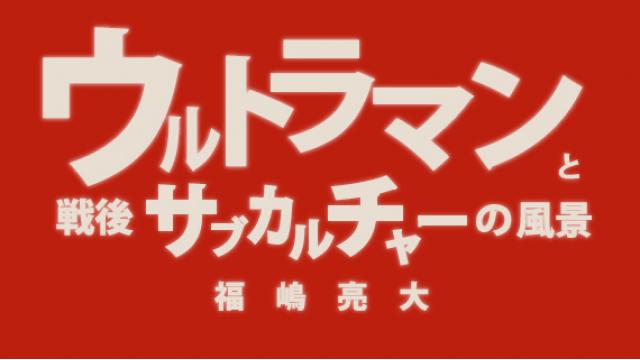-
ジョシュア・ウォン×周庭「香港返還20周年・民主のゆくえ」後編
2017-09-20 07:00
香港の社会運動家・周庭(アグネス・チョウ)さんの連載『御宅女生的政治日常――香港で民主化運動をしている女子大生の日記』。今回は2017年6月14日に東京大学駒場キャンパスで行われた講演「香港返還20周年・民主のゆくえ」の内容をお届けします。香港で民主活動をしているジョシュア・ウォンさんと周庭さんが、雨傘運動後の活動について語りました。(構成・翻訳:伯川星矢)
※文中の役職は、講演当時のものです。
※この記事の前編はこちら
雨傘運動を終えての失望と、民主活動の危険性
ジョシュア ここからは雨傘運動が終わった後のお話をしたいと思います。雨傘が終わったあと、香港人の間には失望感がありました。民主を実現するのは非常に難しいことなのではないか、という疑問も出始めていました。 ご存知の方も多いかとは思いますが、中国政府を批判する本を販売したとして銅鑼湾書店の店主さんや関係者の方たちが、昨年相次 -
福嶋亮大『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』第四章 風景と怪獣 1 虚構的ドキュメンタリーの系譜(2)【毎月配信】
2017-09-19 07:00
文芸批評家・福嶋亮大さんが、様々なジャンルを横断しながら日本特有の映像文化〈特撮〉を捉え直す『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』。円谷が「モダニズム的な飛行機」を愛しながら「反モダニズム的な怪獣」を共存させた流れを追いながら、その後継者としての宮崎駿についての議論を通じて、戦後日本の美学を「怪獣の時代」として総括します。
円谷英二と「崇高」な国策映画
ところで、本多が「記録」にこだわったのは必ずしも彼個人の趣味に留まるものではない。なぜなら、『太平洋の鷲』や『ゴジラ』を支えたドキュメンタリー志向は、すでに戦時下の日本映画において高揚していたからだ。特撮には大正期の枝正義郎らによる映画的技術の探求から戦時下のプロパガンダに到る発展のプロセスがあったが、ドキュメンタリー(記録映画)も戦争をきっかけにして大きく飛躍した。特撮とドキュメンタリーはともに、戦争を苗床として成長した「技術」なのだ。 そもそも、大切な家族を戦地に送り出した戦時下の観客にとって、身内が映っているかもしれないドキュメンタリーやニュース映画は戦場とのかけがえのない「絆」となった[14]。このきわめて真剣で注意深い観客の登場、さらに戦争のもたらす知覚的なインパクトのために、ドキュメンタリーは劇映画の想像力を凌駕するようになった。例えば、今村太平は一九三九年に、亀井文夫監督の『上海』や『南京』、内田吐夢監督の『土』、田坂具隆監督の『五人の斥候兵』といった同時期の記録映画――当時は「文化映画」(ドイツ語のKulturfilmの訳語)と呼ばれた――に言及しながら、こう述べている。
最近の日本映画の大きな問題はやはり記録と劇の問題である。記録映画的方法は主として事変ニュースを土台としてにわかに発展した。多くの劇映画は、戦争ニュースにとりまかれることによって急にみすぼらしくなった。[15]
三〇年代後半以降、ドキュメンタリー的手法は劇映画に着々と「浸潤」していった。本多の師匠の山本嘉次郎監督も、生まれたての仔馬の立ち上がる経過を高峰秀子演じる少女の家族がじっと見守る『馬』の印象的な一場面から、戦争ニュースと劇映画を融合させた『ハワイ・マレー沖海戦』の爆撃シーンに到るまで、戦時下の東宝で撮った映画では事実の記録というポーズを手放さなかった。『ゴジラ』の源流の一つは、これらの動物や戦争を題材とした「記録映画」にあるだろう。 この時期のドキュメンタリーの活性化は、日本に限らず世界的な傾向である。特に、ナチスの対外宣伝に貢献したレニ・リーフェンシュタールの映画は、事実の記録を華麗な映像詩に仕立てた。ヒトラーに感銘を与えたリーフェンシュタールの監督・主演作品『青の光』(一九三二年)には、水晶や山岳をモチーフとするドイツ・ロマン派的な美学に加えて、戦時下の円谷英二が「青空にそびえ立つポプラの葉裏がきらきら光る並木道を静かに駅馬車の通う感傷的な場面」と評したさり気なくも美しいシーンがある[16]。風景の「自生的」な立ち現れを鋭く捉える、彼女のこのリュミエール的な技術は、やがてナチズムの美学として組織化され、ナチスの党大会を記録した『意志の勝利』(一九三五年)やベルリン・オリンピックの記録映画である『民族の祭典』(一九三八年)を――すなわちドイツの力と美をアピールする「全体主義芸術」の最大の成功例を――生み出すことになる。 さらに、円谷自身の特撮も『ゴジラ』以前に「崇高」な風景に関わっていた。リーフェンシュタールの師であり、ナチスの支持者であったアーノルド・ファンク監督の日独合作映画『新しき土』に参加した円谷は、バックグラウンド・プロジェクションのかつてない多用によって、早川雪洲、小杉勇、原節子ら主要キャストを現地に連れて行くことなく、ある程度までスタジオで撮影を間に合わせることができた[17]。四方田犬彦が言うように、「大自然の脅威と火山の噴火」と「恋人たちの激情」の重なり合う『新しき土』の浅間山噴火口の場面は、ファンクによる「ナチスドイツ的な映像の修辞学」の具現化であったが[18]、このナチス的な美学を首尾よく完成させるのに、円谷の技術は大きな助けになったわけだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…
・入会月以降の記事を読むことができるようになります。
・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
宇野常寛『汎イメージ論 中間のものたちと秩序なきピースのゆくえ』第一回 中間のものについて(4)【金曜日配信】
2017-09-15 07:00
本誌編集長・宇野常寛による連載『汎イメージ論 中間のものたちと秩序なきピースのゆくえ』。Ingressとジョン・ハンケのメッセージを通じて、もはや文字列の検索に留まらず、実現実とそこに存在するあらゆる事物を検索するに至ったGoogleの思想を解説します。 (初出:『小説トリッパー』2017夏号)
5 ジョン・ハンケと「大きなゲーム」
こうした変化の象徴として、米Googleのことを考えてみよう。Googleがウェブサイトの検索を提供する企業だったのは過去の話だ。かつてGoogleは、本来無秩序なインターネットを検索可能にし、擬似的な秩序をもたらした。たくさんのサイトからリンクされているサイトは重要なサイトである、そして重要なサイトからリンクされているサイトは重要なサイトである――こうした判断基準を人工知能に与えたGoogleは無秩序に発生するウェブサイトを、重要なものとそうでないものとに峻別したのだ。
こうしてインターネットには擬似的な中心と周辺が形成され、人々はまるでそこをマスメディアのように秩序付けられたものとして読むことができた。それはいわば、ボトムアップの、参加型のマスメディアの誕生だった。政治からの独立が保証されるがゆえに逆説的に国家の保護を受け、第四の権力として特権的に情報を発信する――そしてそれゆえに硬直しやすい――マスメディアに対して、誰もが自由に情報を発信し得るインターネットが、Googleの人工知能に拠る「神の審判」によって重要なものとそうでないものが峻別され、フェアな競争を行う。私たちはあの頃、この新しい世界に希望を観ていた。ブロゴスフィアが担う新しいジャーナリズムが電子公共圏の礎になる――もちろん、短期的にはそこに数え切れないほどの困難が発生することは予測されていたが、同時に長期的にはこの新しいジャーナリズムと電子公共圏への移行自体は既定路線だと考えられていた。人々はボトムアップの、参加型のマスメディアを手に入れ、それが社会変革の礎になると期待した、だからこそ私たちは「動員の革命」を信じたのだ。そして、裏切られた。誰もが情報を発信できる世界が何をもたらしたか、もはや説明する必要はないだろう。
しかし、現在のGoogleはすでに異なるアプローチを行っている。もはやGoogleはモニターの中のウェブサイトの文字列を検索する会社ではない。現在のGoogleはGoogle Mapsが代表するように実空間とそこに存在するあらゆる事物を検索する会社だ。そう、もはや情報技術の支配する範囲はモニターの中にとどまらない。そもそも私たちがいまインターネットと呼んでいるものはIoH(インターネット・オブ・ヒューマン――ヒトのインターネット)と呼ばれるもので、人間が意識的に投稿したモニターのなかの文字列のつながりにすぎない。そしてこれは情報技術におけるインターなネットワークのほんの入口にすぎない。本来のインターネットはIoT(インターネット・オブ・シングス――モノのインターネット)と呼ばれる。それはモニターの中の平面を媒介として人間と人間を結びつける従来のインターネットとは大きく異なるものだ。その支配力はモニターの外側に及び、人間と人間が接続されるだけではなく、人間と事物、事物と事物が接続されることになる。モニターの外側の事物がつながり、検索可能になる。Googleの変節はこの変化を背景にしている。もはやインターネットは人間のものでもなければ、モニターの中のものでもないのだ。
では、このような現実優位の時代に対して、Googleはどのように対応しているのか。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
本日21:00から放送☆ 今週のスッキリ!できないニュースを一刀両断――宇野常寛の〈木曜解放区〉2017.9.14
2017-09-14 07:30
本日21:00からは、宇野常寛の〈木曜解放区 〉生放送です!
〈木曜解放区〉は、宇野常寛が今週気になったニュースや、「スッキリ!!」で語り残した話題を思う存分語り尽くす生放送番組です。
時事問題の解説、いま最も論じたい作品を語り倒す「今週の1本」、PLANETSの活動を編集者視点で振り返る「今週のPLANETS」、週替りアシスタントナビゲーターの特別企画、そして皆さんからのメールなど、盛りだくさんの内容でお届けします。
★★今夜のラインナップ★★メールテーマ「音楽」アシスタントナビゲーター特別コーナー…「長谷川リョーの論点」 and more…
今夜の放送もお見逃しなく!▼放送情報放送日時:本日9月14日(木)21:00〜22:45☆☆放送URLはこちら☆☆
▼出演者
ナビゲーター:宇野常寛
アシスタントナビゲーター:長谷川リョー(ライター・編集者)
▼ハッシュタグ
Twitterのハッ -
井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第19回 我々はどこまでいい加減なプレイヤーたりうるか?―DQ11における「死」について【毎月第2木曜配信】
2017-09-14 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。「キノコで巨大化」「人の家のタンスを開ける」など、「メカニクス」と「表象」がしばしば乖離するゲームの世界。今回は番外編として、『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』の話題を中心に、「いい加減なプレイヤー」をめぐる問について考えます。
(今回は、番外編としてDQ11の話をメインにさせていただきます)
3DS版『ドラゴンクエストXI』(以下DQ11)をクリアーした。クリアー後のアレはもちろんのこと、時渡りの迷宮も最後まで終えた。 そういうわけで、いまDQ11について書かなければ、たぶん次に書く機会というのはないだろうと思うのでDQ11の話をメインに書かせていただく。とくに「ゲームとは何か」に関わる論点として、今作は「死」や「ゲームオーバー」の問題を扱っているが、けっこうざっくりとした表現の仕方だなという感想を抱いた。このざっくりとした表現をどのようにとらえるのかというのは、「ゲームというメディアにおける表象」とどのような態度で向き合うべきか、を考えたときいくつかの重要な問いを含んでいるように思うので、その問題について書きたいと思う。[1] 今回、「死」や「ゲームオーバー」の表現について2つの点で今までとは異なった試みをしている。単にストーリーのみを取り出してみた場合、なるほど、これを「よかった」という感想を抱く人が一定数いるのはわかるようなものだ。他方、逆の評価をした人も当然いたはずのものだ。たとえば『MOON』(1997,ASCII)を褒める人であれば、今回のDQ11についてどのような評価をするか、悩ましい表現があった。
ゲームというメディアのなかでこのようなストーリーテリングをすることについて、いくつかの重要な前提を確認したうえで、この問題をどう評価するのかを述べたい。 いくつかの前提というのは、第一にゲームにおける「喩え」とどのように接するかということ。第二に我々が複合的なリアリティがつなぎ合わされたメディアとどう接するかということだ。 結論から言えば、この二つの問題にどのように扱うかによって、同じ作品に対して、まったく逆の感想を抱くことが可能だ。 これらの前提について確認していくことからはじめよう。 なお、以下のテキストは後半から当然のようにネタバレを含むのでご了承いただきたい。
*メカニクスと表象:「喩え」の設計
ゲームデザインにおける重要なポイントという話をする場合、難易度調整(チューニング、バランシング)、レベルデザイン(マップ・デザイン)、メカニクスデザインなどといった要素がトップクラスのものとして挙げられること。これらに並んで重要なものの一つが、ゲームデザインにおける「喩え」をどのように設計するかということだろう。 ゲームを設計する側にまわらないと気付きにくいことだが、多くのゲームはさまざまなポイントの集合でできあがっている。ポイントA:30、ポイントB:50、ポイントC:32を割りふって…といったようなポイントの集合としてゲームはみなすことはできる。シューティング・ゲームであればポイントABCはそれぞれ機体の「連射速度」「攻撃力」「機体速度」かもしれないし、ギャルゲーであればキャラごとの「好感度」「友好度」「体力」かもしれないし、レースゲームであればマシンごとの「カーブ性能」「最高速度」「加速度」かもしれない。ゲームデザインというのはこれらの「ポイント」のどのように名前を付けていくか、という作業でもある。 この問題について極めて意識的な発言を繰り返しているのは宮本茂だろう。発言を引用する。[2]
遊びには、ゴルフタイプの「ボールをゴールの穴に入れるという、みんなが納得できるルールの遊び」と、野球タイプの「誰かがつくったルールの遊び」があるのです。だから、ゴルフタイプのゲームの場合はルールが明確なため、つくるのが比較的ラクです。それに比べて野球タイプは非常に難しい。『ピクミン』は野球タイプだったため、ルールづくりには非常に悩まされました。 最初は、「一定数以上のピクミンを集めればクリアー」というルールだったのです。でも、この「一定数」って誰が決めたの?ということになりますよね。そこで思いついたのが、「特定の数以上でないと運べない荷物を回収する」というルール。小さいものからだんだんと運びはじめるので、プレイしていくと「大きなものは重たい」という共通の認識ができるのです。そのため、たくさんのピクミンが必要になるゲーム展開となり、結果的に、ピクミンを集めるゲームとなったのです。 『ピクミン』のような野球タイプのゲームは、自然な形で目的を達成させるルールをつくることが重要です。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
★号外★ 9/15(金)開催! 柴那典×森直人「情報環境は映画/音楽の快楽をどう変えるのか コミュニケーション消費以降の文化とその批評について」
2017-09-13 07:30
イベント情報のお知らせです!
今週9月15日(金)19:30〜「映画と音楽」をテーマにしたイベントを開催します。
ハリウッドの大作映画が脱物語化し、ノスタルジー産業化し、アニメ/特撮化し、大衆音楽がフェスとiTunesに引き裂かれて、かつてのレコード文化を捨てたとき、20世紀を支えた映画/ポピュラー・ミュージックはいかに変質しつつあるのでしょうか?
音楽ジャーナリスト・柴那典さんと映画評論家・森直人さんが語り合います。
会員割引券もあります! ぜひ皆様お越し下さい。
★★イベント詳細・お申込はこちら★★
▼概要
日時:2017年9月15日(金)
19:00 開場(受付開始) 19:30 開演 21:00 終演予定
場所:STRATUS TOKYO-Mistletoe Base Camp Tokyo-
東京都 港区 北青山 2-9-5 スタジアムプレイス青山 8F
▼登壇者プロフィール( -
【新連載】長谷川リョー『考えるを考える』 第1回 思想家・山口揚平に聞く、「意識をコントロールし、情報を有機化する方法」
2017-09-13 07:00
今回より始まる新連載『考えるを考える』。あえて、テーマは設けず、僕、長谷川リョーが今一番会いたい人に話を伺っていきます。「会いたい」の基準は一つ。ただ情報を持っているだけではなく、思考をしている人です。第一回目にご登場いただくのは、貨幣論・情報化社会論を専門とする思想家であり、事業家の山口揚平さん。今回取材をさせていただいた僕とは東京大学大学院の同級生でした。 トランプが大統領に当選したとき、改めて気づかされたフィルターバブルの厚み。毎日のように誰かに取材をし、記事を書く私ですが、その営為は決定的にある情報系の枠内に限定されているのではないかと危惧を持つようになりました。それ以来、「そもそも」と考えるメタ思考の重要性について考える機会が増えています。 「20代から本や新聞を読むのを止めた」という山口さんにお話を伺うため、今回は軽井沢のご自宅へ。情報と思考の違い、シングルイシューの見つけ方、お金よりも大切なクレジットとクリエイティビティの育み方まで、普段なかなか議論することの少ない抽象的な問いに答えていただきました。
長谷川 日本のような成熟した先進国の場合、社会問題が複雑化していますよね。働き方がどうとか、子育てがどうとか。一方で、発展途上国の場合は、「明日食べる米がないこと」がシングルイシューになります。本日はシングルイシューを見定めるための視座や、考えることについて考えるメタ思考についてお話を伺えればと考えています。
山口 たしかに、日本における問題は有機的なのでシングルイシューを特定するのは難しいですね。でも本質にメスをいれれば問題は氷解します。いずれにしてもまずは、問題に切り込む強い視点を持つことが重要でしょう。そこから広範に広げてゆく。僕の場合は、大学に入る前から「お金とは何か?」、つまり貨幣論について考えてきました。7年ほどかけて書き上げたのが、『なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか?』です。
経済のツールである「お金」を切り口に、「社会とはなにか?」、「テクノロジーとはなにか?」、「人間とはなにか?」を辿って行きました。自分が関心を持っているものから周辺のテーマを見通し、多面的に捉えていくことで、同じ現象もいろんな角度から入っていけるはずです。なので、入り口はなんでも良いと思います。
長谷川 ご自身のキャリアも「お金」に密接に関わるものですよね?
山口 はい。20代の頃はコンサルティング会社でM&Aの仕事をやっていました。その当時のコンサルティング会社は今の業務改革や統計解析とは違い、情報や知恵を売るのではなく、「考えること」を提供していたんです。いわば、たった一つの本質解を出すための「思考労働者」。この頃に「考えることについて」すごく考えました。それが今につながる根本的な自分の哲学につながっています。
M&Aをやるということは、会社を丸ごと見なくてはいけません。しかも限られた時間で。会社には人事、財務、税務、プロダクト、歴史があり、複合的な存在です。それら全てを俯瞰的に見通した上で、その会社を動かす本質を特定するのがM&Aのもっとも重要な仕事でした。てこの原理のように、本質に小さな力を加えることがもっとも生産性が高まることをこのときに理解したんですね。
よく、「PDCA(plan-do-check-act)」といいますよね。このなかで、9.5割重要なのは「Plan(計画)」です。残りの0.5が「Action(実行)」。M&Aの場合は、一度しかAction(実行)のボタンを押しません。このボタンのことを「ホットボタン」や「コアバリュー」といい、そのボタンを的確に押すために有機的なつながりの中から本質を特定するのです。ですから3ヶ月の仕事のなかで、2.5ヶ月以上は情報調査やインタビューをやりながらも、頭の中では考えごとをしていましたね。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
池田明季哉 "kakkoii"の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝 序章(後編)「変身サイボーグ──戦後日本という母から生まれた新たな可能性」【不定期配信】
2017-09-12 07:00
デザイナーの池田明季哉さんによる連載『"kakkoii"の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。G.I.ジョーが描いた理想の男性性について論じた前回に引き続き、20世紀末に花開いたボーイズトイ文化の原点とも言える変身サイボーグと、そのデザインがもたらしたユニークな身体性について語ります。
序章の前編では、20世紀におけるアメリカ的な男性性の変遷をまとめた。G.I.ジョーというおもちゃを通じて浮かび上がってきた20世紀アメリカにおける理想の男性像とは、最強の肉体と最強の知性を持つ「軍人」であった。そしてそのイメージは、20世紀後半においてフィクションのスーパーヒーローに引き継がれた。スーパーヒーローは悩み苦しむ弱い心をさらけ出し、それまでのハードボイルドな男性像を更新したことで人気を博したものの、身体性においては軍人的マッチョイズムから逃れることはできず、アクションフィギュアの体型はむしろ筋肉が極端に強調されたものへと変化していく。 時を同じくして、日本にもG.I.ジョーの遺伝子を受け継ぐおもちゃが登場する。それがタカラ社(現タカラトミー社)による、日本ボーイズトイ文化の原点とも言える傑作、「変身サイボーグ」である。後編においては、戦後まもない40年代半ばから70年代に至って変身サイボーグが誕生するまでを振り返り、これから語ろうとしている「世紀末ボーイズトイ」の位置付けを明確にしたい。
おもちゃ大国と軍国主義の挫折
戦前から戦中においては、アメリカと同じように、日本における理想の男性性もまた概ね軍人と結びついていた。 日本は昭和に入った1920年代の段階ですでにおもちゃ産業が大きく発展しており、世界恐慌による不況への対応として、おもちゃの輸出が真剣に評価されていたほどだった。おもちゃの領域においては、クールジャパン的な発想はこの時点で既に生まれていたと言える。 このとき流行していたのは、やはり戦争おもちゃだった。日清戦争から日露戦争、そして第一次世界大戦に勝利することによって列強に並んだ日本において、少年たちは兵士や兵器に憧れ、おもちゃもそれに応えるものが作られていった。戦争によってメディアとなるおもちゃこそ作られなくなったものの、この流れは第二次世界大戦に至ってピークを迎える。そして敗戦と同時に、大日本帝国軍が理想としたような名誉を重んじ国家に殉じていくような男性性は、一旦徹底的に否定されることとなるのである。 こうした戦前から戦中の日本における理想の男性性の問題は、男性学的には極めて重要である。しかし他の多くの文化と同じように、おもちゃ文化もまた戦前〜戦中から分断されることによって戦後の文化が発展していった。そのためここではあまり詳細に分析することはせず、代わりに戦後のおもちゃ文化について論を進めていきたい。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 第10回 戦後ロボットアニメの「終わり」のはじまり(PLANETSアーカイブス)
2017-09-11 07:00
今回の再配信は「京都精華大学〈サブカルチャー〉論」をお届けします。 富野由悠季『逆襲のシャア』で明らかにされた、ロボットアニメにおける〈成熟の不可能性〉というテーマは、80年代末の『機動警察パトレイバー』によるポリティカル・フィクション的なアプローチを経た後、1995年の『新世紀エヴァンゲリオン』によって再浮上します(この原稿は、京都精華大学 ポピュラーカルチャー学部 2016年5月13日の講義を再構成したものです/2016年10月28日の記事の再配信です)。
ロボットの意味が脱臭された『機動警察パトレイバー』
たとえばバブル絶頂期の80年代末に人気となった『機動警察パトレイバー』というマンガ・アニメ作品があります。ブルドーザーやクレーンといった重機の役割を果たすロボット「レイバー」が普及している近未来の東京では、レイバーを悪用した犯罪が多発している。そこで警視庁がレイバーを導入して犯罪を取り締まっていくという物語です。 この『パトレイバー』のメインは若い警官たちの青春ドラマです。おそらく日本で初めて、警察という官僚組織を細かく描いてコメディドラマにした作品で、要は『踊る大捜査線』の元ネタですね。 『パトレイバー』においてロボットは「あったほうが絵的にかっこいい」ぐらいの扱いになっています。むしろロボットというSF的なアイテムを導入することによって、戦争もなければ民族対立も少ない現代日本において政治的なフィクションを成立させているところに意義がある作品ですね。たとえば劇場版第2作の『機動警察パトレイバー2 the Movie』はクーデターものです。ロボットアニメという器を使って、東京という大都市と、近未来社会のクーデターシミュレーションを描いているんです。
少し『パトレイバー2』を観てみましょう。これは敵のクーデター部隊が、主人公たちの所属するパトレイバー中隊を襲撃するシーンですね。戦闘ヘリの攻撃に、パトレイバーたちは起動する間もなく格納庫に置かれたまま一方的に破壊されていきます。 これとても象徴的なシーンです。レイバーはあくまでも重機の延長線上であって、戦闘ヘリの前では太刀打ちできないということが強調されています。企画段階から関わってアニメ監督を担当したのは『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』の押井守です。押井守にとって『パトレイバー』のロボットはあくまで企画を通すための方便でしかなく、実質的には東京の大規模テロのシミュレーションがしたかったんです。だからこそ、ロボットの意味を徹底的に否定しているわけです。近未来の日本に人型の重機が普及したとしても、その軍事的な価値はゼロだと、かなり露悪的にシミュレーションして見せているわけですね。 こうして、80年代のロボットアニメのノウハウを受け継ぎながらも内側から更新していくようなかたちでロボットアニメは進化していくことになります。 ただし、ロボットや怪獣などのファンタジー的なアイテムを用いることによって「日本の官僚組織や企業社会がどう動くか?」というシミュレーションをやる『パトレイバー』のメソッドは、むしろ『躍る大捜査線』や『平成ガメラシリーズ』といった実写作品のほうに受け継がれていくことになります。こうした潮流については別の回で詳しく扱おうと思います。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
宇野常寛『汎イメージ論 中間のものたちと秩序なきピースのゆくえ』第一回 中間のものについて(3)【金曜日配信】
2017-09-08 07:00
本誌編集長・宇野常寛による連載『汎イメージ論 中間のものたちと秩序なきピースのゆくえ』。今回は、20世紀に文化の中心だった虚構が力を失い、一気に現実へと傾いていく21世紀の現状を整理しながら、「中間のもの」を扱えるインターネット本来の可能性について論じていきます。 (初出:『小説トリッパー』2017夏号)
4 ほんとうのインターネットの話をしよう
しかし、インターネットとは本来もっと異なるもののはずだった。たとえば前述の「PLANETS」vol.8では以下のような議論が展開されている。
映像の二〇世紀と呼ばれた前世紀は、まさにこの魔法の装置によって社会が決定的に拡大した時代だった。
実のところ厳密にはピントすら合っていない人間の目を、意識を通して認識されたものとして誰かと共有することは、本来は不可能なことだ。しかし人類はこの解離した、三次元の空間を二次元の平面に統合するという術を編み出した。三次元の、解離したものを、二次元に統合して共有可能にすること。パースペクティブという論理を用いて造られた虚構を媒介にすることによって、文脈の共有を支援することに私たちは成功したのだ。そして一九世紀と二〇世紀の変わり目に登場した映像という装置は、その平面の完成形だった。現実を平面に整理し、解離した人間の認識を統合した画像が連続し、擬似体験を形成する。このとき人類ははじめて整理され、統合された他人の経験(カメラの視点)を共有することが可能になったのだ。
こうして成立した映像が放送技術と結託することで、二〇世紀の国民国家は広く複雑化した社会の維持が可能になった。しかし問題は映像、あるいは当時の技術が極端なふたつの人間観しか得られていなかったことだ。
たとえば映画とは極めて能動的な観客を想定したメディアだ。劇場へ足を運び、演目を選び、木戸銭を払い、物語を受け止める態勢を整え暗闇の中に静止している。対してテレビは、極めて受動的な視聴者を想定したメディアだ。生活空間内における流しっぱなしを想定し、散漫な意識の中で一瞬だけ注意を引くことに注力する。
この「映像の世紀」における観客/視聴者の対比は、現在の民主主義の制度が想定する人間像に一致する。それは能動的で理性的で意識の高い市民と、受動的で感情的で意識の低い大衆だ。これは同時に上院/下院、参議院/衆議院の峻別でもあり、そしてそのまま映画/テレビが前提とする人間像に相応している。
そう、要するに前世紀までの人類は、極端に意識の高い市民と低い大衆、ふたつの人間像を想定し、それぞれに対応したシステムを並走させ、両者でバランスをとるという発想を根底に社会を形成していたのだ。
しかし、インターネットは本来この中間のものだった。正確には人間の絶えず変化する能動性に対応し得るメディアだった。人間は市民ほど能動的でも、大衆ほど受動的でもない。これまで(二〇世紀まで)は単にそれが技術的に対応できずに極端な人間像をふたつ想定し、それを並走させていただけにすぎないのではないか。
しかしこれからは違う。いや、そうではないやり方を考えなければいけない。インターネットは、そしてその背景をなす情報技術は、本来は中間のものにアプローチできるものなのだから(2)。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。