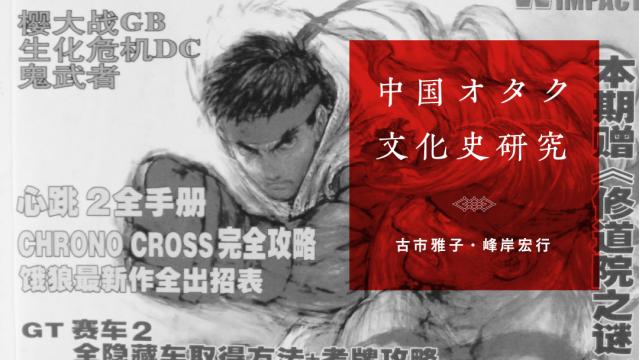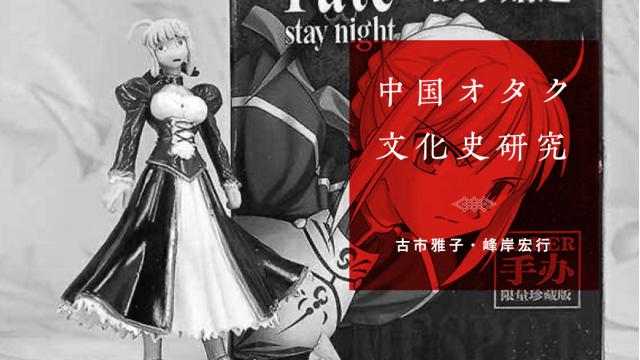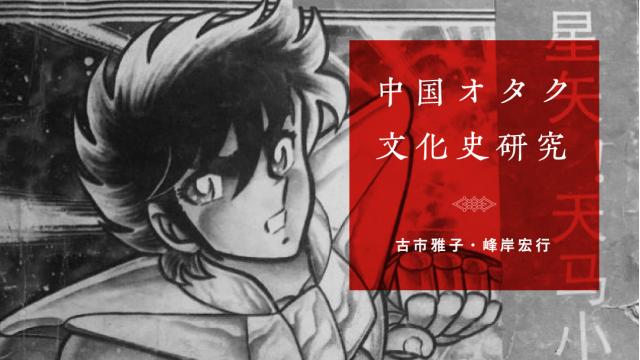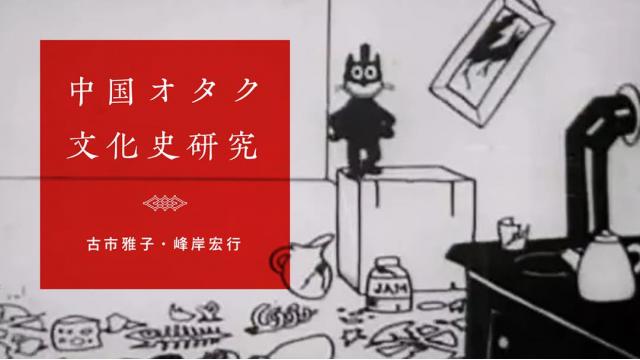-
国家規制下の初期インターネットで発展した中国アニメコミュニティ|古市雅子・峰岸宏行
2021-04-06 07:00
北京大学助教授の古市雅子さん、中国でゲーム・アニメ関連のコンテンツビジネスに10年以上携わる峰岸宏行さんのコンビによる連載「中国オタク文化史研究」の第6回。今回は、2000年代初頭から中盤にかけて日本アニメのテレビ放映が次第に規制されていく一方で、インターネット初期のフォーラムやエリート大学の学生サークルの行動力によって各地に点在していたコンテンツ愛好者たちが接続され、中国全域に「オタク」という存在様式が増殖していくプロセスを辿ります。
古市雅子・峰岸宏行 中国オタク文化史研究第6回 国家規制下の初期インターネットで発展した中国アニメコミュニティ
前回、インターネットの普及により、ゲームコミュニティが形成された過程について考察しましたが、同じことがアニメなど他のジャンルにも同時に起こっていました。 テレビアニメと漫画から始まった中国における日本コンテンツはその後、VCDやゲームセンターの普及、情報誌の出現により全国各地に愛好者を増やしてきましたが、「新浪」(sina)、「捜狐」(sohu)、「網易」(Netease)等の2000年代のIT企業を代表する大手ポータルサイトがニュース配信を開始し、ナスダックに上場した2000年を境に、それまで全国各地に点として存在していたコンテンツ消費者が、インターネットを通してつながり、フォーラム、そして大学サークルをおもなプラットフォームとしてコミュニティを形成し、大きな波となっていきます。
1.社会現象を起こした日本アニメ
中国では、90%以上の家庭にテレビが普及したのは2000年頃だと言われています。『鉄腕アトム』以降、数々の日本アニメが放送されてきましたが、2004年に国家ラジオ・テレビ総局(国家广播电视总局)が「我が国のアニメ産業発展に関する若干の意見」(「关于发展我国影视动画产业的若干意见」)を発表、産業保護政策の一環として、毎四半期における海外アニメと国産アニメのテレビ放送における比率を国産アニメが6割以上にしなければならないと規定し、全国の省レベル、副省レベルのテレビ局のうち1/3以上が子供チャンネルを開設することと定めました。 当時はアニメだけではなく、テレビドラマなども香港、台湾のものが多数を占めるような状況であったため、テレビ番組全体に対する危機意識が底辺にありました。中でも子供に対する日本アニメの影響力には大きな危機感を抱いていたのでしょう。この頃には、多額の広告収入を見込める看板番組も増え、地方局の運営も軌道に乗るようになっていました。子供番組、特に国産アニメの制作に本格的にテコ入れするべき時期が来たと国が判断したとも言えます。 そして2006年には全国のテレビ局で17時〜20時というゴールデンタイムにおける海外アニメの放送が禁止となり、国産アニメと海外アニメの割合が6:4から7:3に引き上げられました。2008年には放送禁止時間が17時〜21時までとなり、こうして実質的に海外のアニメはテレビから締め出されました。 2006年までには、テレビ放送されるアニメの80%が日本アニメになっていたと言われています。そのほとんどが、広州電視台や瀋陽電視台など地方のテレビ局が日本ではなく香港や台湾を経由して取得、吹き替えしたものでした。第2回で書いたとおり、地方局が買い付け、吹き替えしたものをその他の地方局が次々と放送していくかたちで全国に広まる「波状放送」や、いくつかの地方局での放送のみで終わったものなど、さまざまな作品がさまざまな経路で買い付けされ、放送されていました。省レベルのテレビ局でも30以上あるため、どのような作品がどこで放送されていたのか、まだ筆者も把握しきれていません。1980年代の『花の子ルンルン』(中題:花仙子)や『ニルスのふしぎな旅』(中題:骑鹅历险记)から始まり、『中華一番』(中題:中华小当家)、『キャプテン翼』(中題:足球小将)、『ドラゴンボール』(中題:龙珠)、『聖闘士星矢』(中題:圣斗士星矢)、『クレヨンしんちゃん』(中題:蜡笔小新)、『テニスの王子様』(中題:网球小王子)、『ポケットモンスター』(中題:口袋宝贝)、『デジタルモンスター』(中題:数码宝贝)、『赤ずきんチャチャ』(中題:小红帽恰恰)、『新世紀エヴァンゲリオン』(中題:新世纪福音战士)、『ヒカルの碁』(中題:棋魂)、『彼氏彼女の事情』(中題:青春翅翅板)など、ジャンルを問わず、今から見ると考えられないような作品が放送され、また日本アニメの情報番組も数多く存在していました。
そうした中で、社会現象を巻き起こしたとも言えるほど大きな影響を与えたのが『SLAM DUNK』(中題:灌篮高手 1993年)と『美少女戦士セーラームーン』(中題:美少女战士 1992年)です。その頃には、すでに大学受験が激化し、勉強一色の学校生活を送ることが多かった中国の子供たちとって、おしゃれな制服を着て通学し、部活動に熱中したり、放課後に友人と遊びに行ったり、という日本の理想化された学校生活は憧れになっていたと言われています。
女の子はみんな『美少女戦士セーラームーン』に夢中になりました。日本の制服への強いあこがれは、ここから始まり、AKB48、「ラブライブ!」を経て現在まで一つの流れになっています。「なぜこんなに多くの人が『セーラームーン』を好きなのか。古参がイラスト1枚で教えます」というコラムにその理由が書かれています。 それは「1.主人公がかわいい服を着て世界を救うアニメは他にないから。2.世界のトレンドの服を着ているから。3.ビキニだから。4.みんなかわいいから」。[1] また、女の子であっても、「うさぎが変身するときは、体がブラウン管の中で水晶のようにキラキラ光り、胸や足のやわらかな曲線が美少女戦士のスタイルを際立たせるのだけれど、当時はあまりにも純粋だったので、毎回そのシーンになると顔が赤くなってドキドキが止まらなくなり、もし親が来ようものなら慌ててチャンネルを変えていた」[2]とのことです。上海生まれ香港育ち、ドイツのクオーターで日本のファッション雑誌やレミオロメンのMV、蜷川実花監督の映画『ヘルター・スケルター』やハリウッド映画にも出演経験を持つモデルで女優のアンジェラ・ベイビーは、中華圏を代表するセーラームーン好きで、コスプレの写真をSNSに投稿したり、展覧会を見に東京まで足を運んだりすることで有名です。「なんで女の子はみんなセーラームーンをアイコンにするの?」[3]というスレッドが今でも立つほど、中国の女性に根強い人気を誇っています。 『SLAM DUNK』は、それまでスポーツといえば卓球とバドミントンだった中国で、バスケットボールを大流行させました。男の子は流川に憧れ、似たようなリュックを背負って学校に行き、放課後はバスケットボールをするのが「イケてる中高生」でした。 中国人として初めてアメリカのMBAで活躍した国民的スポーツ選手、姚明をはじめ、中国のバスケットボールプロリーグ(略称CBA)で活躍する選手たちも『SLAM DUNK』を見ていたと言っています。
「『トレーニング以外の時間はゲームに多く費やしてきたけれど、バスケットボールのゲームはまったくやらない。どんなにリアルでも嘘に感じてしまうから』。でも彼(注:姚明)も『SLAM DUNK』だけは見た。当時はものすごいブームとなっていて、見ないと他の人と話ができなかったのだ」「CBAで最もかっこいいと言われる楊鳴は、最初から流川が好きだったという。『小学校のときだった。もうバスケを始めていたから、(「SLAM DUNK」は)大好きだった』。楊鳴はひと目見たときから流川楓が好きだったという。『アニメでは彼が一番バスケがうまくて、一番かっこよかった。大好きだったんだ!』」「孟鋒も小学生の時に見た。まだバスケはやっていなかったという。『最初は大げさだなと思った。知ってることもあった』。例えば速攻のときは一人でディフェンスからオフェンスへ移動する。二人でパスしながら進むより絶対に早いから、とか。でも何話か見るうちにストーリーに心を動かされた。『そのうちに流川楓が大好きになった。彼のダンクはほんとにうまいんだ!』孟はその時まだダンクシュートができなかったが、『SLAM DUNK』を見てから『ダンクシュートってどんな感じかやってみたくてたまらなくなったんだ』という。それまで彼は、父親にバスケをしようと誘われても断っていたが、意外にもその後コートに足を踏み入れることとなった。孟は冗談交じりにいう。『SLAM DUNK』がなかったら、今こうしてプロリーグにいることはなかったかもしれない。」[4]
2.修正された『カードキャプターさくら』
他国のコンテンツを輸入する際、自国のルールに従って修正を加えることはよくあります。アメリカでも日本アニメの登場人物の名前をすべて白人風の英語名に書き換えたり、おにぎりをハンバーガーに描き替えたりしていました。アメリカほどではないにせよ、中国でも作品によっては修正が加えられます。 大きく修正された作品のひとつに『カードキャプターさくら』(中題:魔卡少女樱 1998年)があります。『カードキャプターさくら』は女性作家グループCLAMPによる魔法少女漫画で、アニメ化、ゲーム化や商品化とマルチプラットフォームで展開した大人気作です。中国でも高い人気がありました。
父、兄と3人で暮らす小学校4年生の木之元桜(以下、さくら)は父の書庫で不思議な本を発見し、開くと中からケルべロスという封印の獣を自称する生き物が現れます。ケルべロス、通称ケロちゃんは、「さくらの住む町に魔法使いが作ったカード(クロウカード)がばらまかれてしまった。封印が解かれると災いをもたらされるから、なんとかしなければ」という旨を告げます。かくしてさくらは、ケロちゃん、親友の大道寺知世、カードを集めにきた香港留学生の李小狼と共にクロウカードを探し、事件を解決しながらカードを集めに回る、というのがクロウカード編の内容で、クロウカードの所持者となったさくらが新たな困難に立ち向かうさくらカード編、中学に進学した後のクリアカード編が続きます。
本作は『なかよし』で連載されていた子供向けの作品ですが、どこを修正されたのでしょうか。例えばさくらと小狼(しゃおらん)の恋愛に関する箇所です。 カードを集めるライバルである二人ですが、いつしかお互い意識しあう関係になります。さくらが兄の親友である雪兎に抱いていた恋心が叶わず、小狼がいつのまにかさくらのことばかり考えていると気づく頃、二人でエレベーターに閉じ込められ、そこで空気が変わります。さくらカード編の最後で小狼がさくらに告白し返事を待つのですが、マンガでは小狼が香港に帰る際に、そしてアニメ版では小狼帰国後の劇場版第2作終盤でめでたく結ばれます。
しかし、中国テレビ放送版ではそうはなりませんでした。
【4/8(木)まで】特別電子書籍+オンライン講義全3回つき先行販売中!ドラマ評論家・成馬零一 最新刊『テレビドラマクロニクル 1990→2020』バブルの夢に浮かれた1990年からコロナ禍に揺れる2020年まで、480ページの大ボリュームで贈る、現代テレビドラマ批評の決定版。[カバーモデル:のん]詳細はこちらから。
-
「鏰児厅(ゲーセン)」から「網吧(ネットカフェ)」へ〜中国ゲームコミュニティの勃興|古市雅子・峰岸宏行
2021-02-24 07:00
北京大学助教授の古市雅子さん、中国でゲーム・アニメ関連のコンテンツビジネスに10年以上携わる峰岸宏行さんのコンビによる連載「中国オタク文化史研究」の第5回。今回は、1990年代ごろから「鏰児厅」(ブアル・ティン)と呼ばれたゲームセンターや攻略雑誌を核に発生したゲームファンたちのつくる「場」が、2000年代のインターネットカフェ「網吧」(ワン・バァ)の爆発的な普及を経て、様々なコミュニティを増殖させていく過程を辿ります。
古市雅子・峰岸宏行 中国オタク文化史研究第5回 「鏰児厅(ゲーセン)」から「網吧(ネットカフェ)」へ〜中国ゲームコミュニティの勃興
これまでの連載で、中国にとって日本コンテンツの影響がいかに大きかったかを、第1〜3回にかけて『鉄腕アトム』、『トランスフォーマー』、『聖闘士星矢』等のアニメ作品を通して紹介してきました。 1990年代以前はテレビや連環画、以降はそれに加えてゲームや雑誌が消費者に大きく影響を及ぼしていました。第4回「VCDと情報誌が育んだ中国アニメ・ゲーム文化」でもお伝えしたように、中国ではゲーム雑誌が原作となる日本のアニメなどのコンテンツを紹介した土壌があります。ゲームを通して、原作コンテンツを知るという形式は、中国においても角川を筆頭とした日本のメディアミックス展開が成功した例として捉えられるでしょう。 しかし、2000年代にインターネットが普及したことにより、その状況も大きく変わっていきます。今回はゲームという切り口から2000年前後の中国の日本コンテンツ需要の過程を紹介したいと思います。
1.鏰児厅が培ったゲームセンター文化
かつて、現在の北京オリンピックメインスタジアム「鳥巣」のすぐ近くに、「北京康楽宮」という中国で最高峰の室内レクリエーション施設がありました。1990年設立、すべり台のある大型屋内プールやわざわざアメリカから取り寄せた26レーンもあるボーリング場、30のビリヤード台、大きなダンスホールに800名収容の劇場と、同時に1000人は遊べる国内最大規模の高級レジャー施設です。北京市民の平均収入が月900元弱[1]と言われるなか、そこで遊ぼうと思うと一人1000元はかかるため、北京市民にとっては憧れの場所でした。 そして同時に子供たちにも非常に人気の場所でした。なぜならゲームセンターがあったからです。ゲームセンターは北京の子供たちの間では「鏰児厅」(ブアル・ティン)[2]と呼ばれていました。「鏰児」は北京の方言で「メダル」、そして「厅」はホール、つまり「メダルホール」という意味です。
▲当時北京康楽宮で使用されていたメダル
▲1991年撮影された康楽宮。現在は48階建てのオフィスビルになっている。(出典:北京康乐宫拆了)
残念ながら、康楽宮内部の写真は見つかりませんでしたが、当時遊びに行ったことがある人から話を聞きました。魏然は今も日本ファルコム社の『英雄伝説 軌跡』(日本ファルコム・2004~)シリーズをこよなく愛し、最も好きなアニメは『金色のガッシュベル』、最も好きな漫画は『魔人探偵脳噛ネウロ』という、筋金入りの日本コンテンツオタクです。筆者・峰岸が北京で経営していたメイドレストランの常連でした。
「僕が初めて康楽宮を訪れたのは、小学1〜2年生の時(注:1993〜94年)だと思う。その時からゲームセンターはあって、メダルゲームなど様々な遊びがあった。」
北京で銀行に勤める魏然は、子供のころから様々な日本のゲームをプレイしてきた1980年代生まれの生粋の北京っ子です。
「メダルゲームの他に、体験系アーケードゲームの『ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド』(セガ・1997)や『Nascar Racing』(セガ・2000)、シューティングの『1943ミッドウェイ海戦』(カプコン・1987)、3人でプレイできる『ナイツ オブ ザ ラウンド』(カプコン・1992)、『天地を喰らう』(カプコン・1989)があった。大人気だったのが格闘ゲームの『街覇』(別名『街頭覇王』、原題:ストリートファイターII、カプコン・1991~)や『拳皇』(原題:THE KING OF FIGHTERS、SNK・1994~)シリーズ。特に『街覇』は沢山のバージョンがあって、すごく楽しかった。それと『拳皇』の周りには本当に多くの人が集まってた。 昔はみんながみんなそんなにうまくなかったから、うまい人が来たら、みんなでお金出しあってクリアを手伝ってたんだよ。自分じゃラスボスまで到達できないからね。そうしてゲームやストーリーを楽しんでた人も多かったみたいだね。今のゲーム配信を見てる感じ。僕もその一人だったよ」
北京康楽宮は中国でもっとも高価な施設ですが、1990年代から2000年代、北京市内にある比較的規模の大きな鏰児厅だけでも磁器口の小白楼、団結湖の快楽島、官園の小児活動中心、北京展覧館の向い、北京藍島大廈の6階、北京人民大学裏手の夢幻などがあり、路地裏の2〜3台しかないような鏰児厅も含めるとそれこそ無数にありました。
2000年代に入ると、鏰児厅には『湾岸ミッドナイト』(ナムコ・2004)や『太鼓の達人』(バンダイナムコアミューズメント・2001)など、対戦系よりも体験系のゲームのほうが増えていき、現在ではゲームセンターの直訳である「游戏厅」という名称で北京のいくつかのデパートで稼働しています。 とりわけ『太鼓の達人』シリーズの人気は非常に高く、同シリーズを入り口にアーケードゲームに興味を持つ子供も増加するなど、ゲームセンターは仲間が集まる場としての役割を果たしました。その後、ゲームセンターが果たしたリアルなコミュニケーションの「場」としての役割は、パソコンの普及とともに比較にならない規模でオンラインに継承されるとともに、リアルにおいては飲食店や同人イベントへと移行していきます。鏰児厅は、こうして爆発的に増加することになるコミュニティの基礎を生み出したのです。
ゲームのプレイヤーが増え、接する時間が増えることによって、よりうまくプレイする方法やまだ見ぬ必殺技に興味を持つのはごく自然のことです。日本でも1980年代には田尻智が1983年に同人サークル「ゲームフリーク」を立ち上げ、グループや一個人がゲームの攻略情報を独自にまとめて発行していたように、中国でもゲーム熱が上がっていくことによって、攻略法を求めるプレイヤーの増加にともない、ビジネス的にも売れる攻略本が登場します。それがゲーム情報誌「電子遊戯軟件」のムック『格闘天書』です。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
VCDと情報誌が育んだ中国アニメ・ゲーム文化|古市雅子・峰岸宏行
2021-01-28 07:00
北京大学助教授の古市雅子さん、中国でゲーム・アニメ関連のコンテンツビジネスに10年以上携わる峰岸宏行さんのコンビによる連載「中国オタク文化史研究」の第4回。1995年の外貨兌換券の廃止前後、中国国内にも市場経済の恩恵が行き渡り、一般家庭にビデオCD(VCD)デッキが爆発的に普及します。そこから映画やアニメを中心とした大量の海賊版コンテンツが流通するようになるなか、日本産のゲームやアニメを紹介する情報誌が次々と創刊。現在に続く中国オタク文化の礎を築いていきます。
古市雅子・峰岸宏行 中国オタク文化史研究第4回 VCDと情報誌が育んだ中国アニメ・ゲーム文化
1990年代は日本アニメの黄金期の一つで、国際的にも多くの作品が注目を集め、ブレイクしていった時期にあたります。そして中国では、外貨兌換券が廃止され、家電製品が普及するなか、ビデオCD(VCD)を通して大量の日本のアニメとゲームが流入した時期でもあります。また、挿入歌やBGMを収録したCD、キャラクターグッズ、プラモなども多数販売されました。大量のコンテンツから好きな作品を見つけるために、また、アニメやゲームについて論じるために、情報誌が続々と創刊され、大きな影響力をもちました。
1.兌換券の廃止
1995年、中国の消費を変える大きな出来事が起きます。1月1日をもって、15年続いた兌換券が廃止されたのです。 中国では、物資の不足と外貨管理を理由に、1980年から通常の人民元とは別に兌換券を使用していました。そもそも主食や油、肉などは配給制で、「糧票」と呼ばれる主食用チケットに代表される様々なチケットと引き換え制でしたが、まずそれが徐々に地方から廃止されていき、1993年に正式に全廃となります。しかし兌換券は95年までかかりました。 兌換券とは、正式名称を外貨兌換券(外汇兑换券)といい、人民元と等価値で、外国人が中国で消費活動を行う際に使用する紙幣を指します。中国銀行しか発行できない紙幣で、外貨はすべて人民元ではなくこの兌換券に換金し、国内で使用します。この時代、中国では外国人と中国人ははっきりと区別されており、列車のチケット、観光名所の入場料などにはすべて外国人向けの高い価格と中国人向けの安い価格、時には2倍以上の差がある二つの価格が存在し、外国人が宿泊できるホテルも限られていました。外国人向けの場所では基本的に兌換券しか使用することはできません。価格が違うということは設備やサービスも異なるため、中国人にとっては兌換券をもち、そうした場所に出入りすることは大きな憧れでした。そして当時、この兌換券でしか購入できないものがありました。洋酒や高級たばこ、テレビや洗濯機、冷蔵庫などの家電製品、高級腕時計などは、今も存在する友誼商店と呼ばれる外国人向けの商店にしかなく、そこでは兌換券でしか買い物ができませんでした。兌換券を持つ外国人は、まさに特権階級でした。 そのため、人々はなんとか兌換券を手に入れようと必死になります。闇ルートができ、等価ではない高い値段で兌換券を入手できたり、兌換券で買うよりも高い値段で家電製品をこっそり販売したりする人が出てきます。貴重な海外出張の機会を持てた人は、親戚や友人を総動員してお金をかき集め、家電製品をまさに背負って帰国しました。90年代になると、兌換券は徐々に形骸化し、テレビや冷蔵庫を入手する人も増えてきます。 1995年、製造業が軌道に乗り物資の供給にも余裕があらわれ、外貨準備高も少しずつ増えてきたため、兌換券はようやく廃止されます。つまり中国は、95年になってようやく、お金があれば誰でも自由にテレビを購入できる時代になったのです。95年以降、テレビを始めとする家電製品は販売台数を増やしていき、2000年前後には、中国の90%以上の家庭にテレビが普及することとなりました。
2.VCDの登場
1990年代に入り、カラーテレビは沿岸部を中心に少しずつ普及していきました。そして上海や広州等南方の沿岸部にVHSデッキが登場しますが、空テープが一本100元以上と中国でも非常に高価で、広がりませんでした。100元は当時の一般的な家庭収入の1/3に相当し、18インチテレビとVHSレコーダーを購入すると総額5000元にもなります。VHSテープの国産化により価格が30元まで下がると、VHSも普及し始め、VHSレンタル屋が登場し、限られた一部の裕福な層の娯楽として定着していったようです。1995年にはガイナックス作品の『王立宇宙軍 オネアミスの翼』(1987年)の海賊版VHSが発売されていたことから、一定数は普及していたのではないかと考えられます。日本でもおなじみのレーザーディスクは、中国ではVHS以上に高額で6000元もしたため普及には至りませんでしたが、ハリウッド映画『トゥルーライズ』(1994年)、『ザ・ロック』(1996年)等何本かがLDで発売されています。
そして1993年、万燕(Wyan)という電子機器メーカーが「活動図像光盤播放機」としてVCDデッキを発売します。VCDとは、MPEG1かMPEG2で制作されたCD-ROMです。
▲世界で初めてのVCD機器 (参考記事:https://m.zol.com.cn/miparticle/5206782.html)
アメリカに留学していた中国人研究者、姜万勐、孫燕生の両氏が1992年にアメリカで発表されたMPEG形式の映像を収めたCDを再生する機器から着想を得たといわれています。両氏は安徽に会社を作り、巨額の投資を行って中国市場にVCDを流行らせようとしました。93年に1000台を発売しますが、これらは国内メーカーの買い占めにより即完売。買い占めたメーカーはデッキを分解して構造を研究,そもそも単純な構造の機械だったので、多くのメーカーが模倣してVCDデッキを製造、より安い値段で販売をはじめました。万燕はVCDデッキを開発したにもかかわらず、投資額が大きかったがために販売価格を高くせざるを得ず、さらに特許の申請もしていなかったため、すぐに埋没していきました。今ではその名を知る人も多くありません。当時の中国人の知的財産に対する知識の無さ、市場経済に不慣れな様子がよくわかる出来事です。この事例は、中国は模倣ばかりでイノベーションは起きないと言われていた2010年頃までは中国でもイノベーションはできるという事例として評価され、それ以降は市場経済に対する知識と経験のなさを反省する事例として取り上げられています。
VHSやレーザーディスクは庶民には価格が高く、日本をはじめとする先進国はDVDの開発が視野に入っていたためVCDには手を出さず、結果としてVCDはアジア諸国を中心に爆発的に広まりました。しかしそれだけが理由ではありません。VCDがここまで広がったのは、万燕がVCDデッキを販売するにあたり、11の映像出版社から版権を購入し、97種類のカラオケのVCDを同時に販売したからです。VCDは、カラオケができて映画も見れる電化製品として大ヒットしました。
1995年に60万台だった販売数は96年には600万台、97年には1000万台を超えました。その裏には膨大な量の海賊版VCDがあります。万燕のデッキをいち早く分解し、真似して組み立てた機器の販売をはじめたのは広東省の人たちだったといわれています。海賊版VCDも香港経由のものが多かったのでしょう。そのためか、まだあまり海外作品やホラー映画の上映が多くなかった中国で、ジャッキー・チェンやチャウ・シンチーを始め、キョンシー映画や、アーノルド・シュワルツェネッガーやシルベスター・スタローンの作品にVCDで触れた人が数多くいました。 VCDは中国全土の一般家庭、それからレストランなどで、カラオケができるビデオデッキとして受け入れられ、マイクもセットで販売されていました。映画はもちろんですが、実はこのカラオケの他に、VCDを普及させたコンテンツが3つあります。アニメ、ゲーム、そしてポルノです。ポルノについては表立っては語られませんが、当時香港には海賊版AVが大量に出回っていました。それが入ってきたのだと思います。デッキの購入には父親が積極的で、夜になると暗い部屋からテレビの明かりがぼうっと漏れていて、なかをのぞくと父親が一人テレビの前に座っていたという幼少の記憶がある人は数多くいます。 次に、アニメです。テレビで放送されるよりもはるかに多くのアニメが海賊版VCDとして出現しました。TVアニメだけではなく、劇場版などもありました。VCDは容量が少ないため最大74分程度しか収まらず、映画1本につき2〜3枚は必要になります。TVアニメのVCDは1話だけを収めたものや、劇場版アニメや映画には、映画館に行ってスクリーンを撮影したものまでありました。枚数が多いので、一度に数枚をセットして順番に再生できるプレイヤーなども出現します。最も人気のあった機能は、「エラー修正」です。そもそも粗悪な海賊版を読み込むため、クリーニングキットは必須でした。ディスクを読み取るレーザーヘッドもすぐに汚れます。新しいVCDを再生するには、まずクリーニングキットなどでディスクの汚れを取らなければいけません。傷がついてないか、購入する時にしっかり確かめることも必要です。筆者の経験からいうと、食器用洗剤でディスクをなで洗いするのが一番効果的でした。それでも読み込めなかったり、途中で詰まることがあります。「エラー修正機能」がついているデッキは詰まることが少なく、必須の機能となりました。2002年のお正月映画『ハッピー・フューネラル』では、お正月映画の顔、国民的人気俳優、葛優が皮肉交じりにこんなセリフを言っています。「スーパーエラー修正とはつまりスーパー海賊版だ。正規版は修正なんか必要ない」。
数少ない正規版VCDは、日本で一般的に使われるプラスチックのケースに入れられて書店で数十元から100元と高い値段で売られていましたが、海賊版VCDは薄いビニールの袋に滲んだ印刷のカバーとともに入っていて、路地裏の小さな店で1枚10元前後で売られていました。レコードを1枚1枚めくってほしいものを探すように、VCDを1枚1枚めくってほしいタイトルを探していると、指先が黒く汚れます。カバーのコピーだけがファイルに収められ、ファイルをめくってほしいものを探し、店員に伝えてVCDを出してもらう形式の店もありました。しかし1枚10元と言ってもそうたくさん買えるわけもなく、レンタルVCD屋もあちこちにありました。 もう一つ、VCDの爆発的な普及の後押しとなったのが、ゲームです。VCDデッキの競争が激化し、エラー修正機能など各メーカーがしのぎを削るなか、高性能をうたうデッキが出現します。98年に裕興というメーカーが、「パソコンVCD」なるものを発売しました。このVCDデッキには通常のリモコンのほかにキーボード、マウス、ゲーム用コントローラー二つ、より高価なラインにはフロッピーディスク・ドライブがついたものまであり、「勉強、インターネットにゲーム」という触れ込みで学習用として販売されました。
▲裕興「電脳VCD」351D型(『裕兴电脑VCD : 游戏机在中国走过的另一条路』より)
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
1990年初頭における日本マンガブームとその立役者|古市雅子・峰岸宏行
2020-12-09 07:00
北京大学助教授の古市雅子さん、中国でゲーム・アニメ関連のコンテンツビジネスに10年以上携わる峰岸宏行さんのコンビによる連載「中国オタク文化史研究」の第3回。冷戦体制が終焉した1990年代初頭、台湾を経由して中国本土でも日本マンガの海賊版ブームが巻き起こります。とりわけ海南美術撮影出版社が刊行した『女神的聖闘士(聖闘士星矢)』は中国オタク文化の火付け役となり、さらに日本の各マンガ雑誌からのコピーに加えて国内作家の作品を掲載した「画書大王」の創刊で、中国オリジナルのマンガ史が切り拓かれていきます。
古市雅子・峰岸宏行 中国オタク文化史研究第3回 1990年初頭における日本マンガブームとその立役者
今回は、コミック出版のさきがけとなり、中国全土に大きな影響を与えた「海南美術出版社」や漫画連載誌「画王」等を取り上げて、テレビと同時に中国の青少年に与えた漫画による日本コンテンツの影響をお伝えしたいと思います。
1.台湾から波及した日本マンガの海賊版ブームの勃興
改革開放によって民間や個人でビジネスをし、稼ぐことができるようになり、少しずつ財を築く人が出てきた1990年代初頭。WTOへの加盟は2001年まで待たねばならず、新しい時代のビジネスルールを模索しながら経済発展に向かっていた中国に、アニメに牽引された日本マンガのブームが訪れます。『鉄腕アトム』や『トランスフォーマー』の爆発的な人気を受け、中国の子供たちはより多くのマンガやアニメに触れたくなっており、それに応えるようにマンガが出版されていきます。1993年前後にはのべ1億冊以上の日本のマンガが中国で出版されていたとの考察もあるほど、まさに子供向けの出版市場を席巻していました。[1] しかし市場経済における著作権に対する理解はまったくと言っていいほどなく、連絡方法や言語の違いなど様々な壁があり、海外の出版社と連絡を取ることもなかなかできなかったため、出版されたマンガの多くは版権を取得していない、いわゆる海賊版でした。そのため、それぞれ出版に至るルートをたどることはかなりの困難を伴います。ネットの情報を調べ、実際に携わった人、当時消費者であった人達に対して取材を行い、当時の法律や政策等を見ていくと、そこにはテレビ業界の改革、海外コンテンツ輸入、海外アニメググッズ販売店の出現、国営出版社の新興と衰退など、複雑な背景がありました。そしてその根底には、70年代に台湾で巻き起こった日本マンガの一大ブームがあることがわかりました。
台湾では1966年、蒋介石政権がマンガに対する検閲を始め、それまで順調に成長していた台湾漫画産業は大きな打撃を受けます。当時の台湾では、政治に対する風刺画と、戦前の日本マンガの影響を受けた3段組のコマ割で子供向けの「連環図画」の大きく二つのジャンルがありましたが、そのうち、子供向けのマンガに対して厳しい出版規制の措置が取られ、台湾における創作漫画市場にとっては壊滅的な打撃となりました。[2] 70年代の台湾では台湾の作家によるオリジナル漫画がほぼ姿を消すこととなり、それを見た国立編訳館[3]は、それまで禁止していた日本マンガの翻訳、出版を許可します。実際にはほとんどが版権を取得していない状態での出版でしたが、オリジナルマンガの消えた台湾のマンガ市場を、日本のマンガがまさに占拠することになりました。日本のマンガばかりが溢れかえった結果、80年代に入ると、これは日本の「文化侵略」であると排斥運動が起こり、オリジナルマンガも徐々に復興。92年には新しい著作権法が施行されて、台湾のマンガ市場は徐々に正常化していきます。
こうして、台湾のマンガ検閲によって突如起こった日本マンガブームにより、中国に翻訳された日本マンガが大量に出現し、大陸でのマンガブームにおいて大きな供給源として影響を与えていきます。
海賊版マンガの製造販売卸元は、台湾や香港にほど近い広州や福建などの南方に数多くありました。1979年に深セン、珠海、汕頭、廈門が、1988年には海南省が経済特区として開放され、台湾や香港企業が大挙して進出し、徐々に海外との往来が増えるにつれ、非正規である海賊版のマンガも出版点数が増えていきました。
当時、中国の法律では香港や台湾を含む本土以外の企業が出版業務に直接関わることはできなかったのですが、マンガのソースを横流しすることは可能です。実際、1988年に設立された「海南美術撮影出版社」は経済特区である海南島に本社をおき、その翻訳は台湾版に酷似していました。そして同社の刊行物に対しては、日本のマンガ、アニメのコアなファン、「オタク」として育っていく層の多くが、以後特別な思いを持つようになります。
2.海南美術撮影出版社版『聖闘士星矢』が引き起こしたオタク文化の爆発
1988年に『トランスフォーマー』が上海テレビで放映されると、一大ブームが巻き起こり、関連商品や絵本等がものすごい勢いで売れたことは、前回ご紹介した通りです。これを見て、目ざとい人たちがアニメの経済効果に目を付けます。そして1989年、『聖闘士星矢』が沈陽電視台と広州電視台共同で放送されると、1990年12月[4]、「待ってました」とばかりに海南美術撮影出版社は、簡体字に翻訳されたマンガ『女神的聖闘士』を発売しました。この『女神的聖闘士』で、日本マンガブームに火がつきました。海南版[5]『聖闘士星矢』は、それまでの『鉄腕アトム』のように単行本を無理やり連環画サイズに切ったものではなく、サイズはほぼ単行本と同じもので、1冊を3~4冊に分冊し、1冊1.95元で全9巻45冊を出版しました。当時の1.95元は、今の人民元の価値に換算すると10元前後、日本円で約150円ほどの感覚でしょうか。
もちろん、『聖闘士星矢』の正規版は、この時点では中国にありませんでした。『女神的聖闘士』はすでに絶版となっていますが、比較的長い時間、全国で安定して販売されていたこともあり、今でも90年代のマンガブームを象徴する存在として愛され続けています。当時、子供たちが購入することのできた漫画の多くは海南美術撮影出版社が販売しており、その印刷や翻訳の質の高さは今でも正規出版だと一部で誤認されているほどです。中国版Wikipediaである「百度百科」において、企業のページは普通、オフィシャルHPや証券会社の会社紹介をそのまま貼り付け、写真はあっても会社のロゴや本社の写真を使用する味気ないものがほとんどであるなか、すでに存在しない海南美術撮影出版社のページでは写真に『女神的聖闘士』が使用され、ファンが書いたと思われる思いのこもった会社紹介が書かれた異質なものとなっています。 では、この海南美術撮影出版社とはどのような会社だったのでしょうか。それには当時の国有企業改革から紐解かねばなりません。
【12/15(火)まで】オンライン講義全4回つき先行販売中!三宅陽一郎『人工知能が「生命」になるとき』ゲームAI開発の第一人者である三宅陽一郎さんが、東西の哲学や国内外のエンターテインメントからの触発をもとに、これからの人工知能開発を導く独自のビジョンを、さまざまな切り口から展望する1冊。詳細はこちらから。
-
テレビの発展と『変形金剛(トランスフォーマー)』論争|古市雅子・峰岸宏行
2020-11-10 07:00
北京大学助教授の古市雅子さん、中国でゲーム・アニメ関連のコンテンツビジネスに10年以上携わる峰岸宏行さんのコンビによる連載「中国オタク文化史研究」の第2回。1980年に中国初のテレビアニメとして『鉄臂阿童木(鉄腕アトム)』が放送されて以降、中央政府の施策によるテレビ局の増加によって、多くの日本のテレビアニメが堰を切ったように一気に上陸していきます。とりわけ、日米資本が合同した玩具展開とタイアップした1985年の『変形金剛(トランスフォーマー)』の大ブームは、都市部の消費文化に大きなインパクトを与え、中国社会で論争を引き起こしていくことになります。
古市雅子・峰岸宏行 中国オタク文化史研究第2回 テレビの発展と『変形金剛(トランスフォーマー)』論争
中国で最初のテレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』が放送されてから、さまざまなかたちで、日本のアニメが中国で放映されるようになります。そこにはテレビ局の増加とそれに伴うテレビ番組の需要の増加がありました。各省だけではなく、その下の行政単位である県や、直轄市でもテレビ局が設立され、毎日途切れず放送を続けるために手探りで努力を続けるテレビ局において、日本のアニメは重要なコンテンツの一つとなりました。テレビの発展とともに消費経済の洗礼を受けた当時の様子を振り返ります。
1.地方テレビ局の増加と『一休さん』(1975年)による波状放送の始まり
『鉄腕アトム』がCCTVで放送されると、続いて『ジャングル大帝』が『森林大帝』という名前で放送され、すぐにマンガも出版されました。しかしこうした規格外のビジネスモデルは続かなかったのか、CCTVが直接放映権を入手し放映する流れは途絶えてしまいます。代わりに出てくるのが地方局です。
1983年、政府は『四級辦台(テレビ局四級構造)』という新しい政策を打ち出しました。四級とは中央テレビを第一級、各省や北京、上海など国の直轄市のテレビ局を第二級、各省の直轄市を第三級、その下の県を第四級と分け、各地の条件に合わせてテレビ局の設置を許可したのです。それまでは中央、省レベルでしかテレビ局を設立できなかったためごく少ないテレビ局で全国をカバーしていましたが、1983年に北京で開かれた第11回全国広播電視工作会議(ラジオテレビ業務会議)で、中央と各省単位でしか設立できなかったテレビ局が地方直轄市、省の下の県でも設立できるようになり、中国のテレビ局数は一気に増加、そして番組制作も許可されることになりました。
しかしまだCCTVでさえ手探りで運営していた時代です。新設されたテレビ局には番組を制作する設備もノウハウもありません。また初期資金も少なく人材もいなかったので、海外からの番組を買い付けることも、海外番組の字幕を制作したり、吹き替えしたりすることも困難でした。当時はCCTVから配信されたニュースしか放送するものがないという状態の局も多かったようです。 そこでこれらの地方テレビ局は、設立が比較的早かった他局に、すぐに放送できる番組がないか聞いて回ることになります。しかしそれでも番組は足りません。
当時、香港と国境を接し、同じ広東語文化圏である広東省の広東電視台が香港のテレビ局から番組を買い付ける計画を密かに進めていました。1979年に許可が出ると、CCTVと広東電視台は共同で、10本の香港ドラマと1本のアメリカドラマを輸入、まずはCCTV主導で翻訳吹き替えしました。このアメリカドラマは1980年1月に放映開始した『大西洋底来的人(大西洋から来た男:Man from Atlantis;米1977年)』です。ドラマ『大西洋』は大ヒットします。そして翌年、『鉄腕アトム』がCCTVにて放映され大ブームを起こしたのを受け、1983年、新しく香港から日本の大人気アニメを買い付けますが、どうも翻訳がうまくいきません。なんとか2話制作したもののあとが続かない。どこか他の局でやってくれないだろうか。
そんな時、唯一名乗りを挙げたのが、当時、遼寧省広播電視庁副庁長だった晋稻光です。 「我々の省には児童劇団がある、そこでやってみてはどうか。」 なんとか話をまとめると、晋稻光は手に入れたアニメを担いで遼寧に戻り、遼寧児童芸術劇院(以下、遼芸)[※]に持ち込みました。
[※]ここでいう児童劇団は子供の役者が所属する児童劇団ではなく、大人が子供のための劇を演じる劇団のこと。
遼寧電視台は晋稻光に指示されて持ち帰ったフィルムを翻訳吹き替えするために同局スタッフ、張井方を監督に据え、遼芸で声優オーディションを行いました。張監督はオーディションとは一切通達せず、ただ詩と新聞速報の朗読録音テープを役者に提出させ、本当に技術とやる気のある役者を揃えて、遼寧テレビのスタジオで収録を行いました。そして1983年、スタッフの必死の努力の末、吹き替え版が完成します。それが中国で最も知られている日本アニメの一つ、『一休さん(聪明的一休)』(1975年)です。
▲中国で販売されていた一休さんの漫画(1984年)
『一休さん』は日本のお坊さんの話であるため、仏教に関する内容、唯心論に依拠する内容が含まれており、中国での放送にふさわしくない──これが広東テレビが制作を続けられなかった理由でした。日本のお寺での生活や習慣など、香港で翻訳、放送されたものを買い付けても、理解できない部分も多かったのでしょう。しかし、遼寧省はかつて満州国の一部だったところです。幸か不幸か、日本語で教育を受け、日本人の習慣や考え方などに精通した人材が中国で最も多い場所の一つでもあります。遼寧大学日本語学科の教授が翻訳を担当し、チーム一丸となって背景資料に至るまで詳細に調べ上げ、このアニメが中国の子供にいい影響を与える作品であることを確信し、仏教色を減らし、かつ不自然な吹き替えにならないよう一字一句考え抜いて翻訳、吹き替えを行ったのです。
かくして放映された遼寧版『一休さん』は完成度が高く、視聴者からもとても高い評価を得ました。実は遼寧児童芸術劇院は吹き替えの経験などなく、スタジオもなかったのですが、中国人が受け入れやすいように細部まで考え抜かれた翻訳に、海外アニメの吹き替えとして始めて児童劇団の役者を使ったことによって、より質の高い物が出来たこと、そして国内において海外アニメどころかアニメを放送する局がCCTV以外ほとんどなかったことから、これを機に遼寧テレビは一躍、人気テレビ局となります。
アニメの翻訳吹き替えを得意とする遼寧電視台と遼寧遼芸の登場は中国のテレビアニメ放送に大きな一石を投じました。地方局に日本アニメをはじめとする海外番組を翻訳アフレコできる団体が出現したことは大きな出来事です。そして最も重要なのは、「香港等から番組を安く買い付け」、「国内で翻訳吹き替えし」、「自局で放送」、「他地方局で再放送」という、海外ドラマの放送で確立されたビジネスモデルが、『一休さん』を皮切りにアニメでも成立するようになったことです。『一休さん』以降の日本アニメの普及は、全てこの「地方局での再放送」が鍵を握ることとなります。この現象を中国テレビ局の番組「波状放送」と名づけます。つまり、ある地方局が買い付け、吹替版を制作し放送されたアニメシリーズが、波が広がるようにその他の地方局で次々に再放送され、全国に広がっていくのです。
この時期に中国で放送された日本アニメにはほとんど修正は加えられず、そのままの状態で放送されました。朝から晩まで途切れず番組を放送するだけで精一杯だった時代です。厳しい検閲を加える余裕はまったくありませんでした。 この時期、国内で放送されたアニメは中国で吹替版を制作したものだけではなかったようです。1984年に放送された『花の子ルンルン(花仙子)』(1979年)は台湾訛りの中国語だったと当時を記憶している人から聞きました。中国と台湾との関係はまだ緊張が続いていた時代です。台湾で翻訳吹き替えしたアニメが香港に売られ、そこからまた中国に転売されたのかもしれません。もちろん、こうした放映権の二次販売、三次販売時に著作権料が日本に払われたかは定かではありません。改革開放によって、文革の鎖国状態から突然海外の市場経済に接することとなった中国では、そうした行為が許されないことだという認識もなく、また、そもそも正規に放映権を購入する力もないというのが実情でした。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
【新連載】中国オタク文化史研究 「アトム旋風」と改革開放の時代|古市雅子・峰岸宏行
2020-10-01 07:00
今月から、北京大学助教授の古市雅子さん、中国でゲーム・アニメ関連のコンテンツビジネスに10年以上携わる峰岸宏行さんのコンビによる新連載「中国オタク文化史研究」がスタートします。現在の中国では、日本産のコンテンツに影響を受けたアニメ、コミック、ゲーム等のオタク文化が「ACG」ないし「動漫」と総称され隆盛を遂げていますが、その発展を社会・文化的な背景とともに探っていく、本邦初の通史的試みです。初回は、1980年代、鄧小平の改革開放の時代に上陸したTVアニメ『鉄腕アトム』がもたらしたショックを紐解いていきます。
古市雅子・峰岸宏行 中国オタク文化史研究第1回 「アトム旋風」と改革開放の時代
1. はじめに
ACGという言葉をご存知でしょうか? Anime、Comic、Gameという言葉の頭文字をつなげたもので、アニメ、漫画、ゲーム等のコンテンツを指す総称です。中国では、最初は日本のアニメ、マンガ、ゲーム等のコンテンツを指す言葉として普及し、2020年現在は、日本コンテンツに近い絵柄、ストーリー、キャラクター性、設定の中国原作作品も含めた、オタク文化全般を指す言葉となりました。 他にも、動漫という言葉もよく使われます。これは動画、漫画の頭文字をつなげたもので、狭義ではアニメと漫画、広義ではゲームや二次創作作品等も含めたコンテンツ文化全般を指す言葉です。 中国の日本コンテンツ受容の歴史は、日本では「海賊版」という言葉に覆われて今日まで蔑ろにされてきました。2008年の北京オリンピック開催前後あたりから中国の海賊版VCD、DVD、ネットサイト等が日本で話題にのぼるようになりましたが、ではなぜ、反日教育を受けているはずの中国で「海賊版」である日本コンテンツ、価値観が違うはずの日本アニメやドラマ、漫画がこれほど大量に消費されてきたのでしょうか。 この連載では、北京大学副教授の古市雅子と10年間中国のゲーム・アニメ業界で仕事をしてきた峰岸宏行が協力し、日本のコンテンツ、つまり日本のACG/動漫が中国人にどのように受け入れられていったのか、そして中国社会にどのような影響を与えたか、という受容の歴史やその文化的背景等について、明らかにしていきたいと思います。 もちろん、中国のコンテンツ文化は日本からの影響以前に、「中国アニメの祖」と呼ばれる萬氏兄弟が制作した最初の作品『大鬧画室』(1926年)を皮切りに、日本でも上映されたアジア初の長編アニメーション映画である『鉄扇公主』(1941年)など、戦前からの脈々とした歴史がありますが(この時代については、今後の連載で改めて振り返っていく予定です)、戦後の政治的動乱によって、長らく冬の時代を余儀なくされていました。 ですので、まずはようやく改革開放が始まる1980年代からの時代に焦点を当て、日本の読者になじみの深いアニメや漫画、その他の付随するコンテンツについて具体的な作品を入り口に、様々なプラットフォームの発展や政策の変遷を絡めながら、紹介していきましょう。
2. 改革開放の大号令とともに
1976年、10年続いた文化大革命が毛沢東の死によりようやく終わりを迎え、中国は鄧小平の号令のもと、経済発展を最重要課題とする改革開放の時代に突入します。「窓を開けたら、ハエや蚊が入ってくるかもしれない。でもその後には新鮮な空気が入ってくる」。それまで他国との交流をほぼ断っていた中国はその門戸を開放し、階級闘争によって断絶された10年を取り戻そうと、「豊かになれる人から先に豊かになろう」という号令がかけられました。 鄧小平は、指導者として復帰した翌年、1978年に中国の国家指導者として初めて日本を訪問し、記者会見の席上でこう言いました。「科学技術や企業経営の面においては、我々は先進国、特に日本に学ばなくてはならない」。経済発展のモデルとして日本に学ぼうという、「日本ブーム」の始まりです。
鄧小平が「日本に学ぼう」といった理由は3つあります。市場経済体制でありながら経済計画を策定、実施していたこと、戦前の対外的に封鎖された経済体制から戦後、対外開放型経済へと移行していること、経済が立ち遅れた状態から短期間で先進国に追いついた東洋の国家であること。その全てが、中国の状況と重なっていたため、いわば政府の主導による「日本ブーム」が起こったのです。 鄧小平は記者団を引き連れて訪日し、新日鉄や日産、パナソニックなどの施設を訪れ、その様子を国内に報道させました。鄧小平の姿越しに写る日本を目にした人々は、その豊かな様子に驚き目を見張りました。鄧小平が訪日した翌月、早速日本を視察に訪れた中央弁公庁副主任、政府系シンクタンク中国社会科学院の副院長、鄧力群率いる視察団が、『访日归来的思索』という報告書を出しています。「一般的な労働者の家庭でも、40-50平米の家に住んでいる。全国平均で2世帯に一台自家用車を持ち、95%以上の世帯にテレビ、冷蔵庫、洗濯機、レコード、掃除機、炊飯器などの耐用性消耗品がある」、「農民も含めて、みなウールの服を着ている。ファッションは様々で、月曜日に街に出てみると、町中で見かけた女性の中で同じ服を着ている人はいない。案内してくれる女性スタッフも毎日違う服を着ている」、「東京の百貨店はおよそ50数万種の商品を扱っている。我々の王府井百貨公司は2万2千種である」[1]。全国民がみな同じグレーか紺の人民服を着て、仕事も学校も二の次で階級闘争に明け暮れていた中国の人々にとって、敗戦国であるはずの日本人が色とりどりの服を着て、白物家電に囲まれ、自家用車に乗る豊かな生活を送っていることはよほどのショックだったに違いありません。 鄧小平訪日のニュースで、特に強烈な印象を与えたのは新幹線です。東海道新幹線に乗った鄧小平が、「とても早い。追いかけられて走っているようだ。今の我々にふさわしい」と言ったのは有名な話ですが、車窓から伝わる速度、清潔な車内、そしてこの名言と共に、新幹線は日本、そして最先端の科学技術の象徴となりました。その後、中国では高層ビルの名前や、学習雑誌の名前など、いたるところに「新幹線」という言葉が使われ、日本を表す象徴として、富士山、桜、芸者とともに新幹線が使用されました。
こうしたいわば「日本ショック」ともいうべき衝撃を与えた鄧小平の訪日ですが、中国ではまだ一般家庭にテレビがない時代でした。そのような状況のなか、市井の人々にまで熱狂を巻き起こし、「日本ブーム」を決定づけたのは、1979年に輸入、公開された高倉健主演の映画、『君よ憤怒の河を渉れ』でした。 日本国内ではそこまで目立つことのなかった作品ですが、文革の10年間、限られた社会主義国の映画しか公開されてこなかった中国で、この映画は公開とともに一大ブームを巻き起こしました。殺人、強姦犯に仕立て上げられた検察官の高倉健が、迫る警察から逃れつつ寡黙に自ら行動して真犯人を見つけ出すサスペンスです。中国の人々はまずスクリーンに写る東京の高層ビル、最先端のファッション、電子音楽のBGM、主人公を救うため新宿のアスファルトを馬で駆け抜ける中野良子の派手なアクションに熱狂しました。高倉健が着用したトレンチコートとサングラスが大流行し、女性は中野良子のような帽子やブラウスを手に入れるために必死になったのです。「ラヤラ」のスキャットで歌われる主題歌が大ヒットし、みな高倉健になりきって、真犯人を追い詰める主人公の台詞を模倣し、映画を題材にした漫才まで人気を博しました。 中国の人々の心を掴んだのは表面的な豊かさだけではありません。無実の罪を着せられ、迫りくる追手や待ち受ける罠に寡黙に耐えながら、最後には自らの手で真犯人を追い詰め、自由を手に入れる高倉健の姿は人々に衝撃を与え、文革で抑圧されていた10億人の鬱憤や憤懣、豊かさへの渇望が、この作品によって開放されたのです。かくして、高倉健は「男子漢」(男のなかの男)の象徴となり、時代のアイコンとなりました。
「高倉健は私のアイドルだ。当時、日本映画『君よ憤怒の河を渉れ』が中国で公開されると、街の隅々に至るまで『高倉健を求めよ、本当の男を求めよ』というブームが巻き起こった。この映画を見なければ、他人と話ができないようなものだった。彼は私に映画の役と同じように、全く新しいイメージをもたらした。それまで流行っていた『やさ男』や『なよなよした二枚目』とは対象的に、冷厳、隠忍、責任感などのキーワードで人々の心を揺さぶった」[2]
このような時代に、『鉄腕アトム』は中国初のTVアニメとして放映されます。 まだ放送開始まもない中国の国営放送、中央電視台(CCTV)にて、『鉄腕アトム』第一作である1963年のモノクロ作品が放送されると、全国の子供たちの間で一大ブームとなったのです。
3. 『鉄腕アトム』中国へ
1980年12月、『鉄臂阿童木』(鉄腕アトム)がSEIKOの腕時計CMと共に中国のCCTVに翻訳吹き替えで登場しました。1963年に日本初のテレビアニメとして放送された「鉄腕アトム」は、漫画『アトム大使』の中で「宇宙人」と「地球人」との間を取り持った平和の使者だったように、「初のテレビアニメ」、「初のCM付テレビアニメ」として中国で放送され、アトムにとっては41ヶ国目の「海外奉仕」となりました。 アトムの父、手塚治虫は鉄腕アトムが中国で放送されて間もない1980年12月26日に朝日新聞夕刊で掲載された記事「鉄腕アトム中国へ飛ぶ」で以下のように記しています。
「中国にアトムを輸出しようという計画を立てたのはアニメ製作などで協力していた三京企画の木村一郎で、たまたま中国系の代理店で『向陽社』という美術関係の紹介をしている会社が映像分野を扱いたいという意向と企画がドッキングした。」
向陽社の社員が書いた本によると、1979年、鄧小平訪日の翌月、まさに先ほど引用した報告書を書いた訪日視察団の一員として来日したCCTVの副局長、阮若琳が、門戸を開いた中国とのビジネスチャンスを模索していた向陽社の社長、華僑の韓慶愈と会ったなかで、企業が番組の放映権を買い、それをCCTVに贈与する代わりにCMを無償で放送するというビジネスモデルが提案されたといいます。この方法なら、まだ海外の作品を購入する力などまったくないCCTVであっても、レベルの高い日本の番組を放送することができます。こうして三京企画と向陽社の協力により放送が決まりましたが、海外の子供向けアニメを中国で初めて放送するのです。台本の翻訳、吹き替えと全て手探りで進めていくしかありません。経験者がほとんどいない吹き替えという仕事は、最終的に北京広播学院アナウンサー学部1977年度入学の学生が、卒業実習として担当することになりました。しかしそれでも人手が足りず、お茶の水博士の役で参加したのは1977年度生のクラス担任でした。ところが主人公のアトムは、どんなに試しても相応しい声が見つからず、最後の手段として、アトムの担当ディレクター、児童芸術劇院出身の李真恵自身が念のため試したところ最も相応しいということになり、ディレクターが演じることになりました。こうして、「具有十万馬力、七大神力的少年機器人」(十万馬力と七つの超能力を有したロボット少年)というキャッチフレーズで「アトム」はなんとか、中国でのテレビ放映にこぎつけたのです。 この経緯は、後に日本の関係者から、「日本のアニメが安価で海外放映権を販売される前例となり、その後長く相応しい価格で販売することができなかった」と批判されることとなりましたが、当時の中国には日本のテレビ番組放映権を取得できる力などなく、新しい時代を迎えた中国で、初のTVアニメシリーズとして日本のアニメが放映されたことが当時の中国人民、そして日中関係に与えた影響は計り知れません。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
<前へ
2 / 2