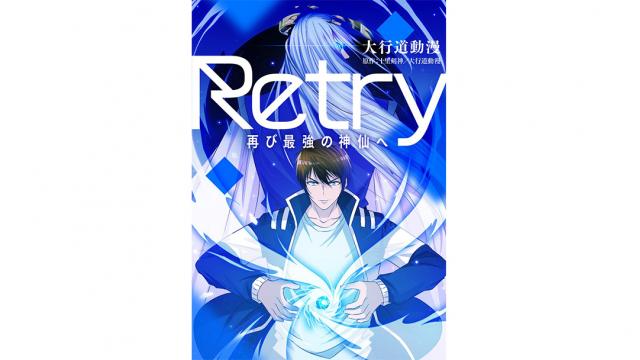-
中心をもたない、現象としてのゲームについて 付記:全体の要約と質問に対する答え|井上明人
2024-11-13 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。今回は最終回として、連載の各章を振り返りながら、その背景を深堀りしていきます。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて本連載はおよそ10年近く続けられ、また論点が多岐にわたっている。また後半にいくにつれ、筆者自身がかなり悩みながら書いた箇所も増えていくため、全体像が掴みづらいものになっていた。改めて、全体としてどのような議論構成となっていたのかを、なるべく手短にまとめると同時に、わかりにくかったであろう箇所についての補足として最後によくある質問に対する答えを付記して終わることとしたい。
第一章 「ゲーム」をめぐるいくつかの不連続な問
まず、ゲームについて考えるということが我々が世界をどのように理解するのか?ということと深く関わっているということを確認することからこの連載ははじまっている。たとえばビデオゲームというメディアは、体験したことのない未知の問題について文章という道具立てでは困難だった「戦場の不合理」を効率的に理解させることができるかもしれない。それは感覚的な臨場感という問題だけでなく、現場で発生するトレードオフの複雑さや、「合理的な愚か者」が生じるメカニズムを理解させるためのメディアとしてもかなり優秀なメディアとしての特質を持っている。こうした特質から、ゲームは社会的な批判(批評)のツールとしても大きな注目を浴びている。
一方で、ゲームに関わる「楽しみ」のようなものを社会的活動のどこまで持ち込むのが妥当なのか、ということは古代から議論になってきた。たとえば、受験勉強や、健康維持のための運動、面倒な単純労働などを遊ぶように楽しくできるのならば、それは多くの人が歓迎することだろう。しかし、楽しい労働ならば労働者が資本家に搾取されてもいいものなのか?また、社会の様々な活動に楽しみを持ち込むといっても、戦争や政治を「楽しく」やってみせることは果たしてどこまで許されるだろうか?
こうした特性もあり、思想史的にも、自由論、幸福論、労働思想、政治哲学といった多様な文脈において、ゲームや遊びの問題はクリティカルな論点として言及されることも少なくなかった。つまり、自由や幸福、労働、政治にまつわる重要問題であるという認識は実のところ数千年来存在していたものだと言っていい。
それにもかかわらず、ゲームや遊び、それにまつわる楽しみをめぐる研究は自由や労働といった問題に比べればその議論の蓄積は(無いわけではないが)相対的に薄い。
この概念は、自由や幸福の問題と同じように、複雑で、やっかいな側面をもっている。この概念について述べてきた、ヴィトゲンシュタインや、サットン・スミスらは、遊びに関わる概念が曖昧であり、相互に矛盾した側面があることを述べている。
この重要でありながらも、厄介な概念について考えていくことが本連載全体の重要なテーマであった。ただし、本連載はゲームの定義を行うことを目的とするものではない。定義のようなものを行うことの難しさを前提とした上で、ゲームという現象の厄介で捉えがたい特性について、少しでもその複雑性の構造を説明しようする試みである、「定義」は試みていない。
▼該当回
・〈ゲーム〉をめぐるいくつかの不連続な問(井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第1回)
・理性を喚び起こすもの――複数の合理性と向き合う(井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第2回)
・ルールのないゲームたち ――ゲームにルールはどのように必要なのだろうか?―― (井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第3回)
・「ゲームとは何か」をめぐる交わらない答えたち (井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第4回)
第二章 ゲームとはどのように論じられてきたか。何が論じられるべきなのか
第二章では、議論の大きな背景を確認した上で、詳細な議論をはじめる前の重要な前提ーーすなわち、一般的な論文でいうところの方法論に相当するーー点を確認してきた。
「ゲーム」や「遊び」の概念に関する研究は、ゲームや遊びの重要な特性がなんであるかという見解に類似点や共通的がありつつも、その曖昧さや多様さも同時に強調されることが多い。また、「ゲーム」や「遊び」がなんであるかという捉え方に異なったいくつかの方向性があり、それらがくっきりと(離散的に)分かれるわけではなく、グラデーション状に繋がっているということが示されている。この曖昧性を生じさせているポイントはいくつかの点から説明することができる。
第一は、「ゲーム」がHDMIのような技術規格用語や専門用語などではなく「日常言語」であるということである。日常言語は、歴史的、地理的に概念の指示する範囲に多様性があるのはごく一般的なことである。「ゲーム」の訳語となる語彙の意味範囲は、言語圏によって少しずつ異なっている。
第二は、ゲームが「日常行為」であるということだ。「ゲーム」というのは、一見、ひとつに繋がった行為であるかのように認識されがちだが、実際にはゴールやルール、自己決定、楽しみ……など様々な関連概念が連合したものが一つのパッケージとして流通しているものである。これが一つにまとまっているような状況は、人間の認知メカニズムから、自然環境、経済、社会システムといった多様なものに影響を受けている。複数の要素がまとまったときに、新たな性質を獲得することを「創発性がある」と言うが、ゲームという現象の成立はどうやら創発性があると見てよい。
日常言語であり、創発性のある日常行為でもあるものの特性を考えていくには、ゲームに関わる複数の要素間がどのようにネットワークを結んでいるのか、というその関係を見ていくことが順当なアプローチになるだろうということを確認した。そして、三章以後では、複数の概念や事象間の関係について詳細な検討を行っていく。
▼該当回
・議論手続きとリサーチクエスチョン (井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第5回)【不定期配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第6回 日常行為としての「ゲーム」を考えるということ【不定期配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第7回 概念の中心性――分けることとつなぐこと【不定期配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第8回 ゲームとは楽しいものでなければならないのだろうか?【不定期配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第9回 どこまでが「ゲーム」なのか?【不定期配信】
第三章 学習説のネットワーク−−積極的学習行為としてのゲーム−−
各要素間の関係を検討するにあたって、まずゲームの概念の特にコアな要素と思われるものから順に考えていくため、ゲームを積極的な学習のプロセスとして見なす立場を丁寧に取り上げて論じていく。このような立場は、フロー体験やラフコスターの議論に象徴されるが、このゲームを積極的な学習のプロセスとみなす立場を「学習説」と名付け、この説明の強力さを確認するのが三章全体の要点だった。ゲームを説明する説明は、さまざまなものがあるがこの立場からの説明は、近代以後のゲームの概念において、重要なものであり続けてきた。
なぜ、この立場からの説明が説得力を持つのか。端的に言えば、それは、ルール、駆け引き、非日常、楽しみなど、ゲームについての重要な様々な側面のほとんどに大きく関わってくる概念であるからだ。
ゲームを遊ぶ人々に特有の非日常的な環境(二次的現実)の成立は、ゲームを遊ぶ人々特有の世界の捉え方(二次的フレーム)を立ち上がらせる。非日常的な環境だけでなく、ルールやゴール、駆け引きやトレードオフのような要素を多く兼ね備えた行為の環境は、そのような独特の世界の捉え方を立ち上がらせる環境として効率的に機能するという特性をもっている。
これらのプロセス全体においては、様々な事象が同時並行的に巻き起こっている。ただ、これらのプロセスの大半は大まかに言ってしまえば、ヒトが環境へ適応する過程で生じている認知のクセのようなものに根ざしたものだと言うこともできる。人間の適応や学習のプロセスは、ゲームに関わる多彩な側面に、かなり一貫した説明を与えうる可能性がある。
第三章では、その一貫した特性を、複数の事象の成り立ちのネットワークを媒介するハブ的な特質として整理してきた。学習説は、ゲームに関わる主要な事象や概念の関係性に一応の説明を与えることができてしまう。それゆえ、三章までで、読むのに力尽きた読者は、学習説がゲームのほとんどを説明できてしまうかのような話だと思っただろう。
▼該当回
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第10回 学習説の世界――積極的学習行為としてのゲーム――【不定期配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第13回 プレイヤーのいないゲームは存在しうるか?【不定期配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第16回「非日常」をめぐる四つの中間の概念をつくる【不定期配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第17回 二次的フレームの形成【毎月第2木曜配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第18回 物語からゲームへ【毎月第2木曜配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第20回 ゲームから物語へ(1)【毎月第2木曜配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第21回:ゲームから物語へ(2)【毎月第2木曜配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第23回 駆け引き(学習説の他説との整合性④)【毎月第2木曜配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第24回 駆け引き(学習説の他説との整合性④-2)【毎月第2木曜配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第25回 ゲームは依存の仕組みなのだろうか?(学習説の他説との整合性⑤)【毎月第2木曜配信】
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第26回 ゲームにとって快楽とは何か――「快楽」説の検討(学習説の他説との整合性⑥)
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第27回 メタファーとしてのゲームーー「快楽」説の検討(2)(学習説の他説との整合性⑥)
・井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第28回 学習説はどこまで説明ができたのか
-
中心をもたない、現象としてのゲームについて 第41回 第5章-7ハブとしての循環概念を評価する|井上明人
2024-08-28 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。
「遊び-ゲーム」の分節を説明できる理論はいかにして可能なのか。「インタラクション」「学習」「循環」といった概念でそれを記述する困難を確認しつつ、改めて「遊び-ゲーム」を分節化すること自体の意義を問い直します。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて第41回 第5章-7 ハブとしての循環概念を評価する
5.7 ハブとしての循環概念を評価する5.7.1 包含関係によるハブ概念としての循環概念
前回、「遊び-ゲーム」に関わる現象を観察する4つの観察モデルが、さまざまな遊び-ゲームを捉える説明(学習説や非日常説)の多くに適用可能なものであることを示してきた。
これは、いわば複数の要素間の循環のような現象がゲームを説明する鍵を握っているのではないかということを示すものだった。こうした複数の重要概念が、この4つの観察モデルを通して並列させてみることができるとは一体どういうことなのかを考えてみたい。
「遊び-ゲーム」にとって中心的な概念とは何か、という基本的な問いを考えたとき、その対象となる行為を幅広く説明可能なものとして、第三章では、ゲームを学習として考えるという発想を論じてきた。それと同様に、循環もまた遊び-ゲームに関わる概念を幅広く説明可能なものとなっている。学習説の概念が多様な概念と先後関係を持つというような形で機能し、複数の概念間をつなぐハブとして機能しうるからではないか、というのが現時点での見解だった。
前回までの議論から言えることとして、 ここで循環のモデルとして取り上げた概念系も、そうした性質をもっているということだ。多様な現象を記述できる媒介となりうる性質をもっている。これは遊び-ゲームについての「循環」系の概念を使った説明が、遊び-ゲームのほとんどの領域を記述可能な万能理論的な性質をもっているということを示しているといっていい。それゆえに、ガダマーも、ボイデンディクも西村清和も、多くの論者が循環的な性質の意義を強調してきたと考えてもいいだろう。
では、循環のモデルはハブ概念として、学習説と比較して、どのように評価できるだろうか? 循環的な側面を強調することは、学習説とは異なっている側面がある。
第一に、循環のモデルを用いて遊び-ゲームに関わる諸概念を記述することはできる。しかし、「記述できる」ということは、因果関係や相関関係、先後関係といった仕方で諸概念と関係しているといったことではない。
さまざまな概念を「記述できる」ということは、遊び-ゲームに関わる様々な概念が循環に関わる属性を共通して備えているということである。
言い換えれば、それは遊び-ゲームに関わる様々な概念が、循環に関わる概念の(1)部分集合であるか、(2)もしくは積集合(共通部分)としての性質を持っているということだと考えられる。可塑的な複層構造をもったものは様々なものがあるが遊び-ゲームはその一例となりうるし、循環参照的な推移をするものも様々なものがありうるが遊び-ゲームはその一例となりうる。
すなわち、何らかの包含関係という形で循環に関わる概念は遊び-ゲームの諸概念のハブとなっていると考えられる。
部分集合であるか積集合であるかはさておくにせよ、遊び-ゲームの諸概念を幅広く含むかたちで、循環系の概念は位置づけることができる。学習説が現象の移行するプロセスに着目していたのとは違った関係性によって循環系の概念は概念のハブとしての性質を持っていると見做すことができる。
5.7.2 循環概念は遊び-ゲームだけを含むのか
包含関係的なハブであるということは良いとして、これが何らかの包含関係によるものなのだとすれば次に起こる問題は、これがどこまで広い現象を説明するものなのかということだ。
学習説は、「学習」と省略して呼んではいるが、実際にはフロー体験のような比較的、限定された学習のケースを想定している。では、可塑的な複層構造や循環参照的な順序といったものはどうなのか。
素朴に考えれば、可塑的な複層構造のような話は、記述可能な範囲が広すぎると言っていい。構造化が徐々に進むやや複雑なプロセスをもったような現象を含むものであれば、だいたいのものはこのモデルで記述できてしまう。生命の進化プロセスでも、法の制定過程でも、組織の秩序化が行われるプロセスでも記述できる。記述できる幅が広すぎる。
20世紀後半に多くの学問分野で、オートポイエーシスやシステム論が注目され、それらの理論は、生命システムから社会システムまでかなり広範な領域を説明してきた。こうした一般性の高い話との切り分けをしなければいけない。
説明力は高く、確かに循環のような現象は遊び-ゲームの記述において有用であるが、遊び-ゲームの領域固有の特徴を限定するための説明モデルとしては適切な粒度であるとは言い難い可能性がある。
5.7.3 適切な限定を加えることはできるか?
これは、適切な限定をすることが不可能であると言っているわけではない。
概念範囲の広さをめぐる論点は、ビデオゲーム研究に限定した話をするならば、「インタラクティビティ」概念が、ビデオゲーム特有の性質を適切に記述する概念たりうるのか? という議論でも似たような議論がなされてきた。インタラクティビティの概念と「循環」の概念が同じであるかどうかはやや注意すべき点もあるが[1]、可塑的な複層構造や、固定的な複層構造、あるいはその中間のような複層構造は、一般に「インタラクティビティ」という語彙によって想定される範囲とほとんど重なるものだろう。
「インタラクティビティ」はビデオゲームに特有の性質を持つ語彙として、しばしば注目されてきたが、「インタラクティビティ」のあるものはビデオゲーム以外にも、ゲーム以外のPCのソフトウェアや、若干の複雑な挙動をする機械の多くに当てはまる性質である。そのため「インタラクティビティ」をビデオゲーム固有の性質として見做すことはしばしば批判を受け[2]、そして、適切な範囲の限定を加えるための議論も蓄積してきた。
興味深いことに、インタラクティビティの範囲を限定する際に行われる概念化は、しばしば学習説やコミュニケーション説の要素を部分的に採用しているように解釈できるものが多い。
たとえば、オーセット(1997)は「エルゴード的(ergodic)」という概念を導入し、読者が読み通すために「小さくない努力(nontrivial effort)」を要するものだという限定を加える[3]。また、スマッツ(2009)Smuts, A. 2009. What Is Interactivity?. The Journal of Aesthetic Education, 43(4), 53–73.は、反応を返すもののうち、完全にコントロールするものではなく、完全にコントロールされるものでもなく、完全にランダムな仕方では反応しないもの[4]という限定を加える。プロのテニスプレイヤーがまともに勝負にならない程度に下手な相手とプレイするようなときは、あまりインタラクティブな状況とは言えず、何かを習得することが難しいようなときには、その何かが最もインタラクティブであるのだという[5]。こうした概念化は、遊び手による主体的な状況の関わりについての概念化であり、とりわけスマッツによる概念化はインタラクションの議論と学習説の議論を融合させた議論のように読める。
また、クロフォードによるインタラクティビティの概念化は、会話をモデルとしたものになっている。クロフォードによれば、インタラクションとは「二人の行為者が交互に聞き、考え、話す循環的プロセス」だと言う[6]。
ここまで、遊び-ゲームのハブ概念として、学習説、コミュニケーション、インタラクティビティといった概念が強力に機能しうることを述べてきたが、いずれも、インタラクティビティの概念化のために、深く関係を持ちうる学習説やコミュニケーションような概念ハブの特質を借りてくることで、概念の範囲を絞ろうとしているように思われる。
こうした概念の限定の仕方は、遊び-ゲームに関わる範囲を限定する上で、学習やコミュニケーションが強力なハブ概念として機能しうる限りにおいて、説得的な限定にはなりうるだろう。
ただし、ここで与えたい限定は、学習説やコミュニケーションのようなハブ概念に頼らないかたちでの概念の限定がありうるのか? ということである 。学習説やコミュニケーションなどを再記述するものとしての「循環」の適切な概念化のために、学習説やコミュニケーションの概念を借りてしまってはトートロジカルな説明になってしまわざるを得ないため、それらに頼ることはできない。
学習説ほとんどそのものではなくても、学習説の一部を構成する――たとえば「自発性」――のような心的態度を条件の限定に持ち込んで、「自発的に循環の中で揺蕩うこと」あるいは「循環の中で揺蕩うことを拒否しないこと」といった形で限定すれば、それなりに限定できるかもしれない。ただし、循環の観察モデルのなかに心的態度を持ち込むことを正当化できる根拠を筆者はここで持ち出すことはできない。
循環や「インタラクティビティ」といった概念を扱うことの難しさの一つは、「会話」や「学習」といったものに比べると、こうした概念が指し示す範囲についての日常的な意味の範囲というものが日本語ではあまり明確に存在しているとは言い切れないという点がある。「インタラクティビティ」などは英語圏ではかなり日常的な語彙になっているようだがそれでも1960年以後のことであり、非西洋圏では、いまだ日常的な語彙とは言えず、言語圏によっては、かなり専門的な語彙にさえ響く[7]。いわば「日常概念」であるのかどうかのボーダーライン上にあるものだと言える。
それゆえ、この概念が適切な範囲をもった日常概念たりうるかどうかは、現在の原稿執筆時の2024年時点では、議論すること自体がおそらく難しい。この概念がハブ概念として適切な範囲を持ちうるかどうかは、100年後の議論に委ねても良いかもしれない。
2024年の現時点では、「適切な概念範囲の限定を与えることが難しい概念なのではないか」ということを確認するに留めたい[8]。
-
中心をもたない、現象としてのゲームについて 第40回 第5章-5.4 遊び-ゲームにおけるルールを循環モデルとして再記述する|井上明人
2024-08-27 21:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。
ビデオゲームに内在するプログラム構造に対して、大会のレギュレーションなどの可塑的なルールといった「二層構造」の「ルール」があると言えるゲームについて、その構造をモデルとして抽象化し、遊び/ゲームの体験性の本質に迫ります。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて
5.5.4 遊び-ゲームにおけるルールを循環モデルとして再記述する
一見すると構造が固定されているようなルールやゴールについても、循環モデルで記述しなおすことができる。
構造として固定されているものを、ルールやゴール、ソースコードといったゲームのメカニクス部分だと考えたとき、そこからその都度、算出されるのは一回ごとの試合などのゲームプレイにあたる部分になるだろう。
ビデオゲームのハードウェアやソースコードの改造が難しいような形で提供されているクラウド型のオンラインゲームのようなものでは、ゲームプレイを通じて固定された構造を変化させることは難しい[6]。ビデオゲームをこのように観察するならば、ビデオゲームは固定的層をもった構造と、それから算出されるものというモデルによって捉えられることになる。
しかし、ビデオゲームにとってのルールとは実際にはもう少し緩やかに決定されていくような性質ももっている。すでに何度か触れているとおり、大きな格闘ゲームの大会や、RTAの大会などでは、どのキャラを使ってはいけないか、いわゆる「裏技」のようなものをどこまで使用してもよいかなどといったことが、大会が会を重ねるごとに少しずつ調整されて変化していくことがある。
ビデオゲームの大会の場合は、ソースコードとして固定された部分と、長期で見た場合にはある程度の可塑性がある大会のレギュレーションという二段構えだが、スポーツの大会などでは後者のようなレギュレーションがベースであるため長期的にはスポーツのルールは可塑的なものであるといえる。
実践を通じて、ルールに変化が加えられ、調整が働いていくプロセスは我々の日常的な慣習や、共同体内での規範、法といったような様々なルールにおいても見られる側面である。
これらのプロセスを順序として観察するのであれば、ルールの書き換えられるプロセスということになる。つまり、試合における想定外の発生→ルールの書き換え→想定外の発生→ルールの書き換え→……といった形として整理できる。
また所与のルールで処理できない行為がなされた場合には、それは「不正」とみなされたり、ゲーム自体に関わりのない行為とみなされることになる。ビデオゲームのルールの特徴として、現時点のセンサリング技術等によって定量化したり、入力情報として評価が可能な程度のものでなければ評価ができないという特性がある[7]。複雑な意味の解釈が困難になるケースが多いというのが、ビデオゲームのようなメディアにおいては一つの特徴となっている。一方で、TRPGや『キャットアンドチョコレート』のようなアナログの会話ゲームでは、捻ったユーモアのような、意味的にかなり複雑なものであってもゲームの要素として判定が可能である。行為の評価者が人間であることによって、はじめてそれは可能になっている[8]。
下記に同じくまとめておく。
・観察困難:無秩序/ゲーム外の行為/不正・順序として観察:試合における想定外の発生→ルールの書き換え→想定外の発生→ルールの書き換え→…・可塑的な複層構造として観察:制度(慣習、ルール)―試合・ゲームプレイ・固定的な複層構造として観察:ゲームプログラム―試合・ゲームプレイ
-
中心をもたない、現象としてのゲームについて 第39回 第5章-5 ゲームを循環として再記述する|井上明人
2024-08-27 21:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。
ゲームに「飽き」ることや「上達」「特殊プレイ」開始の過程、あるいは対戦/協力プレイヤー同士のコミュニケーション、それらに共通する構造をモデル化し、ゲーム/遊びの体験の普遍性に迫ります。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて
5.5 ゲームを循環として再記述する
さて、「循環」の概念を捉えるための道具立てとして四つの観察モデルが整ったところで、ようやく「循環」の概念がなぜゲーム全体を統合的に捉えるキー概念なのかを示したい。
一言で言えば、ゲームを遊ぶというプロセスは、多様な循環プロセスであると言えるからだ。それゆえ、これまでの各章で議論してきた内容の多くを、循環プロセスとして再記述することが可能だという性質をもっている。
ここまで示してきた四つの観察モデルを用いて、ゲームの循環プロセスが実際にどのような形であてはまるのかを示したいと思う。この作業を通して、遊び-ゲームに関わる様々な概念が相互にどのように関係しているのかの関係性を理解することができる。すなわち、どのように様々な概念が繋がっているのか、ということが「循環」の概念を通して理解ができる、ということだ。なお、下記で再記述する対象とする学習説のプロセスや、非日常、コミュニケーション等の話は、いずれも第三章で一度長めに言及した概念である。
5.5.1 学習説のプロセスを循環モデルのバリエーションとして再記述する
まず、改めて学習説的なプロセスを四つの観察モデルによって整理してみよう。
本連載の中心的な論点の一つだった、ゲームの学習プロセスについて、そこで現れる様々な様態を四つの観察モデルによって、記述することができる。
基本的には、ゲームを遊ぶことはプレイヤーの認知が可塑的に変化していくプロセスである。[1]ゲームの学習説を純粋に認知プロセスの説明として見直した場合は、可塑的な複層モデルとして観察される。ここまで説明してきたように、気ままにゲームを遊ぶプレイヤーの多くは遊ぶ目標も、その手段も、ゲームへの理解へのあり方も、遊ぶうちに徐々に更新されていく。
その中でも、ゲームの学習の方策が固定的になったり、ゲームの上達の目標事態が固定的になるかどうかといった点については、ゲームプレイヤーによって異なり、可塑的な構造の中にも、変化を拒む構造が現れる。プロのゲームプレイヤーになろうという人は、どのようなゲームであれ、ゲームの大目標がある程度固定された形でゲームに向き合う態度を持つことになる。
学習することとは飽きることと、上達が交互に繰り返し、循環するプロセスとして記述することができる。
学習説が類似の行為の繰り返しから成り立つことは、学習説を論じる上での前提として提示してきた。学習説的な事態の中には、再帰的な反復によって、あるゲームに上達していくプロセスが含まれている。そして、また学習が止まったとき、そこには「飽き」が訪れやすくなるという前提にたっている。
「飽き」たときに、上達プロセスそのものから降りてしまい、ゲームをやめてしまうこともあるが、飽きた後にいわゆる「やりこみ」のプロセスに入ることもある。そもそものルールを少し改変した状態でゲームをしてみたり、少し似た別のゲームを開始するといったプロセスはまさにこれだ。
こういった「逸脱」は、「遊び」の領域における中核となる概念としてしばしば位置づけられる[2]。二次的現実からの逸脱(飽き)は、一次的現実からの逸脱(ふざけること、油を売ること)とは区別すべきものだが、前項で述べたように大きく「逸脱」という視点を設定したとき、両者は概ね似たようなものとされることが多い[3]。
「逸脱」(≒遊び)は、一次的現実からの逸脱であるにせよ、二次的現実からの逸脱であるにせよ、繰り返しの習熟プロセスにいったんリセットをかけて、別の形でプロセスを再起動させるための契機として機能しうるものでもある。そのため、逸脱それ自体に循環的な側面はない。「それ以上、上達をしなくなったとき」にフォーカスの方向性を変えることで「新たな上達プロセス」を開始することができる。新しい領域に向かわせるような機能をもっている。
そして、こうした様態は、逸脱行為(怠けてゲームをはじめる)→適応行為(ゲームに上達する)→逸脱行為(通常のゲームに飽きる)→適応行為(特殊ルールでのゲームプレイに上達)→…といった順序的プロセスとして適応と逸脱のプロセスを記述することができる。
もちろん、遊びはじめたゲームの中で何をやればいいのかわからないという、「どうやってゲームを遊んだらよいのか、わからない」という状態も当然あるし、上記のゲームにハマって、ゲームに飽きて…とかいうプロセスの中で、今までやっていたことをやめるという状況は具体的に、次に何をやろうか、というような行為の焦点が構成されないことももちろんある。
上達に向けてゲームプレイヤーが自己の身体を統御していくプロセスも、ゲームに飽きて逸脱をしていくプロセスも、いずれもゲームを遊ぶという行為の循環のうちの一側面としてここでは記述可能になる。適応と逸脱、シングルループとダブルループ、学習IIと学習IIIといった学習をめぐる様々な概念系を、いったんこの四つのモデルによって整理することができる。
上記の議論を簡単にまとめておこう。・観察困難:(解釈が難しい逸脱)・順序として観察:逸脱行為(怠けてゲームをはじめる)→適応行為(ゲームに上達する)→逸脱行為(通常のゲームに飽きる)→適応行為(特殊ルールでのゲームプレイに上達)→…・可塑的な複層構造として観察:きままにゲームに上達するプロセス・固定的な複層構造として観察:(※大目標が固定されたケースとしては、プロプレイヤーなど)
-
中心をもたない、現象としてのゲームについて 第38回 第5章-4-5循環のバリエーションを考える:4つの観察モデル|井上明人
2023-12-20 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。
「レベル上げ」や「素材集め」などの「作業」が一概に攻略のための「手段」とは言い切れないように、ビデオゲームにおける「目的ー手段」の関係は構造的に不安定さを抱えます。今回はゲームにおける「目的ー手段」関係の揺らぎを理論化し、ゲームを楽しむ体験がどのように構築されているか考察します。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて第38回 第5章-4-5 循環のバリエーションを考える:4つの観察モデル
5.4.5.1 共通の性質をもったものたちは、どこまで同じものか?
さて、少し話の論点が増えてきたので、話をあらためて整理していきたい。 ここまで大雑把に、逸脱と循環の双方があるようなプロセスについて述べてきたが、逸脱と循環の双方の側面を持ちうるようなプロセスとして、いままで挙げてきたものは次のようなものだった。 ・プロスポーツ選手による、上達戦略のメタ的再構築(意図的な再構築によるもの)を通した訓練[19]・プロスポーツ選手による、同じ訓練に「飽きる」ことを肯定した上での訓練[20]・組織における旧式の評価基準の見直しを伴う、組織の再構築や訓練[21]・社会における旧式の評価基準の見直しを伴う、社会制度の再構築や訓練[22] ・子供の砂場遊び[23] ・パフォーマンス芸術[24] ・意図せざる行為の自己目的化が起こり、行為自体が複雑化し、当初期待されていた範囲から抜け出ていくもの(やりこみなど)[25] このように並べてみると、これらは逸脱であると同時に適応であるような側面のある一連のリストになっているのかもしれないが、冷静に見つめ直してみると、本当に同じものだと言っていいのか不安になってくるリストでもある。共通する性質を見出すことはできるのかもしれないが、これらの中にはかなりの違いもある。 遊び-ゲームを循環としてみなす議論の類型について、なるべく基本的な概念からはじめて整理をしてみよう。
5.4.5.2 固定層モデルと可塑層モデル
循環をめぐる観察のバリエーションについて、上記のリストを眺めてみて思うのは、これらは安定と変化のようなものをどのように構造化し、どのようなバランスで共在させているかということのバリエーションだという印象を持つことができそうだ。 この、安定と変化というものを、もう少し丁寧に概念化していくための概念を導入しよう。 何かの力を加えられたとき元の構造を維持する力が強いものと、元のあり方自体が変化してしまうものを区分する概念として「可塑的(plastic)」という概念が、人間の認知について語る上でしばしば用いられる。 この概念を用いて遊び-ゲームをめぐる観察のモデルの差を、まずは二つに分けてみたい。 第一の観察のモデルは、ゲームの展開を生み出す前提自体は確固たる不変のものとして存在し、ゲームプレイヤーはそこから生成されるものと戯れているものがゲームであると考えるモデルである。この発想では、ゲームを遊ぶということは(1)固定されたゲームメカニクスの構造と、(2)そこから現象する活動、という複層構造を持つものとして記述することができる。あらかじめ設定されたゴールや勝利条件を達成する行為だけがゲームを遊ぶというものだと考えるものだ。こうしたゲーム観はビデオゲームにおいては一般的なものだといえるだろう。この発想からすると、ゲームプレイヤーは、もともとプログラムされたビデオゲームによって展開しうるバリエーションを実行するための媒介者に過ぎない。ビデオゲームの前提自体は固定されており、ゲームプレイヤーが何をしようともビデオゲームのプログラムに影響を与えることはない。この複層的だが、前提が固定されて変わることのないモデルを、固定層モデルとしてここでは名付けよう[26]。 第二は、ある程度まで安定的な構造があり、その構造から現象するものが循環的に構造を自己変容させていくという観察だ。ゲームプレイヤーは、ゲームの遊び方や上達の仕方に、しばしば変化を加えていく。コントローラーを変えたり、裏技を使ったり、縛りプレイもあれば、ズルとみなされる類のテクニックを使うプレイヤーは少なくない。遊ぶ活動を通して、ゲームメカニクス自体に変化をもたらしたいという欲求が生じ、その結果としてゲームのそもそもの構造自体を改変させていくという関わり方は遊び方としてかなり広範に観察される行為である(Consalvo 2009)[27]。この状況下では(1)ゲームメカニクスの構造は少しずつ変化を加えてよいものであり、(2)ゲームのメカニクスとゲームを遊ぶという二層の構造は、相互作用を起こすもの、という形で整理できる。この構図は「循環」という概念によって想起されうるモデルだろう。このモデルでは、もともと設定された勝利条件から離れた遊び方は、特殊なものではない。むしろ遊ぶという行為のごく標準的なあり方として捉えることができる。この可塑的で複層的なモデルを可塑層モデルと名付けよう。可塑層モデルと固定層モデル
5.4.5.2.1 可塑的なものと固定的なものの並列
固定層・可塑層という二つのモデルは、同じものを再生成しつづける構造と、何かを生成することを通じて生成の構造自体が変化するものという区別である。この固定層・可塑層といった二つの説明モデルを通じて、ここまで述べてきた議論――学習の仕方が固定されているものと学習の仕方自体を再構築されていくもの――という二つを考え直してみよう。 ざっくりと言えば、学習の仕方が固定されている前者が固定層モデルで、学習の仕方の再構築があるものが可塑層モデルにあてはまるように考えたくなるところだ。しかし、そのように直接的な当てはめをするのであれば、丁寧な概念化をする必要ない。 人間が学習し、上達するというプロセスはそれ自体が可塑的なものだ。人間の理解の枠組み自体は(脳の病気などが無い限りは)可塑的な柔軟性を持っている。つまり、学習や上達を含む一連のプロセスは、可塑的な側面を持つ。 一方で、「目標」については、目標自体が固定される場合と、固定されない場合とで分けてしまうことができる。目標の方向性が固定されていれば、シングル・ループの学習となり、飽きることや学び方の目標を変更することのできるものであればダブル・ループの学習に繋がりうるものだ。 すなわち学習の仕方が固定されている場合というのは、「認識は可塑的に変化しているが、目標は固定的」で、学習の方策自体が再帰的に変化するものは「認識が可塑的であると同時に、目標も可塑的である」という形をとる(下記の図を参照)。下部二層:シングルループ/ダブルループ これで、シングル・ループの学習と、ダブル・ループの学習の間の差は整理できそうだ。 しかし、これでもスポーツ選手の訓練と、ゲーマーが様々なモードを揺蕩うことの差は区別できない。 スポーツ選手など、自己の行為を律するタイプの人が行為のメタ認知を行いながら学習を再帰的に変化させていくのと、ゲーマーが思いがけず行為の自己目的化を行ってしまった結果として、どう評価すればよいのかわからないような複雑さを手にしていくようなプロセスはどちらも、行為の目標の水準で学習を再帰的に変化させていくという意味では同じものだ。 ゲームを遊ぶという行為のなかで、社会的評価が変わりやすい、これらの行為の違いはどこにあるのか。少し注意深く考えれば、この両者には「目標」の制御の内実に違いがある。 スポーツ選手による訓練方針の再構築では、行為のおおもとの大目標の部分はあまり変化しないことの方が多いだろう。スポーツ選手であれば、訓練の方針が変わったとしても、スポーツで良い結果を残すという基本的な方向性自体は変わらないはずだ。 一方で、自宅でゲームをする人が、うっかりゲームをやりこんでしまうときには守らなければならない大目標はそれほど固定的ではない。ゲームを楽しむとか、ラスボスを倒すとか、ゲームに上達するといった大目標が変化することを許容する性質をもっている。(下記の図を参照) 下部三層:目標だけが可塑性を持たないケース -
中心をもたない、現象としてのゲームについて 第37回 第5章-4 「循環」概念をめぐって|井上明人
2023-12-08 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。 「逸脱」としての「遊び」と「同化(洗練)」としての「ゲーム」、両者の「循環」がある種の理想として語られがちなゲーム研究において、その視点の妥当性を改めて検討し直します。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて第37回 第5章-4 「循環」概念をめぐって
5.4.1 遊ぶ/遊ばれる
「循環」概念は、遊び-ゲームをめぐるキー概念の一つである。 そして、おそらくこの、遊びの「循環」をめぐる現象は遊び-ゲームをめぐる多様な現象を、一つの現象のような形で統合させている主犯の一つであろう。 遊び-ゲームをめぐる循環の問題は、特にドイツ系の遊び-ゲームの論者(およびそれに影響を受けたドイツ哲学に強い研究者)においては強調される。 シラーの議論の後、20世紀前半にはボイデンディクが、シラーやフロイトへの批判を行う。ボイテンディクによれば、シラーやフロイトの議論が主観的な精神活動の内部の活動のみに注目しており、その外部との関係が意識されていないということに着目しはじめた。 ガダマーもボイテンディクの議論を読んだ上で「すべての遊びは遊ばれることだということである。」と述べる[1]。ガダマーは「遊び手」が状況を制御するという特権性を持たないということを述べるため、いくつかの例を挙げている。一つには、遊び相手の必要性である。ガダマーは次のように述べる。
「遊びであるためには、たしかに現実に他者が加わる必要はないにしても、遊ぶ者の遊び相手、すなわちその一手に対して自ら逆襲する別のものがいつも存在しなければならない。遊んでいる猫が毛糸の玉を選ぶのは、毛糸の糸が一緒に遊んでくれるからであり、ボール遊びが無限に続くのも、いわばそれ自身が思いもよらないことをしてくれるボールのまったく自由な動きによるのである」[2]
西村清和もガダマーやボイテンディクの視点に影響を受けつつ「遊びつつ、遊ばれる」[3]という視点を重視し、遊びに関わる広範な現象をこの視点から説明しようと試みている。 ガダマーの述べるとおり、遊ぶという行為は、遊び手が全てを制御できるものではない。遊ぶという一連のプロセスは遊び手の意図の外側にあるものによって遊ばれる現象でもある。 この循環的な側面は、かなり広範な説明力をもっている。 まずは、前回の最後で述べたとおり、循環的な概念の「理想化」の問題から議論をはじめることにしよう。
-
中心をもたない、現象としてのゲームについて 第35回 第5章 ゲーム/遊びはなぜ分かれ、接続するのか|井上明人
2023-07-18 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。 連載本編としては実に4年ぶりとなる論考です。本章から「ゲーム(game)」と「遊び(play)」の定義を分析しながら、文化人類学的視点で「ゲーム」の本質を探ります。複数の言語での定義や、ホイジンガ、カイヨワといった古典を参照しながら、近年の研究において「ゲーム/遊び」の分節・重なりがどのようにみなされているか概説しました。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて第35回 第5章 ゲーム/遊びはなぜ分かれ、接続するのか
5.1 gameとplayの分節と連結
さて、学習、コミュニケーションの問題を扱ってきたが、最後の大きな論点として「プレイ≒遊び」の概念を考えたいと思う 。 「遊び」の概念は、「ゲーム」の概念を考える上で、しばしば重要な論 -
我々は「事件」の起こらない世界をどのようにして見つめればよいのか|井上明人
2021-12-07 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。今回は、何気ない「散歩動画」やゲーム実況動画がなぜ視聴されるのかについて考察します。人間の動機付けに介入する「ゲーミフィケーション」についての著書もある井上さんが、改めて「没入」を可能にする体験デザインとは何かを捉え直しました。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて 我々は「事件」の起こらない世界をどのようにして見つめればよいのか
▲散歩動画を探すための100万人以上の都市マップ(※PCからのアクセスで検索可能)
じっくりと増えてきている「散歩動画」
ここ数年の間に、主観視点で撮られた無編集のYouTubeの散歩動画のアップロード数がゆっくりと増えてきている。100万人以上の都市部であれば、世界のほとんどの地域で、その風景をYouTube経由で散歩しているのを見ることができる。アフリカや、アジアの貧困地域では、やや動画が見つかりにくい地域もあるが、それでも世界の大半の都市風景が動くところをたちどころに見ることができるようになってきている。風景を見るだけであれば、Googleストリートビューでも見ること自体はできるが、都市の人々が、動き、生活するその様を高解像度で確認することができる。世界遺産も見ることができるし、日本に限って言えば、急行の停まるような駅ならだいたいの駅周辺の風景が収められている。 こうした動画が急増しつつある背景には、手ブレがほとんど気にならない高解像度の屋外映像が、簡便に撮りやすくなってきたことがその一因にある。2020年前後の段階で、iPhone 11 Pro MAX以後のPro MAXシリーズや、Osmo Pocketシリーズ、GoPro、Sony ZV-E10などといったおよそ3万円~10万円強ぐらいで手に取れる屋外撮影に適した小型カメラの選択肢が揃うようになってきた。
▲YouTubeビデオを前に歩く
これらの動画は、とくに何か劇的なことが起こるわけではないのだが、ものによっては数万、数十万の再生数になっている動画も少なくない。誰がどのように楽しんでいるのか、その全貌はいまひとつよくわかりきらないところがあるが、私個人としては、散歩の動画をを映し出しながら、同期して、画面の前で足踏みするというのが面白いよ、というのを広めている。特に、画面の前で足踏みをしながら、友人や家族など誰か親しい人と数十分ほど一緒に歩くと、あたかもその土地に旅行にでも来たかのような気分を味わうことができる。 去年から、ちくちくと動画を探して、おすすめの散歩動画の一覧も作った。コロナ禍のなかにも関わらず、サマルカンドや、ウイグル、ジャマイカなどの世界の都市風景に親しみを感じるようになってきた。
暴動とデモの境を歩く
こういった動画は、単にさまざまな都市の風景を観光的に記録するだけでなく、その地域の重要な時間も記録している。 この文脈でさまざまな動画を探し歩いているのだが、特に印象深かったものの一つが、2020年のBlack Lives Matterのデモ隊に参加した人の動画だ。抗議活動の風景をそのまま歩きながら主観視点で撮影した無編集の動画がYouTubeにいくつもアップロードされている。
▲「protest 4k walk -vlog」でYouTubeで検索をかけた結果
私は、その動画を大きなモニターで映し出しながら、デモ隊と供に数十分の道程を歩いた。 最初、デモ隊は、警察の庁舎を抗議活動に参加した全員で取り囲むことを目標に据えて、行進は、おだやかに開始される。「Black Lives Matter!」「Black Lives Matter!」の掛け声とともにデモは進む。 しかし、十数分したところで、デモ隊は数十人の警察官によって行進を制止させられる。警察官の指示によれば、この先を直進せずに、左に曲がれという。警察からの要請は「左に曲がれ」それだけだ。 その要求を聞いたデモ隊の人々は、急速にざわつきはじめ、デモ隊に参加している黒人の男性が、悲痛な表情とともに警察に対して絶叫をはじめ、デモ隊の他のメンバーが彼に説得をはじめる。 それまで、平和的に歩いていた人々の行進が、たった3分で急激に雰囲気が変わり一触即発の空気が流れる。他の地域でのこの抗議活動ではすでに死者も出ているときだ。 現場の空気感は、この抗議活動が平和なデモとして終わるのか、それとも暴動と見分けのつかないようなものに変わりうるのか、そのぎりぎりの瞬間を映し出す。
▲ざわつきはじめるデモ隊(出典:https://www.youtube.com/watch?v=tdo2_0affNU<2021年11月5日閲覧>)
デモの参加者たちからは、警察を罵る絶叫をする人間が現れ、警官隊も、このデモが暴動に発展したとしても対処ができるように、陣形を組み始める。 数分ほど、何人かのデモ隊参加者からの絶叫が続く。供に歩いていると、直接的な暴力による衝突が発生するかと思われる雰囲気に飲まれそうになる。その場で、必死の形相をしている人々を前にして、この場でどう動くべきか、ということを考え始めようとしている自分に気づく。実際は、その場にいるわけでもないのに。 その後、しばらくしてデモ隊は、警察の要請どおり、ルートを変更して左折しはじめる。ぎりぎりのところで、このデモ隊は暴動には発展せずに、デモ隊も、警察もともに際どい雰囲気のなかをどうにか終わらせることに成功する。 結局、この動画では、直接的な衝突は起こらない。 緊張感のある場面はあるものの、この動画は、暴動という事件が起こらなかった動画だ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
なぜ異世界は、100周目ではなく2周目なのか|井上明人
2021-06-01 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。いまやアジアの共通言語になっている「異世界転生」について考察した前回に続き、さらにそのストーリーテリングの本質を掘り下げます。日本でのその隆盛の発信源となった「なろう系」の作品傾向で突出する、異世界で「2周目」の人生をやりたい放題に生きるという物語。たとえば2000年代には同じ人生を何十、何百周もやり直す「ループもの」が流行したのに対し、なぜ圧倒的に「2周目」なのか? ゲーム体験の掘り下げから、その疑問を分析します。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて 番外編 なぜ異世界は、100周目ではなく2周目なのか
やたらと多い「2周目」の転生の物語
なぜ、異世界はやたらと「2周目」が多いのだろう。 3周目や、100周目の話も存在はしているが「2周目」を主軸とした話がやたらと多い。『無職転生』『転生したらスライムだった件』などはその筆頭だろう。長い話のどこかに3周目以後の問題が挟み込まれていることがあっても、主軸となるストーリーラインは、現代社会から転生して異世界で2周目をやりたい放題する話である。もしくは、異世界の住人が異世界に転生して、やりたい放題の2周目を生きる。こういった話が多い。 この傾向は、「小説家になろう」のランキング上位作品につけられた作品内容を示すタグの中身をみてみると確認できる。次に示すのは、上位300作につけられたタグを集計したものだ。(2021年5月5日時点)
1位 異世界転生 97作品 32% 2位 異世界転移 86作品 29% 3位 チート 85作品 28% 3位 異世界 85作品 28% 5位 ファンタジー 78作品 26% 6位 魔法 70作品 23% 7位 男主人公 65作品 22% 8位 冒険 61作品 20% 9位 主人公最強 59作品 20% 10位 書籍化 54作品 18% 11位 ハーレム 47作品 16% 12位 成り上がり 44作品 15% 13位 ハッピーエンド 33作品 11% 13位 ほのぼの 33作品 11% 13位 女主人公 33作品 11% 16位 オリジナル戦記 30作品 10% 17位 恋愛 29作品 10% 18位 転生 28作品 9% 19位 ざまぁ 27作品 9% 20位 悪役令嬢 26作品 9% 20位 日常 26作品 9% 22位 コミカライズ 25作品 8% 22位 ダンジョン 25作品 8% 24位 ラブコメ 24作品 8% 25位 ご都合主義 23作品 8% 25位 剣と魔法 23作品 8% 27位 貴族 22作品 7% 27位 魔王 22作品 7% 29位 学園 21作品 7% 30位 追放 20作品 7% 30位 内政 20作品 7%
レーティングを示す「R15作品(78%)」、「残酷な描写あり(71%)」を除くと、そのほとんどが2周目を示す「異世界転生」タグは、上位300作品中の三つに一つに見られている。 より上位の作品になるとその傾向はさらに顕著になり、累計ランキング上位30作品だと、ちょうど半数の15作品に〈異世界転生タグ〉が付けられている。下記は、異世界転生タグの付けられているランキングのトップ作品だ。
〈異世界転生タグの付けられた累計上位30位以内作品〉[1]
・伏瀬『転生したらスライムだった件』 ・理不尽な孫の手『無職転生 - 異世界行ったら本気だす -』 ・馬場翁『蜘蛛ですが、なにか?』 ・ハム男『ヘルモード ~やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する~』 ・愛七ひろ『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』 ・逢沢大介『陰の実力者になりたくて!』 ・Y.A『八男って、それはないでしょう!』 ・香月美夜『本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~』 ・FUNA『私、能力は平均値でって言ったよね!』 ・甘岸久弥『魔導具師ダリヤはうつむかない』 ・錬金王『転生して田舎でスローライフをおくりたい』 ・ひよこのケーキ『謙虚、堅実をモットーに生きております!』 ・沢村治太郎『元・世界1位のサブキャラ育成日記 ~廃プレイヤー、異世界を攻略中!~』 ・夜州『転生貴族の異世界冒険録 ~自重を知らない神々の使徒~』 ・吉岡剛『賢者の孫』
ここに挙げたほとんどの異世界転生小説は、その多くが「2周目」の物語だ。これは、男性向けの異世界ハーレム、チート系と言われる作品だけでなく、女性向けの悪役令嬢ものでも、2周目の転生というフォーマットが踏襲されがちである。 単に、主人公が強いという設定が必要なのであれば、10周目や、50周目の存在のほうが、よほど強いはずである。しかし、なろう小説ではそういった話は多数派ではない。 よく言われるように、もし、なろう小説が単に「ゲームの想像力をそのまま反映した小説」であるということであれば、20周目の主人公とかが、もう少し登場してもよいはずなのにも関わらずだ。 なろう小説の外に目を向ければ、同じ人生を何十周もする話は数多くある。比較的物語の文化として近いところにあるライトノベルであれば『オール・ユー・ニード・イズ・キル』[2]しかり、ノベルゲームならば『ひぐらしのなく頃に』(以下『ひぐらし』)しかり。 人生を何十周もするという世界観がベースになっている話自体は、今どきまったく珍しくない。 (以下、いくつかの『ひぐらし』のネタバレを含む)。 『ひぐらし』では、物語世界内で他のキャラクターに対して、かなり強い立場の人間として、昭和50年代の雛見沢村を何周もしていることを自覚しているキャラクターが登場する。このキャラクターが『ひぐらし』の世界内において強力な立ち位置を占める理由は、もちろん人生を何十周もしているからにほかならない。同じ事件がおこる昭和58年6月の雛見沢村を何度も何度も見ていれば、雛見沢村で起こりうることに精通するのは当然で、問題を解決するのに一番近い地位にいる立場になることができる。あたりまえである。 「繰り返される世界で強い立場を得る」ことを、少ない設定で説得的に描くならば、ゼロ年代ノベルゲームで普及したループ式の物語形式を踏襲しても良さそうなのにも関わらず、なろう小説ではそれが踏襲されていない。『ひぐらし』はもちろん「Fate」シリーズ、『月姫』、『CROSS†CHANNEL』『Steins;Gate』など、ゼロ年代にヒットしたノベルゲームだと、ループものは、現在の異世界転生に匹敵するほどによく普及した形式だった。なろう小説のヒット作品でこのループ形式を明確に受け継いでいる作品もある(『Re:ゼロからはじめる異世界生活』)。だが、なろう小説群の中ではあまりメジャーな設定ではない。転生系と同じぐらいか、それ以上に「追放復讐系」「転移・召喚系」もかなりの数を占めているが、この「2周目」フォーマットの興味深い点は、韓国発のなろう系(ウェブトゥーン)でも、中国のなろう系(閲文集団)でも、メジャーな形式として受け入れられているということだ(もちろん、2周目以外のフォーマットもある)。 主人公が強くなるという点以外に、2周目の転生物語と、ループの物語は何が違うのだろうか。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
アジアを羽ばたいてしまっている異世界転生|井上明人
2021-02-02 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う『中心をもたない、現象としてのゲームについて』。今回は番外編として、韓国・中国での「異世界転生」ものの方向性の違いを考察します。いまやアジアの共通言語になりつつある「異世界転生」ジャンル。その多くが「復讐劇」の形態をとる点はよく似ていますが、日本ではいじめられっ子が個人的動機から強者を見返すパターンが多い一方、中国・韓国ではそれぞれの社会の特質を反映し、復讐にまつわるモチベーションのあり方が大きく異なるようです。
井上明人 中心をもたない、現象としてのゲームについて 番外編 アジアを羽ばたいてしまっている異世界転生
「ピッコマ」から見える韓国・中国での転生ものの隆盛
最初に異世界転生ものについて書いたのは、2017年だった。2017年時点では、ウェブ小説をベースとした異世界作品の消費はピークなのではないかと思っていた。しかし、異世界ものの快進撃は、2021年現在になっても、とどまることなくウェブ小説のコミカライズやアニメ化の波は多くの読者諸氏が知るところだろう。 そして、この波は、国内のみの状況にとどまらず、2010年代後半には、もはや韓国・中国を含むアジアをまたぐ一大文化現象になっていると言っていい。 この状況をもっとも、わかりやすく把握できるのは、2016年にサービスがスタートした、ウェブマンガアプリのスマートデバイス向けの漫画・小説アプリ「ピッコマ」である。 「ピッコマ」は韓国資本のアプリであり、ベースになっているサービスが韓国の「カカオページ」である。日本のマンガも数多く掲載されているが、韓国と中国のウェブマンガが多数日本向けにローカライズされている。そして、その多くに「転生」もののストーリーが含まれ、また、人気作品の多くが各国のウェブ小説をベースにしている。 たとえば、2020年の「ピッコマ」内でよく読まれた人気作品を見てみると、2020年に国内で歴史的な大ヒットを遂げた『鬼滅の刃』は、3位にとどまり、1位は韓国発の『俺だけレベルアップな件』(2016-、Chugong・h-goon・DUBU(REDICE STUDIO)、原題:나 혼자만 레벨업)、2位も韓国の『極道高校生』(2017-、原作lee hoon young、作画KIM EUI KWON、原題:보스 인 스쿨)(もとは、カカオページではなくtoomicsという別のサイトの人気作品)と韓国勢が上に並ぶ。そして、『鬼滅の刃』の次に並ぶのは、中国版の「なろう」とも言えるウェブ小説サイト「阅文集团」の人気作品『Retry〜再び最強の神仙へ〜』(2016?-、原作:十里剣神 作画:大行道動漫、原題:重生之都市修仙)となっている。
中世ヨーロッパ風ファンタジー世界ではなく、武侠世界に転生する中国系転生小説
では、「ピッコマ」でローカライズされるような作品は、「小説家になろう」のような異世界転生もの小説そのものかというと、似た点は多いのだが、全く一緒というわけではない。 大きな違いの一つを、ざっくりといえば、転生する先が、中世ヨーロッパ風の謎ファンタジー世界ではなく、中世中国風の謎ファンタジー世界である「武侠世界」に転生することが多い。 なろう小説であれば、D級冒険者・C級冒険者、B級冒険者……といった強さのランキングシステムがあるが、武侠ものであれば、一成、二成、三成……(あるいは、達人、一流達人、超一流達人……など)といった形で概念系が変わる。この概念系は、かなり普及しているようで、中世ヨーロッパ風ファンタジーであっても、中国・韓国の作品では、「一成、二成……」の概念が使われていることも多い。たとえば、『4000年ぶりに帰還した大魔導士』(2017-、kd-dragon(REDICE STUDIO)・落下傘・フジツボ、原題:4000년 만에 귀환한 대마도사)などは、ほとんどヨーロッパ風の登場人物しか登場しないが、強さの概念系だけは、「一成、二成……」がベースとなっている。 武侠世界観というジャンルは日本ではマイナージャンルだが、中国・韓国のコンテンツマーケットにおいては、もともと20世紀の中頃から広く受容されてきた超メジャージャンルである。この世界観が、いかに支配的なものかがわかるだろう。 物語のベースも、その影響があり近年の「転生」モチーフと、武侠世界観モチーフをかけ合わせたようなものも少なくない。たとえば、『神魔驚天記』(2016-、GomGuck・O'Emperor、原題:신마경천기)や、『華山転生』(2016-、tomassi・JUN、原題:화산전생)は、いずれも無念のなか死んだ主人公が前世の記憶をもって次の生に転生し、次の生で無双する。また、「もともと伝説的な武人だった主人公が死んだのち、数千年後に転生する話」などの設定も数多くあり、連載を追っていると、あまりにもそれぞれの作品の設定が似かよっているので、どの話がどの作品だったのか混乱してしまいそうになる感じなどは、まさに「なろう小説」を読んでいる感覚に近い。
復讐劇の日・韓・中
「なろう小説」が、設定だけは、一見して似ているが、中身にいくつかのクラスターがあるように、「ピッコマ」の転生物語群にも、いくつかの作品の方向性がある。 アジアの転生もの作品は、「復讐劇」の形態をとる作品が非常に多いのだが、復讐にかかるモチベーションのあり方がそれぞれに大きく異なっている。
(1)日本:いじめられっ子の復讐からの発展
まず、日本の復讐劇シナリオから確認しておくと、このジャンルは、すでにブームが一周した感があるが、2010年代前半からすでに、白米良『ありふれた職業で世界最強』(2013-)や、アネコユサギ『盾の勇者の成り上がり』(2012-)があり、2010年代後半には、勇者パーティーから無能の烙印をおされて追い出された主人公が、やりかえすというタイプのテンプレートが量産された。基本の物語フォーマットは、いじめられっ子がいじめっ子を見返すタイプの怨念系の話の亜種が多かった。最近は、復讐物語が基本フォーマットになりすぎたため、もはやいじめられっ子ストーリーとも言い切れなくなってきたが、日本の作品における復讐の対象は、クラスメイトだとか、もともとは対等な立場だった人間にたいする復讐がかなり多く見受けられると言っていいだろう。そして、追い出された主人公は何かしらの正義を主張できる立場にあることが多い。
(2)韓国:権力者に対する抵抗としての復讐
そして、韓国系の復讐劇シナリオだが、これは怨念の強さが日本よりもグレードアップする感触が強い。たとえば、ピッコマで連載され、国内で話題となっている作品に『梨泰院クラス』(2017-2018、Kwang jin、原題:이태원 클라쓰)(「ピッコマ」では、ローカライズの結果『六本木クラス』と改題)などはわかりやすいが、対決する相手が同じクラスのいじめっ子であるにしても、そのいじめっ子は、大財閥の息子であり、主人公を追い込んでくる存在は、社会的な権力者であり、韓国系の復讐劇シナリオの多くは、個人的な復讐劇である以上に、不当な権力に対する社会正義の実現という形式をとって表現されていることが多い。 先に紹介した、武侠ものの『神魔驚天記』や、中世ヨーロッパ風の『4000年ぶりに帰還した大魔導士』のどちらでも、権力者や支配者による陰謀が物語の大きな主題となっている。 韓国の「復讐モノ」は、日本人の読者である私にとっては、正直、やや情念が濃すぎる印象をもってしまうが、近代韓国社会において「権力者の陰謀」は日本よりも遥かに切実で実際にたびたび大きな事件が起こっている社会でもある(光州事件や、6月民主抗争など)。 日本的なコンテンツとは明らかに異なっているが、「韓国」という社会の特質がこういったところにも流れ込んでいるのをみることができるのは、興味深くもある。
(3)中国:弱肉強食の世界における復讐
さて、韓国の復讐劇までは、日本の多くの読者にとっても比較的、読みやすいというか日本の物語の類型の一種としても回収できないわけでもない。実際、日本の物語でも、権力者への復讐が要素として含まれていることは珍しくはない。その意味で、韓国と日本の物語の違いは、あくまで全体的な傾向性の話であって、いずれも「虐げられた弱者が正義の実現を図る」という点では、大まかには類似した物語である。復讐のモチベーションが個人的なものが強いか、社会的な文脈が強いかという違いがあるという程度の問題でしかないと言えば、そうなのである。 他方で、カルチャーショックを受けてしまうのは、やはり中国ウェブ小説発のいくつかの作品群である。一部の中国作品の復讐ものには、正義の問題というものが存在しない。 予め断っておくと、「ピッコマ」では、中国系コンテンツのローカライズは、韓国作品に比べると、そこまで多いわけではないので、ここで紹介する作品が中国という巨大国家の全体を代表していると言い切れるわけではない。……しかし、それでも、次に挙げるいくつかの作品を挙げたいと思うのは、やはり、どう捻っても、日本の物語の作品系譜からは出てこないからである。 まず、軽いジャブ的に紹介しておくと、たとえば、『最強課金プレイヤー』(2019?、原作:SHIWUSHUANG、作画:XIANGPIZHA、中国語原題:氪金玩家)は、その傾向をもった作品の一つだ。現実世界で、とある富豪にひどい目に合わされた主人公は、VRMMOの世界で再起を図り、自分を軽んじた相手にやりかえすのだが、そもそも、主人公自体がいささか落ちぶれたとは言え大富豪なのである。『最強課金プレイヤー』というタイトルがあらわしているように、主人公はゲームの世界に億単位の金額を使ってゲーム内世界で最強になっている。
『Retry〜再び最強の神仙へ〜』:登場人物の全員が悪役の発想
中国作品で、特筆すべき作品は、『Retry〜再び最強の神仙へ〜』である。最初に言及したとおり、2020年の「ピッコマ」ではアクセス数が、3位の『鬼滅の刃』に次ぐ4位の人気作品であり、「ピッコマ」内で、もっともたくさん読まれた中国ウェブトゥーンになる。 主人公は、500年修行した仙人だったのだが、仙人として命を失ったあとに大学生時代(日本では2019年)にタイムリープをして、人生をやりなおす。 本作は、弱肉強食の世界観なのであるが、この作品の提示する力こそが全ての世界というのは、たとえば『グラップラー刃牙』シリーズ(1991-、板垣恵介)など以上に一貫した「力」への信頼がおかれている。 比較のために刃牙シリーズとの違いを確認しておくと、刃牙シリーズの世界の中で「世界最強」というような概念が登場するとき、「最強」という価値観が重要な作品世界であることは、読者にむかって繰り返し説得される。銃が登場した近代以後の世界において、個人的な力を磨き上げることが無意味なのではないかというような、ごくあたりまえの考えを、あえて否定するために、刃牙シリーズの格闘家たちは一人で野生の猛獣を倒し、軍隊と立ち向かい、アメリカ大統領を震えさせる。刃牙シリーズは、そのようなフィクションのリアリティを説得的に繰り返し描くことではじめて成立する魅力的な法螺話である。 一方で、『Retry〜再び最強の神仙へ〜』は力が重要であるということを一切、誰も説得しない。説得しないし、それが重要であるとか、重要でないといったメタ的な価値について誰も、疑問を挟まない。登場人物の全員が、個人的な武力、財力、政治力、美貌といった現世的な「力」が何よりも重要だということについて、一切の疑問を持っていない。そして、誰も、復讐者の正義だとか、弱者の権利だとか、そういうことを口にしない。 復讐をするならば、ただ単に力でもって、相手を制圧すればよい。虐げられたら、ただ単にやりかえす。何だったら、殺したければ殺してもよいので、主人公は、けっこうどんどんと相手を殺す。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
1 / 7
次へ>