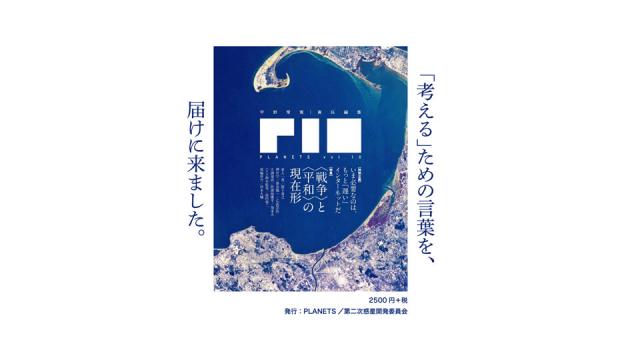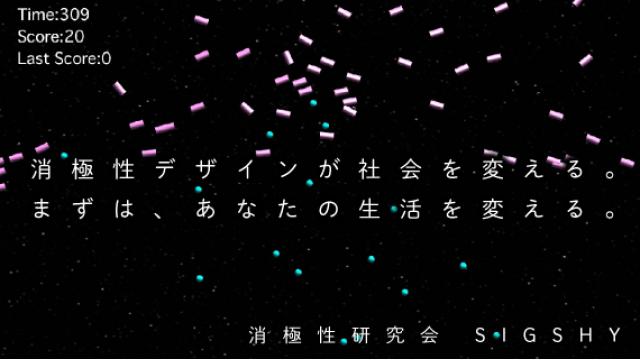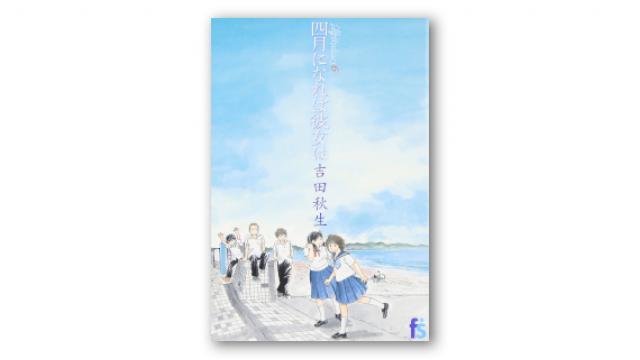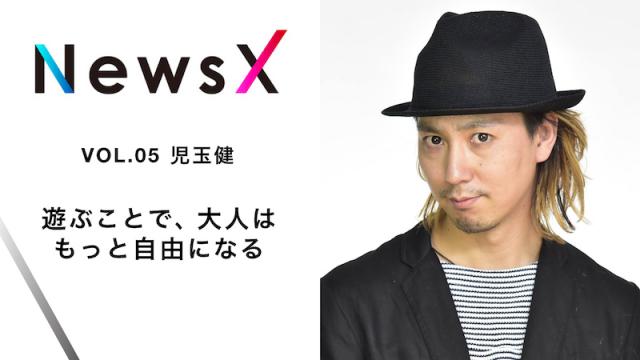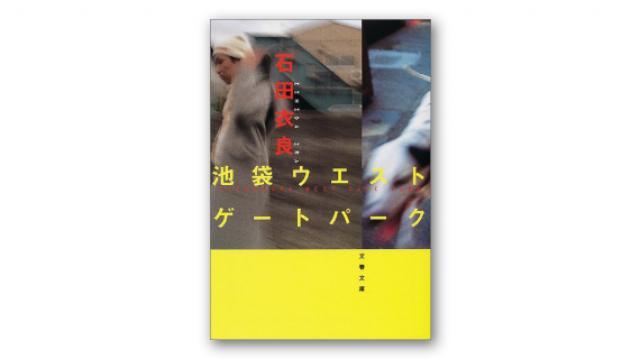-
11/10(土)スタンダードブックストア心斎橋(大阪)にて開催!『PLANETS vol. 10』刊行記念 宇野常寛トークライブ!(号外)
2018-11-08 18:0011/10(土)12:00~スタンダードブックストア心斎橋(大阪)にて、『PLANETS vol.10』刊行記念宇野常寛トークライブが開催されます!
★お申込みはこちらから
テーマ:「地方から文化を発信するには」
今号で10号を迎える宇野常寛責任編集の「PLANETS」は、12年前に京都で会社員をしていた宇野が創刊した「地方発の」ミニコミ誌だった。 この地方からの「小さな」スタートはいかにして、時代の最先端を切り取る最強のインディペンデントマガジンに成長したのか。 そしてメールマガジン、ネット放送、イベント、オンラインサロンなどを有機的にメディアとコミュニティを連動させる宇野とPLANETSはこれから何を目論むのか。 「地方」はこれからの最大のキーワードだと語る宇野常寛が、「第二の地元」関西で語り倒します。
参加者にはP10特製ステッカーの配布がございます! 関西近郊のみなさま、ぜひお越 -
『消極性デザインが社会を変える。まずは、あなたの生活を変える。』第7回 消極性デザインは悪い積極性にも効く(西田健志・消極性研究会 SIGSHY)
2018-11-08 16:50
消極性研究会(SIGSHY)による連載『消極性デザインが社会を変える。まずは、あなたの生活を変える。』。今回は西田健志さんの寄稿です。西田さんが開発し、学会で好評を博した傘連判状システム。この仕組みは(悪い意味で)積極的な人の声ばかり目立つ昨今のウェブで、消極的な人たちの意見に力を与えるシステムになりうるのでしょうか。その可能性と課題について論じました。※本記事に一部、誤記があったため修正し再配信いたしました。著者・読者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。【11月8日16:30訂正】
【お知らせ】 11月12日(月)にPLANETS CLUBの定例会で、消極性研究会から栗原一貴、簗瀨洋平、渡邊恵太の3名がゲスト講師として参加します(消極性研究会×宇野常寛 社会をなだめる #SHYHACK・PLANETS CLUB第9回定例会)。残念ながら私(西田健志)は参加がかないませんが、P10の座談会や本連載、そして消極性研究会の今後の活動について色々とご意見・ご感想いただけましたら幸いです。
消極性デザインは悪い積極性にも効く
本連載も無事1周しまして今回は西田健志が担当します。よろしくお願いします。
みなさん、PLANETS vol.10(以下、P10) はもう読まれましたか?今回はP10と併せてお読みいただくとより楽しめる内容にしたいと思いまして、私もいま8割くらい読んだところです。おもしろすぎて執筆が遅くなってしまいました。心よりお詫び申し上げます。(これを書き終わったら残りを読むんだ…)
P10には消極性研究会も「消極性デザインで平和を実現する―消極的な人よ、戦争を止めよ。いや、そもそも戦争しなければよい。」という座談会で登場させていただきました。宇野さんから「戦争と平和」というテーマをうかがったときには、これまで私たちが消極性デザインを試みてきたフィールドとの距離感を少なからず感じて期待と不安が半々くらいでした。でも終わってみると消極性研究会の持ち味が発揮された読み応えのあるものになったと感じています。ぜひご一読ください。
▲『PLANETS vol.10』
この座談会、2つの意味でいつもの消極性研究会と違いました。1つは、何も作らないでアウトプットしているところです。私たちも普段からSlackだとか飲みの席だとかで、ちょうどこの座談会のように大いにブレストを繰り広げていますが、それがそのまま世に出るということはまずありません。アイデアを実際に体験することができる何かしらのプロトタイプを制作したうえで世に問うというのが私たちの基本スタンスです。「消極的な人が暮らしやすいようにする」という目標設定で活動していくには言葉だけではインパクト不足だと考えてきたわけです。
しかし、今回の座談会で飛び交った突飛とも言えるアイデアの数々が思っていたよりも評判よく受け入れられているようで、今後の活動についても考えさせられるところがありました。司会や編集の腕前なのか、読者が訓練されているのか。それとも、実はいつものブレストにそれだけの価値があるのか…。
もう1つの違いは、「(悪い意味で)積極的な人を消極的にするには?」という枠で思考を広げる展開になったところです。普段、私たちの活動では消極的な人がメインターゲットで、積極的な人については「積極的な人にも消極的になるときがありますよね?」として、やはり消極性を念頭にデザインをしてきました。座談会でも序盤はどちらかというといつもの流れに乗っていたと思うのですが、後半にかけていつもと逆の流れになっていたように感じました。これまでにも栗原さんのSpeech Jammerのように積極的な人に対して用いるアイデア事例もありますが、それもあくまで「静かにしてほしい」と言えないでいる消極的な人の方を主語としているものでした。
しかし、流れは反転させながらも「人の性格を変えられなくても環境を変えることで行動は変えられる、ハックできる」という観点においてはいつも通りのやり口はキープされていたので、私たちにとってもちょうど次の一歩を示されたような、司会の確かな腕前を感じる時間でした。(誉めすぎ…?)
「遅いインターネット計画」
積極的な人こそどうにかしたいという発想になるのは、私たちよりも宇野さんは日ごろ積極的な人に目を向けることが多い(悩まされている?)からなのかなとも感じました。拙速なインターネット上のコミュニケーションから距離を置くことで良質な情報を提供することに注力しようというP10 の「遅いインターネット計画」にもそれが表れているように思います。そのつながりを感じたこともあり、遅いインターネット計画に関する議論についても大変な興味関心を持って読ませていただきました。
私がデザインしたコミュニケーションシステム、懇親会の座席を決めてくれるシステムを導入して利用してもらってきたのは学会や大学など、ある程度は人数が多いながらも外界からは閉じていて、たとえシステム上は匿名にしたとしても度を越した悪ふざけはしづらいし、積極的に問題行動を起こす人がいたとしても少数なのでその都度個別に対応すればまあ何とかなる、そういう世界でした。その視点から観測されやすいのは大多数の消極的な人たちと行動で、取り組まなければならないと感じるのも消極性デザインということになるわけです。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
本日21:00から放送!宇野常寛の〈木曜解放区 〉 2018.11.8
2018-11-08 07:30本日21:00からは、宇野常寛の〈木曜解放区 〉
21:00から、宇野常寛の〈木曜放区 〉生放送です!〈木曜解放区〉は、評論家の宇野常寛が政治からサブカルチャーまで、既存のメディアでは物足りない、欲張りな視聴者のために思う存分語り尽くす番組です。今夜の放送もお見逃しなく!
★★今夜のラインナップ★★メールテーマ「腹が立ったこと」アシナビコーナー「加藤るみの映画館の女神」and more…今夜の放送もお見逃しなく!
▼放送情報放送日時:本日11月8日(木)21:00〜22:45☆☆放送URLはこちら☆☆
▼出演者
ナビゲーター:宇野常寛アシスタントナビ:加藤るみ(タレント)
▼ハッシュタグ
Twitterのハッシュタグは「#木曜解放区」です。
▼おたより募集中!
番組では、皆さんからのおたよりを募集しています。番組へのご意見・ご感想、宇野に聞いてみたいこと、お悩み相談、近況報告まで、なんで -
井上明人『中心をもたない、現象としてのゲームについて』第30回 第三章 補論2:なろう小説におけるダダ漏れの欲望を考えるための2つの「切断」
2018-11-07 07:00
ゲーム研究者の井上明人さんが、〈遊び〉の原理の追求から〈ゲーム〉という概念の本質を問う「中心をもたない、現象としてのゲームについて」。今回のテーマは「なろう小説」の欲望のあり方についてです。従来のフィクションを(主人公と読者の)「主体の切断」を前提とした作品と捉えた上で、なろう小説やゲームを「利得の切断」の側面から改めて検討します。
昨今のコンテンツに詳しい人ならば、言うまでもないことだろうと思うが、「なろう小説」の欲望だだ漏れ感は、何かタガが外れているという感触がある。 チートによる俺Tueeeeと、(奴隷)ハーレムがセットになるというフォーマットは、控えめに言ってもやばい。「なろう小説」をはじめとする、異世界転生等の一群の物語については、本連載の第22回について扱ったが、俺Tueeee展開はともかくとして、あのハーレム展開っていうのはさすがにどうなのという人は多いと思う。この欲望ダダ漏れの表現はなんなんですかね、ということを、今回は書きたいと思う。
<お断り>ハーレムものの「望ましくなさ」について
本論に入るまえの、すこし「お断り」的な話をしておこう。今回、ゲームや物語における欲望について触れるが、ハーレムもの(あるいは逆ハーレムもの)の物語は、その多くが性的な欲望がだいぶ露骨な物語である。今回の原稿は、これを擁護するとか、批判するとかそういう話ではない。 もちろん、なろうの累計ランキングベスト10に居続けている、蘇我捨恥『異世界迷宮で奴隷ハーレムを』みたいな作品とかについて話すとなると、かなり色々と厳しいところがある。全部読んだが、本当にタイトルどおり異世界に行って、女の子の奴隷を買って、ダンジョンを探索していく話だ。主人公がわかりやすい悪人なんかであれば、ヤクザもののような、ある種の特殊な世界を描いた小説として切り離して読めるのでまだ良かったのだが、主人公は平凡で善良な日本人の青年だということになっていて、奴隷にも対等(?)で優しく、奴隷から愛されている「善良な」奴隷主をやっている話だ。主人公は読者にとって遠い存在として描かれているというよりは、読者の欲望を代行する存在として描かれている側面がどうしても強い。それも含めて、やはりこれは、露骨な欲望ダダ漏れ小説なのではないかという感触がエゲツない。 「書いてるほうも読んでるほうも、そこらへんの準ポルノ的な性質は、もちろん、わかって書いてて、わかって読んでますよね!?」ということに同意が得られる状態なのであれば話は簡単だと思うのだが、いかんせん、ここらへんの細かい話は複雑になりがちだ。 ハーレムものの反対で、イケメンにかこまれる逆ハーレムの令嬢モノというのもあるが、そういうものを見たら「これは、女性の欲望の話ですよね」と、多くの人が感じると思う。ハーレムものも、それと同様で「これは、男性の欲望の話ですよね」と言われたら、「まあ、そりゃ、そういう風に思われるよね」で、みんな納得してればいいのだけれども、どうも、そうなっていない。 「いや、でもこの作品はそれだけじゃない…!」みたいなことを言い出したりする人もいるし、「うーん、これは…微妙…男性側の欲望…と言えなくもない…?かな?どうだろ?」みたいなボーダーラインケースも多数ある。そしてボーダーラインケースについて、過激な主張をする人が出てくると議論に収拾がつかなくなる。 もっとも、なろう作品のハーレムもの(ないし逆ハーレムもの)については、ボーダライン上の作品もないとは言わないが、露骨に性的欲望の溢れ出た作品もかなり多い。そういった露骨な作品について「性的な欲望を満たす作品ではない」という主張をする気もないし、それは望ましくもない。
加えて言うのであれば、もし問題化するのであれば、個別の作品がどうこうというより、ジェンダーへの想像力が失われやすいメディア環境が総体として構築され、読者が批判を受け入れる感覚がなくなってしまうのは望ましくないと思っている。たとえば、映画の中でジェンダーバイアスを測る基準である、ベクデル・テスト(注1)というものがある。これは(1)少なくとも2名の名前のある女性が出てくる。(2)女性同士が互いに会話をする。(3)男性以外のものを話題にする。という3つの基準を測るもので、ベクデル・テストは個別の作品のジェンダーバイアスを論じるためには必ずしも妥当な基準だとは言えないが、おおまかな基準としては理解がしやすいため解釈にブレが生じにくいという意味で、信頼性(注2)の高い調査をしやすい基準である。この基準をもとに「ベクデル・テスト・コム」(注3)というユーザーが編集できるサイトで、実際に7800個以上の作品がチェックされ、データとして可視化されている。
Source: Robin Smith(2017),”Sizing Up Hollywood's Gender Gap” (注3)http://bechdeltest.com/
このデータを見るとわかるとおり、昔の映画は明らかにベクデル・テストの結果が悪い。1970年代前半の映画でベクデル・テストに合格しているのはわずか四分の一程度だ。1970年代に比べれば、2010年代の状況はマシだ。1970年代のメディア環境は、2010年代のメディア環境よりも、ジェンダーバイアスのことに思いを至らせるのが相対的に難しい状態にあった可能性が高い。 個別の作品についてどうこうというよりも、全体的なメディア環境をこのような指標を立てながら論じていくことができればよいと思う。重要なのは、個別の作品よりも、人々の想像力を生み出すトータルなメディア環境のあり方ではないかと思う。なろう小説などが、総体として、ジェンダーやセクシュアリティの多様性や、敏感であるべきポイントへの想像力を失わせるように機能してしまうことがあるのであれば、それは望ましくない。
以上のことを踏まえた上で本題に入る。
利得の切断
ゲームというメディアは、しばしば欲望を表出することをよしとするメディアである。RPGでキャラクターを育てて最強になろうが、ギャルゲーでハーレムエンドを目指そうが、『シヴィライゼーション』で帝国主義を展開しようが、『メタルギア・ソリッド』で敵兵士を虐殺してまわろうが、好きにして良い。むしろ、その欲望が叶えられていくプロセスを楽しむことこそが、ゲームを楽しむことと、しばしば同義である。 もちろん、『moon』『Undertale』『mother』など、そうした状況を批評的/批判的にとりあげる作品も一定数あるので、すべてのゲームメディアが、欲望を丸出しにすることを肯定しているとまでは言えない。ただ人文学者がゲームについて語る時、欲望を丸出しにすることへの「批判」はしばしばなされるし、海外のゲーム研究でも多数の議論がこうした素朴な欲望への批判が議論されている。 ただ、『moon』や『Undertale』はあくまでも、メインストリームに対する「批判」として機能している作品であって、ゲームシーンのメインストリームは、やはりゲームプレイヤーの欲望を叶えていくプロセスを肯定するものが多い。 敵がうざいから、殺す。虐殺してもよい。 女の子がかわいいから、落とす。ハーレムでもよい。 国を大きくしたいから、周辺諸国を征服する。帝国をつくりあげてもよい。 こういった欲望を実行するというのは、我々の日常的な倫理観からすれば、かなり問題のあることだ。しかし、ゲームのなかで、これは許される。 これが許される理由の一つは、これらの行為が「本当」になされるわけではないからだ。少なくとも、我々の生きる日常的な現実の利得とは切り離されたところに、ゲームプレイヤーの欲望は成立させられている。 ゲームをはじめれば、遊び手は一次的現実とは切り離され、特殊な目的を設定され、任意のルールのなかでインセンティヴ構造を与えられる。一次的な「本当」の現実とは別の、二次的な現実のなかでの行為であるというのが、ゲームを遊ぶときの前提である。ゲームのなかでゲーム内通貨を得ても、普通は円やドルに換金できるわけではない。 ゲームを遊ぶということは、特殊なルールを受け入れる、そこが特殊な時空間であることを受け入れることだ。ゲーム内の人々の行為のインセンティヴは、現実世界には即さない。勝利を大目的とした階層化した目的構成にしたがって、プレイヤーはどのような振る舞いをするのかを選ぶ。 ここでは振る舞いの特殊性も同時に成立している。これらは、ゲームというメディアの特質がそもそも持ってしまっているものだ。それが、ゲームという二次的現実において、「帝国主義的」であったり、「非人道的」とされる振る舞いが許される(場合によっては、積極的に推奨される)ことの理由だ。それゆえに、ゲームにおいて、「ゲームが設定したインセンティヴ構造」にしたがって動くことは、恥ずかしいことでも悪でもない、ある意味で普通の行為だ。町中で人を銃殺すればそれは犯罪だが、FPSで敵を銃殺するのはふつうの行為である。もし、ゲームプレイヤーの行動が、一次的現実の観点から見た時に「恥ずべきもの」であるのならば、それは少なくともゲームプレイヤーのだけの責任ではない。それはゲームのインセンティヴ構造を設計したゲーム制作者との共犯である。 一次的現実から切断された環境のなかで行為するとき、プレイヤーはゲームの構造が要請する欲望の代理人でもある。RPGで敵を殺したがっているのは、プレイヤーなのか、ゲームの構造なのか。明確な区別は、ふつうできない。 ここでは、プレイヤーの欲望や行為は日常の利得から切断されている。この切断を「利得の切断」と呼んでおこう。 この利得の切断が生じている状況下において、プレイヤーが殺人をしたり、他国を征服したり、ものを盗んだりしても、プレイヤーにとっては特殊な行為をしたという感覚にはならないことのほうが多いだろう。
主体の切断
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝 第二章 ミニ四駆(4)「もうひとりのディカプリオ、もうひとつのプリウス」
2018-11-06 07:00
デザイナーの池田明季哉さんによる連載『"kakkoii"の誕生ーー世紀末ボーイズトイ列伝』。『レッツ&ゴー』における〈成熟〉の失敗は、乗り物を通じた暴力の否定であり、ひいては自動車にまつわる〈男性性〉の拒否を意味します。90年代末に描かれたその想像力は、トヨタ・プリウスに象徴される、00年代の世界的な自動車のパラダイム転換を予見していました。
バトルレースと『レッツ&ゴー』の倫理
『レッツ&ゴー』におけるミニ四駆の美学は、成熟を拒否している──この結論は、20世紀末ボーイズトイを通じて新しい成熟のイメージを発見しようとする本連載の趣旨からすると、奇妙に思えるだろう。しかしここで考えたいのは、こしたてつひろが、なぜ理想的な成熟を描けなかったのか──いや、描かなかったのか、ということだ。
その理由は、『レッツ&ゴー』シリーズにおける敵の描写によく表れている。シリーズを通じて烈や豪(あるいは烈矢や豪樹)の前に立ちはだかる敵は交代していくのだが、勝利のためならばマシンを破壊しても構わないという思想を持っている点では執拗なまでに一貫している。
こうした思想、およびこれに基づくマシンへの直接攻撃を容認するレギュレーションには、アニメ化された際に「バトルレース」という名前が与えられている。通常のレースにバトルレースを持ち込む、あるいはバトルレースそのものを主流のレギュレーションとして推進しようとする敵との緊張がドラマの軸に据えられている。敵が勝利という結果にこだわることは、重要なレース結果の不自然なまでに軽い描写と表裏一体である。『レッツ&ゴー』において、レースにおける勝利という社会的価値を通じて男性性を追求し自己を実現しようとすること──ミニ四駆と社会を接続することで「大人」を目指す営みは、暴力や破壊と深く結びついている。
▲「WGP編」に登場するイタリア代表のマシン、ディオスパーダ。刃物が仕込まれており、レース相手を切り裂く(むろん反則である)。 『爆走兄弟!!レッツ&ゴー(12)』p36
▲「MAX編」に登場する敵、ボルゾイ。バトルレースを是とするボルゾイレーシングスクールを主宰する。 『爆走兄弟レッツ&ゴーMAX(1)』p96
だから『リターンレーサーズ』において、F1レーサーとなった豪が危険なドライビングを繰り返していることは、解決されるべき重大な問題として描かれる。これはレースを扱った物語作品において、むしろ例外的な価値観といっていいだろう。勇気を持ってリスクを取り、勝利を掴もうとする精神は、それが意図的に事故を引き起こそうとする悪意あるものでない限り、肯定的に描かれることの方が多いからだ。たとえば先代の『四駆郎』だけを見ても、四駆郎たちは命がけのレースに自ら身を投じていったし、その源流たる自動車文化を象徴する源駆郎が参加していたのは、死のレースといわれる「地獄ラリー」だった。成長した四駆郎もまた、こうした過酷なレースに身を投じていったことが示唆されていた。いうなれば四駆郎たちや豪は、成熟を目指した結果、バトルレースに身を投じてしまっているのだ。
▲クラッシュしたときのパーツは、武勇伝を語るものとしてではなく「いましめに」飾られている。 『爆走兄弟レッツ&ゴー!!ReturnRacers!!(1)』p16
『レッツ&ゴー』は、確かに成熟を拒否している。しかしこしたてつひろがバトルレースを徹底して悪として描き、自らの生命を危険にさらし続ける豪の成熟のあり方を露悪的に描いたことは、乗り物を通じて社会と短絡した主体が引き起こす暴力を容認しないという倫理的な態度だったといっていい。ここでこしたてつひろが拒否したものは成熟そのものではなく、『四駆郎』までは引き継がれていた、20世紀の自動車文化における男性性のイメージなのだ。
ミニ四駆が「魂を持った乗り物」という中間的な存在として描かれた理由も、そこにある。自動車は、工業技術によって身体を拡張し、主体にレバレッジをかけて社会に接続する。その拡張感は、自動車を直接操作しているという感覚に支えられたものだ。こしたてつひろはミニ四駆が操作できないことを肯定的に捉え、ここに「魂」という想像力を介在させて操作を間接化することでいったん主体から切断した。そしてさらにミニ四駆をスポーツとして社会からも切断することで、主体と社会の間で機能する緩衝としての役割を与えた。
こしたてつひろの慧眼は、比喩的にいうなら、ミニ四駆が「交通事故を起こさない自動車」であることを発見した点にある。言い換えれば、進歩を目指しながらも暴力と結びつかない形で、政治的に正しく男性性を追求する可能性を、ミニ四駆という「おもちゃ」の中に見いだしたのだ。
もうひとつのトヨタ・プリウス
20世紀的な男性文化・自動車文化の批判的継承として、こしたてつひろが『レッツ&ゴー』で描いた想像力は先見的かつ重要だ。
実は自動車の文化史においてこれとちょうど相似形を描いている出来事がある。それはレオナルド・ディカプリオによるトヨタ・プリウスの再発見だ。
▲レオナルド・ディカプリオ主演『ウルフ・オブ・ウォールストリート』
▲トヨタ・プリウス。写真は2003年から2011年にかけて生産された二代目。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
アッシュ・リンクスは、 それでも生き延びるべきだった――『海街diary』 (PLANETSアーカイブス)
2018-11-05 07:00
今朝のPLANETSアーカイブスは、宇野常寛による『海街diary』と吉田秋生論です。本作で円熟の極みに達しつつある吉田秋生のここまでの作家性の変遷と、初期作『河よりも長くゆるやかに』などに見られた「もうひとつの成熟の可能性」を読み解きます。(初出:『ダ・ヴィンチ』2014年9月号)
▲吉田秋生『海街diary(6) 四月になれば彼女は』
吉田秋生の『海街diary』の最新刊(今年の7月に発売された『四月になれば彼女は』)を読んでまた鎌倉に行こうと思った。以前にもこの連載で取り上げたことがあるのだけど、僕は鎌倉が好きで年に何度も足を運ぶ。たいていはよく晴れた日に、思いつきで出かける。こういったことができるのが自営業の特権だ。半日かけて、由比ヶ浜から極楽寺にかけてのゾーンをぶらぶらして、途中、目についたお店に入って休憩する。そして必ずお土産に釜揚げのシラスを買って帰るのだ。観光ガイドには一時期、このマンガの舞台になった場所を紹介する「すずちゃんの鎌倉さんぽ」を使っていた。映画やドラマのロケ地めぐりが趣味の僕がどこかの街を気に入るときはたいていこういったミーハーなきっかけだ。
そんなミーハーな人間が、こんなことを言うといわゆる「鎌倉通」の人たちに怒られるかもしれないが、僕は実際の鎌倉は吉田の描くそれよりも、つまり昔ながらの人情下町コミュニティが残っていて、都心部とは違った時間のゆっくり流れるスローフード的な空間よりも、もう少し猥雑でスノッブな街だと思う。一年中昭和の日本人が観光客として群れを成しているし、夏のビーチはファミリー、カップルそしてエグザイル系のお兄さんたちで溢れている。こういっては失礼だが彼らはスローフードのスの字もない人々だけれども、こうした人々がいるからこそこの街に僕のような人間にも居場所があるのだと思っている。
だから正直に告白すれば、僕はこの『海街diary』に出てくる鎌倉にはちょっと住めないな、と思っている。もちろん、それは否定的な意味ではない。この作品に出てくる鎌倉はそういった猥雑さを排したことで、とてつもなく優しく、そして強靭な磁場を備えた空間として成立している。そしてその淀みのなさに、自分はちょっと住めないな、と憧れるのだ。
吉田秋生という作家を語るときは、かつてこの作家が用いた「川」というモチーフを中心に考えるとその変遷がクリアに浮かび上がってくる。
かつての吉田秋生は当時のアメリカン・ポップカルチャーの絶大な影響のもと、戦後日本的「成熟と喪失」を正しく引き受けた作家だった、と言えるだろう。同時代の少年マンガが戦後日本的未成熟の肯定に開き直り(反復される強敵との戦いで成熟を隠蔽しながら、実は幼児的遊戯を継続し続けるバトルマンガと、終わりなき日常をてらいなく描き続けるラブコメマンガ)、先行する先鋭的な少女マンガ(24年組等)がむしろヨーロッパ的意匠とファンタジーへの傾倒で戦後少女文化ならではの深化を見せていったのとは対照的に、吉田は同時代の少女マンガ家としては珍しく戦後日本人男性の「成熟と喪失」の問題を正面から引き受けていたのだ。
初期の吉田作品において少年は(たとえ舞台がアメリカであってもどこか戦後日本的な屈折を抱えた、マチズモを引き受けることができない主人公の少年は)思春期にアイロニーを、偽善/偽悪を、社会の淀みを受け入れることでイノセンスを失う。そしてそのイノセンスと引き換えに彼は成熟を遂げていく。
たとえばこの時期の吉田の代表作『河よりも長くゆるやかに』は80年代初頭の基地の街(福生)を舞台にした青春群像劇だ。主人公の男子高校生・季邦(としくに)は父親の浮気が原因で両親が離婚し、病死した母親の代わりに季邦を育てる姉は進学を断念して水商売をしながらアメリカ兵と付き合っている。そして季邦もまた、生活費と進学資金のためにアメリカ兵への売春あっせんや麻薬密売に手を染めている。しかしそんな季邦もまた、昼間はバカでお気軽で、性欲と食欲を持て余したいち男子高校生であり、物語はそんな季邦とその周囲の人々の日常のドラマを、過酷なものと気楽な他愛もないものを織り交ぜながら描いていく。
『河よりも長くゆるやかに』の後半、アンチクライマックス的にさり気なく描かれる主人公とその友人の会話に前述の世界観は凝縮されている。
その場面で、主人公の季邦とその友人の深雪は橋の上から川を眺めている。深雪は問う。この川は、上流は流れが早くて水も綺麗だけど、海に近づくにつれて汚れていく。でも川幅も広まって、流れはゆるやかになっていく。どっちがいいか、と。そのとき季邦ははっきりとは答えない。しかし彼の回答が後者であることはタイトルからしても明らかだ。
しかし、吉田はその後長期連載を開始した『BANANA FISH』で転向する。季邦的な河口の広く深くゆるやかな流れから、同作のヒーローであるアッシュ・リンクス的な上流の澄んだ、清く速い流れに転向したのだ。リバー・フェニックスをモデルに造形されたアッシュは、絶対的な美貌と頭脳と運動神経を持つ完璧超人として僕たちの前に現れた。したがって彼には成熟の必要はなく、物語はその心の隙間(トラウマ)を埋めてくれる承認(ボーイズ・ラブ的な関係性)をめぐるものに終始し、そして承認を獲得すると同時に若くして死んでいった。彼は喪失を経て成熟して大人になることはなかったのだ。
ある意味、吉田はここで近代的な人間の成熟と喪失の物語を諦め、ポストモダン的な人間(キャラクター)の承認の物語にシフトしたという言い方もできるだろう。
絵柄的にも、『河よりも長くゆるやかに』『吉祥天女』から続く大友克洋的な(劇画的な)絵柄から次第にシャープなボーイズ・ラブ風の絵柄に変化していっている。この絵柄の変化は同時に前述の人間観の変化でもある。物語当初は象徴的な「父」であるゴルツィネへの復讐譚、つまり少年の成長物語のひな形である「父殺し」の物語から、相手役の少年・英二を対象としたボーイズ・ラブ的な承認獲得の物語への移行とこの絵柄の変化はほぼ符合している。こうして吉田は変化していったのだ。
そして『BANANA FISH』の続編的性格を持つ『YASHA─夜叉─』『イヴの眠り』を経て吉田が開始した『海街diary』は、その題名が示す通り上流の速く清い流れでもなく、河口のゆるやかに淀んだ流れでもなく、まさに満ちて引く反復運動があるだけの「海」の物語として登場した。吉田の本作におけるテーマはかつての成熟ではなく、「死」もしくは「老い」だ。長くゆるやかな河口すらも突破して、海に出たあとの物語が、ここには描かれているのだ。
同作の主人公は鎌倉に住む四姉妹だ。かつての季邦のように壊れた家庭をもつ彼女たちだが、(四女のすずをのぞけば)思春期を既に通過しており成熟と喪失をめぐる葛藤は昇華してしまっている。むしろ彼女たちが直面しているのは、既に海に出た世界でいかに老い、死んでいくのかという問いだ。実際に、本作はすずを中心とした青春群像劇を基調にしながらも、常に死の影がまとわりついている。たとえばすずが所属するサッカーチームのエースストライカーの少年は小児がんで足を切断し、いきつけの食堂のおばちゃんもあっけなく病死する。そしてその後の遺産をめぐるトラブルに主人公たちも巻き込まれていく。これらのエピソードで描かれているのは取りかえせない人生の選択を、その過ちも含めていかに引き受けるかという問いであり、絶対に許せない存在や出来事とどう折り合っていくのかという問いだ。言いかえれば「これから」の人生よりも「これまで」の人生のほうが(少なくとも可能性のレベルでは)長くなってしまった人々が、その生の終わりまでの時間をいかに受け入れるのか、という問いだと言える。
看護師を務める四姉妹の長女は劇中でホスピスに異動になるが、この設定は本作それ自体の性格を示しているといえるだろう。吉田にとって海は、海の街は言葉の最良の意味において、人生の終わりと向き合うこと、可能性の限界と向き合ってそれを受け入れることに挑戦する場所、つまりホスピスなのだ。
同作には繰り返し「絶対に許せない人」──生前には何の愛情も示さず遺産だけをむしり取ろうとする親戚──や、理不尽すぎる運命──夢をつかみかけたときに襲い、すべてを奪い去る病魔──が繰り返し登場する。これは吉田が本作で、こうした個人の力ではどうにも抗えない世界の欠損とどう向き合うか、という問題に正面から対峙していることを意味する。思春期であればそれは、運命を跳ね返す可能性と、欠落を受け入れる成熟でそれを乗り越えることができる。しかし、終わりが近づいた人々にはそれはない。死ぬ間際まで納得できないような欠落と、人々はどう向き合うのか。それが「海」の問題なのだ。そして吉田は、いまのところ、こうした欠落と対峙し続け、ぎりぎりまでその痛みを緩和するまさにホスピス的な優しい「強さ」を、静かに提示し続けているように思える。決して大上段に構えない、静かな語り口──まるで毎日の食事を一食ずつ大切に経ていくような確かさ──をもって、しかし確信をもって、この優しい「強さ」を提示する吉田の姿勢と手腕を、僕は本当に貴重に思う。吉田秋生という作家は円熟の極みを迎えつつある、と断言してもいいだろう。
しかし──僕はこの作家が完成に近づくからこそ、鎌倉の海が完成に近づくからこそ、そこで吉田が選び取らなかったもうひとつの海の可能性について考えてしまう。
かつて福生(『河よりも長くゆるやかに』)を流れていた川はたぶん、あの鎌倉の海には(少なくとも直接は)つながっていない。なぜならば前述したように季邦たちの眺めていた川は一度「逆流」し、清く澄んだ清流に浄化されているからだ。その結果、『河よりも長くゆるやかに』の福生と『海街diary』の鎌倉は、つながっていない。いや、もちろん別の時代に描かれた別の作品なのでつながっていないのは当たり前なのだが、それ以上にこのふたつの街はその世界観のレベルで異なっている。それは何か。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
宇野常寛 NewsX vol.5 ゲスト:児玉健 「遊ぶことで、大人はもっと自由になる」【毎週金曜配信】
2018-11-02 07:00
宇野常寛が火曜日のキャスターを担当する番組「NewsX」(dTVチャンネル・ひかりTVチャンネル+にて放送中)の書き起こしをお届けします。10月2日に放送されたvol.5のテーマは「遊ぶことで、大人はもっと自由になる」。けん玉パフォーマー・人狼ゲームマスターの児玉健さんをゲストに迎えて、現代の大人にとっての「遊び」はどうあるべきなのかを語り合います。(構成:籔和馬)
NewsX vol.5「遊ぶことで、大人はもっと自由になる」2018年10月2日放送ゲスト:児玉健(けん玉パフォーマー・人狼ゲームマスター) アシスタント:加藤るみ(タレント) アーカイブ動画はこちら
宇野常寛の担当する「NewsX」火曜日は毎週22:00より、dTVチャンネル、ひかりTVチャンネル+で生放送中です。アーカイブ動画は、「PLANETSチャンネル」「PLANETS CLUB」でも視聴できます。ご入会方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。 ・PLANETSチャンネル ・PLANETS CLUB
「遊び」に目覚めたのは30歳を過ぎてから
加藤 NewsX火曜日、今日のゲストは、けん玉パフォーマー、人狼ゲームマスターの児玉健さんです。 児玉さんがけん玉をはじめたのは、30歳のときなんですよね。
児玉 僕は29歳まで普通に不動産屋さんでサラリーマンとして営業の仕事をしていたので。その頃、リーマンショックがあり、外部の力でサラリーマンを一旦辞めることになって、そのあときに遊びに目覚めました。けん玉も人狼も30歳からはじめたんです。
宇野 子どもの頃に「けん玉のタケちゃん」とか言われていたようなことではないんですね。
児玉 全然そんなことないですよ。小学生の頃に、けん玉を少しはやったことがあるけど、玉が剣先に刺さるか刺さらないかくらいのとこで止めちゃった。みなさんと一緒です。
加藤 児玉さんについて、これから深掘りしていきたいんですが、宇野さんから児玉さんの紹介をお願いできますか?
宇野 児玉さんに番組冒頭でけん玉のパフォーマンスを見せてもらったんだけど、けん玉だけをやっている人じゃないんですよ。今のメインの仕事は、けん玉のパフォーマンスと、あとは人狼という推理ゲーム。渋谷にある人狼をみんなで遊ぶ部屋「人狼ルーム」を運営しながら、日本を代表する人狼プレイヤーとして活躍している人なんです。児玉さんは人狼とけん玉を中心にいろんな遊びを通して「現代における大人の遊びは何か?」ということを研究していて、それをコンサル的にいろんな集団に教えたりとか、プロデュースしたりとか、そういった活動をしている人なんですよね。
加藤 今日のトークのテーマは「遊ぶことで、大人はもっと自由になる」です。宇野さんは児玉さんの存在をどのようにして知ったんですか?
宇野 僕が児玉さんと出会ったのは、実はけん玉ではなくて、人狼がきっかけなんですよ。僕の知り合いである、ゲーム作家のイシイジロウさんが「宇野さんが人狼をやったら、すごく面白いんじゃないか?」ということを考えてくれて、児玉さんが運営している渋谷の人狼ルームに誘われて行ったんですよ。人狼ルームは外見的には何の変哲もないマンションの一室なんだけど、夜の7〜8時になると、いろんな職業に就いている人が続々と集まって、11時ぐらいまで、ひたすら人狼をやっているんだよね。あの感覚がすごく好きで。みんなで駄菓子屋に連れ立って行って、ガシャポンをやって、その足でかくれんぼしたりしていた小学校の頃の体験に似たような感覚で遊ぶということが、大人になってもありえるんだということが、僕はすごく感動的でした。しかも、この人はそれを仕事にしているわけ。人々に遊びを提案して、それをプロデュースすることがすごく素敵だなと思い、今日ここにお呼びしました。
児玉 ありがとうございます。
「遊び人」を職業にして生きていく
加藤 今日も三つのキーワードでトークしていきます。まず一つ目のキーワードは「職業『遊び人』とは」です。
宇野 もともとただのサラリーマンだった人が、どういう経緯で職業『遊び人』みたいな、遊びのプロになっていったのか、そして、遊びのプロとは具体的には何なのかを、紹介のついでに深掘りしていくところから始めたいと思います。
児玉 遊び人というと、チャラチャラしている人も指すじゃないですか。でも、僕は真面目な遊び人なんですよ。僕は創り出すというよりは、遊びというものを広げるほうだと思っているんです。 サラリーマンを辞めると、転職をしないといけないじゃないですか。転職を考えたときに、不動産じゃない業界にいこうと思ったんですよ。
宇野 違う業界に行きたかったんですね。
児玉 そのときに、娯楽産業とか、娯楽業界に行きたいと思ったんです。僕が大学生のときに、食玩がものすごく増えた時期で、ずっとおもちゃを買い漁っていたんです。
宇野 食玩とは具体的に何を買い漁っていたんですか?
児玉 ベアブリックのようなメディコム・トイさんのおもちゃが好きでしたね。会社を辞めたとき、俺はメディコムトイとか行きたいなとか思っていたんですよ。この機会に、好きだったものをなんとか仕事にできないかなと最初に思ったんです。そのときに、娯楽業界のことををいっぱい調べたんですよ。そしたら、もちろん企業ではあるので、どこの企業も自分が思っているよりいろんなことをやっていて、いろんな企業を見てまわって、しっくりこなかったんで、自分でもうやっちゃおうとなった。 そして、遊びをいろいろ研究していたときに、「人狼ゲーム」と「けん玉」に出会った。この二つがピンときて、一旦これに没頭してみようと。それにどちらも、もともとマイナーなものだったので、これを世間に違うかたちで見せて、それをやっていこうと。 フリーター期間が1年ぐらいあったので、30歳になって1年間仕事をしていなかったんですよ。30歳の1年は、20歳の1年より結構強いですよ。切羽も詰まっているし、社会人経験があるから、そこそこ動きも軽い。
あえて失敗して見せることがパフォーマンスになる
宇野 転職を意識して、遊び産業を研究しているなかで、結果的にけん玉と人狼に出会っていったと。ちなみに、なんでけん玉だったんですか?
児玉 本当に偶然です。おもちゃの勉強をする学校があったんですよ。実は世の中には、おもちゃコンサルタントという資格がありまして。NPOが出している国家資格とかではもちろんないんですけど、僕は暇だったし、最低限動かなきゃみたいな気持ちがあったので、飛びつきますよね。 それで、おもちゃコンサルタントを取りに行ったときに、同じクラスに今の相方(飯島広紀さん)がいたんですよ。彼はけん玉がうまかったんですよ。遊びを勉強しているし、けん玉もちょっとぐらい上手かったら、役に立つかもなと思って、彼に教えてもらっていたら、ハマって。そこから、「ちょっとパフォーマンスとかしてみない?」という話になり、いろいろやりだしたというのが始まりですね。
宇野 それが今のパフォーマンスコンビの「ZOOMADANKE(ず〜まだんけ)」になっていくわけなんですね。
児玉 相方は10歳下だったんで、20歳の大学生でした。その子に、30歳のおっさんが一緒にパフォーマンスをやろうぜと(笑)。
宇野 最初パフォーマンスは仕事としてやろうと思ったんですか?
児玉 当時、僕は30歳なので、仕事をしなきゃいけないというのは頭のどこかにありますよね。なので、まずはビジネスとして頑張ってみよう、ダメだったら趣味にしよう、という感覚だったんですね。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
本日21:00から放送!宇野常寛の〈木曜解放区 〉 2018.11.1
2018-11-01 10:00本日21:00からは、宇野常寛の〈木曜解放区 〉
21:00から、宇野常寛の〈木曜放区 〉生放送です!〈木曜解放区〉は、評論家の宇野常寛が政治からサブカルチャーまで、既存のメディアでは物足りない、欲張りな視聴者のために思う存分語り尽くす番組です。今夜の放送もお見逃しなく!
★★今夜のラインナップ★★メールテーマ「本屋」アシナビコーナー「井本光俊、世界を語る」and more…今夜の放送もお見逃しなく!
▼放送情報放送日時:本日11月1日(木)21:00〜22:45☆☆放送URLはこちら☆☆
▼出演者
ナビゲーター:宇野常寛アシスタントナビ:井本光俊(編集者)
▼ハッシュタグ
Twitterのハッシュタグは「#木曜解放区」です。
▼おたより募集中!
番組では、皆さんからのおたよりを募集しています。番組へのご意見・ご感想、宇野に聞いてみたいこと、お悩み相談、近況報告まで、なんでもお寄せくださ -
成馬零一 テレビドラマクロニクル(1995→2010) 堤幸彦(6)『池袋ウエストゲートパーク』後編ーー堤、クドカン、窪塚洋介。それぞれのIWGP
2018-11-01 07:00
ドラマ評論家の成馬零一さんが、90年代から00年代のテレビドラマを論じる『テレビドラマクロニクル(1995→2010)』。今回は『池袋ウエストゲートパーク』論の後編です。ドラマ版と原作小説を比較しながら、作品に関わった3人のクリエイター、石田衣良と堤幸彦と宮藤官九郎の影響を検討。さらに本作以降、窪塚洋介が背負うことになった時代性について考察します。
石田衣良からみた『IWGP』
次に原作小説とドラマのストーリーの違いについて考察したい。 石田衣良はシナリオ版『池袋ウエストゲートパーク』(角川書店)の解説で、小説とドラマの違いについてこう書いている。
メディアが違うから、原作(寒色系シリアス)とドラマ(暖色系コメディ)のトーンは違うけれど、両者は最も大切な部分で共通していたとぼくは思う。 それは圧倒的なスピード感とキャラクターの立体感だ(もうひとついうなら池袋という現実の街のライブ感)。ぼくも作家なので、文体にはかなり気をつかう。IWGPでなにを一番大切にしているかというと、人物の描写と文章のスピード感なのだ。 それを宮藤さんは即興性豊かな組み立てと特異なコメディセンス(その場の思いつきともいう、だがなんと切れ味のいい思いつきか)でしっかりと再現してしまった。(「風を切ってフルスイング 石田衣良」:『宮藤官九郎脚本 池袋ウエストゲートパーク』著:宮藤官九郎・角川書店より)
石田はドラマ化に際して「小説とテレビではメディアが違います。原作に気兼ねなどしなくていいから、とにかく思い切りフルスイングしてください。そしたら空振りだって納得できますから」(同書)と磯山に伝えたそうだが、ドラマ版『池袋』と小説を比べると、物語の流れは大筋では同じだが、細部が微妙な変更が施されており、その改変の仕方が見事だというのが当時の印象だった。
のちに数々のオリジナルドラマを手がけることになる宮藤だが、本作は原作モノだったこともあり、作家性に関してはまだ未知数だったが、まずは優秀なアレンジャーとして、その才能は大きく印象づけたと言えよう。
「ダサさ」をまとうことで見えてくるもの
原作の改変ポイントは多数あるが、中でも大きく変わったのは主人公のマコトの造形だろう。小説はマコトの一人称で進むハードボイルド小説の構造となっている。台詞もカッコよくてクールだ。 それをドラマ版では工業高校上がりの馬鹿なヤンキーで素人童貞という側面を強く打ち出している。
原作小説の第一巻が発売されたのは1998年、ドラマ化されたのは2年後だが、最先端の都市の風俗(ストリートカルチャー)というものは、活字になった時点でどんどん古びてしまう。 小説の『池袋』もその側面は強く、情報の鮮度という意味ではドラマ版は圧倒的に不利である。また、小説では成立したカッコいい語りも生身の人間が喋ったら台無しになることも多い。仮に小説をそのまま映像化していたら目も当てられない作品となっていただろう。 だが、宮藤の脚本はカッコよく書かれていた石田衣良の世界を少し斜めから見て、あえてかっこ悪く――宮藤がドラマ内で用いる言葉で言うなら「ダサく」――することで、物語を読み替えて言った。
それはそのまま、トレンディドラマで描かれていたような匿名性の高いおしゃれな街としての東京ではなく、地元(ジモト)としての池袋という、具体的な土地の持つ固有性を打ち出していくという作業だった。 宮藤の脚本は脚本の構成はごちゃごちゃしているが、一つ一つが具体的だ。会話の中には固有名詞がたくさん登場し、その延長で、実在するテレビ番組や芸能人が登場する。 権利関係の処理の問題もあってか、実在する商品名や固有名詞を出すことをためらうドラマは今も少なくないが、固有名詞が具体的であればあるほど、そこに描かれている人間たちの実在感は増していく。すべてのものに固有の名前があり、ワイドショーや雑誌で語られる記号としての東京や女子高生やカラーギャングではなく、くだもの屋のマコトや風呂屋のタカシといった、固有名を取り戻すことで、流行り廃りの激しい風俗の根底にある地に足の付いた感覚を取り戻したことこそが、テレビドラマにおける宮藤の最大の功績だろう。
それは人間関係の描き方にも現れている。特に画期的だったのはマコトの母親・リツコ(森下愛子)の描き方だ。 原作小説では、ほとんど描写されてないリツコのディテールはコミカルではあるが、シングルマザーながらにマコトを育ててきた母親としての優しさやたくましさが描かれていた。
のちに織田裕二主演の連続ドラマ『ロケット・ボーイ』(フジテレビ系)の脚本を宮藤に依頼するプロデューサーの高井一郎は『池袋』の脚本について「よく見ると普遍的な親子愛や友情が隠れて描かれていますよね」(「特集・宮藤官九郎」『クイックジャパンvol.35(太田出版)』より)と語っている。 小ネタで彩られたサブカルドラマとして語られがちな宮藤の作風の奥底にある本質を高井は早くから見抜いていた。 それは一言で言えば家族も含めた共同体(仲間)に対する信頼である。 80年代のトレンディドラマ以降、テレビドラマで家族が描かれる機会は年々減っていた。橋田壽賀子・脚本の『渡る世間は鬼ばかり』(TBS系)を例外とすれば、家庭内暴力や不倫といったネガティブな形でしか家族は描かれなくなっていた。 『未成年』(TBS系)等の野島伸司のドラマは、その反動もあってか、家族再生を試みるのだが、そこで描かれたのは血の繋がらない中間共同体的なもの、『池袋』で言うとGボーイズ的な共同体だった。そういった共同体は反社会的な性質を帯びて、やがては暴走して崩壊する。それは学生運動末期の連合赤軍事件やオウム真理教の地下鉄サリン事件などに連なる、日本の疑似家族共同体の失敗の歴史の反復とも言えよう。 対して宮藤が面白いのは、一方で疑似家族的な仲間のつながりを描きながら、対立軸として血縁関係にある親子を描かないところだ。むしろ、親子も友達のように付き合ってしまうことで、今まで重々しいものだった家族という概念自体を軽いものとして扱っていたのである。
原作小説とドラマ版の大きな違い
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
<前へ
3 / 3