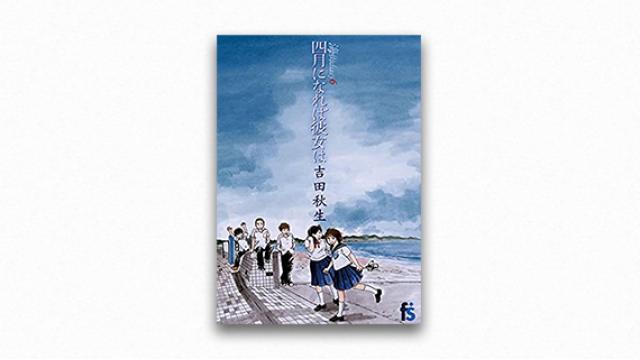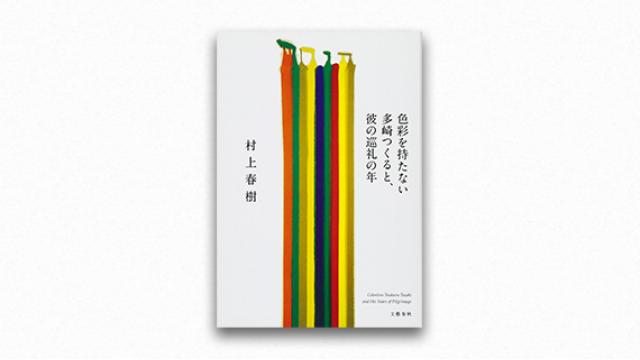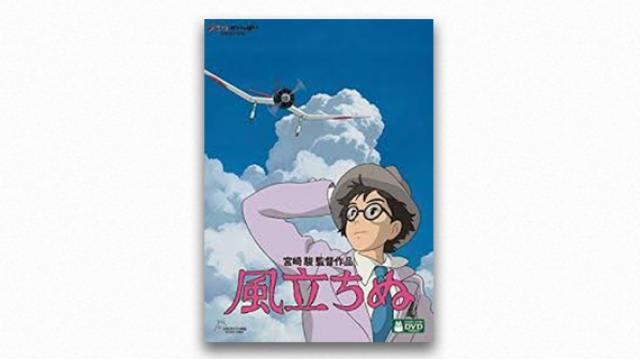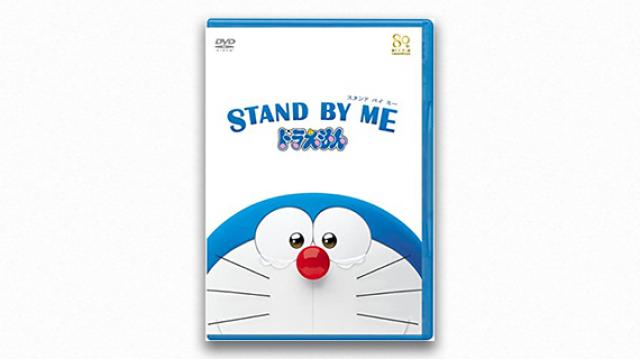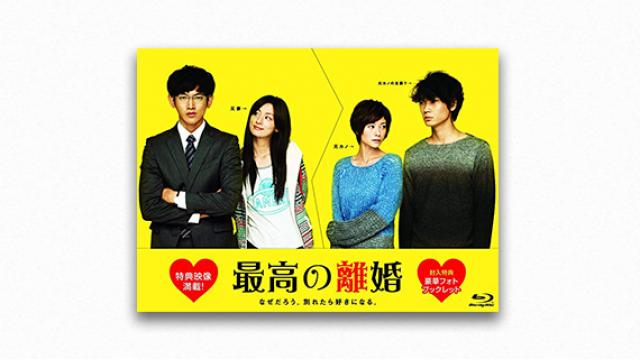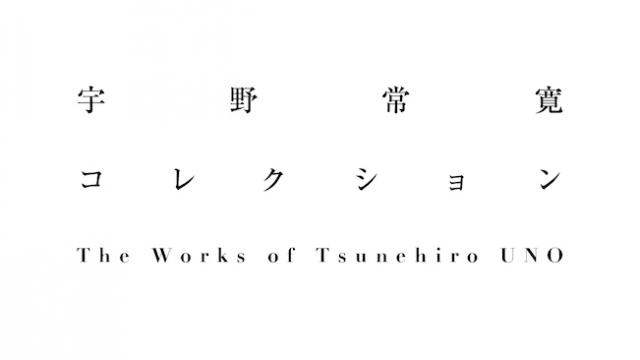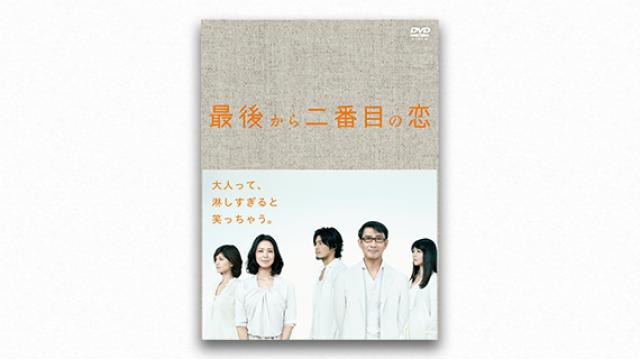-
我々の身体を"マリオ"化する企て――チームラボ猪子の日本的想像力への介入 宇野常寛コレクション vol.19【毎週月曜配信】
2020-04-27 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回は2014年に開催された「チームラボと佐賀 巡る!巡り巡って巡る展」を取り上げます。海外ではすでに新世代のデジタルアートの旗手として大きな注目を浴びていながらも、チームラボにとって日本国内ではほぼ初めてだった大規模な展覧会。宇野にとっても彼らのアートと系統的に向き合っていくターニングポイントとなった異例ずくめの佐賀展は、情報技術と日本的想像力との関係を、どのように更新したのでしょうか? ※本記事は「楽器と武器だけが人を殺すことができる」(メディアファクトリー 2014年)に収録された内容の再録です。
※チームラボ代表・猪子寿之さんと宇野の対談を収録した「人類を前に進めたい チームラボと境界のない世界」(PLANETS刊)好評発売中です!詳細・ご購入はこちらから。
「超楽しいよ、佐賀」「佐賀、ハンパないよマジで」「福岡から電車で一時間しないよ。マジすぐだから」 打ち合わせにならなかった。 その日僕は事務所のスタッフと一緒に水道橋のチームラボに来ていた。チームラボとは猪子寿之が代表をつとめる情報技術のスペシャリストたちのチームで、近年はデジタルアート作品を数多く発表している。主催の猪子が掲げるコンセプトは情報技術による日本的な想像力の再解釈だ。西欧的なパースペクティブとは異なる日本画の空間把握の論理を現代の情報技術と組み合わせることで、猪子はユニークな視覚体験を提供するデジタルアートを多数産み出してきた。
僕はいま、彼らチームラボと2020年の東京オリンピックの開催計画を練っている。ほうっておけば高齢国家・日本が「あの頃は良かった」とものづくりとテレビが象徴する戦後日本を懐かしむだけのつまらないオリンピックが待っている。そこで、僕はいま仲間たちと若い世代が考えるあたらしいオリンピック・パラリンピックの企画を考えて、僕の雑誌(PLANETS)で発表しようとしているのだ。僕たちの考えではテレビアナウンサーが感動の押し売り的文句を連呼し、「同じ日本人だから」応援されることをマスメディアを通じて強要されるオリンピックの役目はもう、思想的にもテクノロジー的にも終わっている。僕たちが考えているのは最新の情報技術を背景にした、あたらしい個と公のつながりを提案するオリンピックだ。開会式の演出からメディア中継にいたるまで、実現可能な、そしてワクワクするプランを提案すべく日々議論している。だからこの日もそんな議論が行われるはずだったのだが、猪子の口から出るのはいつまで経っても「佐賀」の話題だった。
そう、その日(3月10日)佐賀県ではチームラボの展覧会「チームラボと佐賀 巡る!巡り巡って巡る展」が開催中だった。チームラボの評価はむしろシンガポール、台湾などアジア圏のアート市場で高く、国内での大規模な展覧会は今回が初めてのものとなる。今回の展示は佐賀県内の4ヶ所にも及ぶ施設にまたがる大規模なものだが、存命の、しかも弱冠36歳の若いアーティストの展示を県が主催するのは異例のことだ。この異例の開催については県庁内でもさまざまな議論が交わされたようだが、開催後は予想外の好評と来場者数の伸びに湧いているという。その日猪子は半分冗談まじりに、あと二週間足らずで終わるこの展覧会を僕に観ろ、と繰り返した。
たしかに一度、猪子の作品をまとめてじっくりと観てみたいという気持ちは以前からあった。しかし、観に行くとしたらその週末に弾丸ツアーを敢行するしかない。さすがにその展開はないだろう、と思っていた僕を動かしたのは何気ない猪子の一言だった。「会期延長しようぜ1ヶ月くらい。なら行ける」と口走った僕に、猪子はこう言ったのだ。「宇野さん、俺と宇野さんの一番の違いはね。なんだかんだで宇野さんは夢を生きている。でも、俺は現実を生きているんだよ」と。もちろん、これは冗談だったのだと思う。でも、僕はこの何気ない一言に猪子寿之という作家の本質があるような気がしたのだ。そして、僕は気がついたら答えていた。「え、じゃあ、行っちゃおうかな。うん、行くわ」と。
ここで猪子という作家の掲げる「理論」を簡易に説明しよう。猪子曰く、西欧的なパースペクティブとは異なる日本画的な空間把握は現代の情報技術が産み出すサイバースペースと相性がいい。全体を見渡すことのできる超越点をもたないサイバースペースは日本画的な空間と同じ論理で記述されるものだ、と猪子は主張する。そして、多様なコミュニティが並行的に存在し得る点は多神教的な世界観に通じる。猪子はこのような理解から日本的なものを情報技術と結びつけ、たとえば日本画や絵巻物に描かれた空間をコンピューター上で再解釈したデジタルアート(アニメーション)を多数発表している。
その題材の選択からオリエンタリズムとの安易な結託と批判されがちな猪子だが、実際に国内の情報社会がガラパゴス的な発展を続けていること/そしてその輸出可能性が検討されていることひとつをとっても、猪子の問題設定のもつ射程はオリエンタリズムに留まるレベルのものではないのは明らかである。
さて、その上で以前から僕が指摘しているのはむしろ猪子のキャラクター的なものへの態度についてだ。 猪子が度々指摘する主観的な、多神教的な、アニミズム的な世界観は同時にキャラクターというインターフェイスを備えている。たとえば私たち日本人は本来「人工知能の夢」の結晶であるはずの「ロボット」を「乗り物」として再設定している(マジンガーZ、ガンダム、エヴァンゲリオン)。「初音ミク」もまた集合知をかりそめの身体に集約して、作品を世界に問うための装置だと言える。要するに私たちは、日本人は自分とは異なる何かに、ときには集団で憑依して社会にコミットする(「世間の空気」を「天皇の意思」と言い換える)という感覚を強く有しているのだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
フル・フロンタルこそ真の「可能性の獣」である『機動戦士ガンダムUC』宇野常寛コレクション vol.18【毎週月曜配信】
2020-04-20 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回取り上げるのは『機動戦士ガンダムUC』です。ファースト・ガンダム世代の作家・福井晴敏をストーリーテラーに迎え、架空歴史=宇宙世紀への本格的な改変・介入を、富野由悠季以外の作家がはじめて行い、富野批評的な側面を負うこととなった本作。主人公バナージやミネバといった新世代のニュータイプたちの成長劇として描かれたはずの物語の陰で、「説教リレー」に淫する中年世代の危うい本音とは? そして彼らが対峙する「悪役」フル・フロンタルが抱く、作者にも見過ごされた可能性とは? ※本記事は「楽器と武器だけが人を殺すことができる」(メディアファクトリー 2014年)に収録された内容の再録です。
今からさかのぼること33年前──1981年2月22日今やそこはまったく別の意味で「聖地」となりつつある新宿東口のスタジオ・アルタ前はアニメファンでごったがえしていたという。70年代末からのアニメブームは『宇宙戦艦ヤマト』などのヒット作を中心に、国内におけるアニメーションを児童向けのいわゆる「ジャリ番」から、大人まで楽しめるサブカルチャーの1ジャンルに押し上げていった。その流れの中核にあったのが、79年にテレビアニメ第一作が放映開始された『機動戦士ガンダム』だった。テレビでの本放送時は玩具の売り上げ不振等の理由からいわゆる「打ち切り」の憂き目を見た『ガンダム』だが、その革新的な世界観と重厚な物語などで折から形成されていたアニメファンのコミュニティで大きな支持を受け、アニメブームの主役となっていった。
そして加熱するファンコミュニティの空気に応えるかたちで『ガンダム』劇場版三部作の公開が決定され、その宣伝イベントして企画されたのがこの「アニメ新世紀宣言」だった。 「私たちは、アニメによって拓かれる私たちの時代とアニメ新世紀の幕開けをここに宣言する」壇上に立った富野喜幸(現:由悠季)はそう宣言した。『ガンダム』の生みの親として、今でこそ広く知られている富野だが当時はまだ知る人ぞ知る存在だった。この時期の富野の発言にはたびたび、自作を中心とするアニメを子供向けの低俗な娯楽としてではなく、独立した1つの文化ジャンルとして受け入れる若者たちの感性を、新世代の感性として肯定する内容が見られる。80年代の後半から富野はどちらかといえばサブカルチャーに耽溺し、情報社会に適応した若者を現代病の患者として否定的に言及することが多くなったので、現在の富野を知る読者はこうした発言を知るとむしろ驚くかもしれない。
さて、ここで注目したいのは『機動戦士ガンダム』の作中で登場する「ニュータイプ」という概念が、当時の新世代─アニメ新世紀宣言に賛同した若いファンたちの世代─と重ね合わされていたということだ。「ニュータイプ」とはファースト・ガンダムと呼ばれる初代『機動戦士ガンダム』の作中で、新兵のアムロがエースパイロットとしてわずか数カ月の間に急成長する根拠として与えられた設定である。それは人類が宇宙環境に適応することで発現する一種の超能力である。しかしそれはテレキネシスやテレポーテーションといったものではなく、極めて概念的で、抽象的な超能力で超認識力ともいうべきものだ。「ニュータイプ」に覚醒した人類は、地理や時間を超えて他の人間の存在を、それも言語を超えて無意識のレベルまで感じることができる。これは富野による極めて個性的な超能力設定だと言える。宇宙移民時代に人類が適応し始めたとき、その認識力がこのようなかたちで拡大していく、と考えた作家は古今東西他にいないはずだ。
そしてこの「ニュータイプ」という概念は、作品外のムーブメントと結果として重ね合わされることになった。後にメディアを賑わせる「新人類」の語源のひとつがこの「ニュータイプ」であるという説もあるが、おそらくは「新世紀宣言」が代表する当時のアニメブームが、前述のように世代論と深く結びついていたことがその説の背景にあると思われる。当時物語の中で描かれた「ニュータイプ」とは人類の革新であり、社会的にそれは「アニメ新世紀宣言」が掲げたように、新しいメディアに対応した新世代の感性の比喩だったのだ。
あれから約30年、当時ティーンだった「ニュータイプ」たちは今や40代の堂々たる中年になっている計算になる。その後『ガンダム』は81年から上映された劇場版三部作と、小中学生の間でのプラモデル商品の大ヒットを通じて社会現象化していった。そしてそれから30年、何度か下火になりながらも断続的に続編が発表され、その広がりはアニメに留まらず、プラモデル、ゲームなどにもおよび「ガンダム産業」と呼ばれる現在においては国内最大級のキャラクター・ビジネスを生み出すシリーズに成長している。
そのシリーズ展開は多岐にわたり、ティーンを対象とした続編が制作され続ける一方でファースト・ガンダムのファン層をターゲットにした中年向け作品も存在する。いや、正確にはこの「ガンダム産業」はこうした中高年市場に大きく依存していると言っても過言ではないだろう。
さて、そんな中高年向けガンダム市場の中核にここ数年君臨しているのが今回取り上げる『機動戦士ガンダムUC』である。本作はストーリーテラーに『終戦のローレライ』などの歴史SF、『亡国のイージス』などのポリティカルフィクションで知られる福井晴敏を迎え、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の続編的な物語を展開している。本作ではこれまで事実上の原作者であった富野のみが許されていたファースト・ガンダムから続く架空歴史=宇宙世紀への本格的な改変・介入をはじめて富野以外の作家が行い、作中にはブライト・ノア、カイ・シデンといったファースト・ガンダム以来の人気キャラクターが多数登場する。要するに高齢の原作者に代わり、40代のファーストガンダム世代の作家が「正史」を紡ぐ権利を手に入れた、と言えなくもないだろう。その結果、本作はファーストガンダム世代の「ファン代表」である福井による、富野批評的な側面を否応がなく負うことになった。そして、結論から述べれば本作をもって、富野由悠季が築き上げてきた「ガンダム」シリーズの、特に物語面での達成はほぼ引き継がれることなく失われてしまうであろうことがはっきりしたように思う。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
アッシュ・リンクスは、それでも生き延びるべきだった『海街diary』宇野常寛コレクション vol.17【毎週月曜配信】
2020-04-13 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回取り上げるのは、漫画『海街diary』です。戦後日本的な「成熟と喪失」の問題を正しく引き受けた作家・吉田秋生。鎌倉を舞台にした本作では、初期作のような「成熟と喪失」をめぐる葛藤は昇華され、いかに「老いと死」に向き合うかが静謐な筆致で描かれます。そんな作家としての円熟の一方で、もし初期の可能性のまま描き続けていたらあり得たかもしれない、もうひとつの「鎌倉の海」とは? ※本記事は「楽器と武器だけが人を殺すことができる」(メディアファクトリー 2014年)に収録された内容の再録です。
吉田秋生の『海街diary』の最新刊(今年の7月に発売された『四月になれば彼女は』)を読んでまた鎌倉に行こうと思った。以前にもこの連載で取り上げたことがあるのだけど、僕は鎌倉が好きで年に何度も足を運ぶ。たいていはよく晴れた日に、思いつきで出かける。こういったことができるのが自営業の特権だ。半日かけて、由比ヶ浜から極楽寺にかけてのゾーンをぶらぶらして、途中、目についたお店に入って休憩する。そして必ずお土産に釜揚げのシラスを買って帰るのだ。 観光ガイドには一時期、このマンガの舞台になった場所を紹介する『すずちゃんの鎌倉さんぽ』を使っていた。映画やドラマのロケ地めぐりが趣味の僕がどこかの街を気に入るときはたいていこういったミーハーなきっかけだ。
そんなミーハーな人間が、こんなことを言うといわゆる「鎌倉通」の人たちに怒られるかもしれないが、僕は実際の鎌倉は吉田の描くそれよりも、つまり昔ながらの人情下町コミュニティが残っていて、都心部とは違った時間のゆっくり流れるスローフード的な空間よりも、もう少し猥雑でスノッブな街だと思う。一年中昭和の日本人が環境役として群れを成しているし、夏のビーチはファミリー、カップルそしてエグザイル系のお兄さんたちで溢れている。こういっては失礼だが彼らはスローフードのスの字もない人々だけれども、こうした人々がいるからこそこの街に僕のような人間にも居場所があるのだと思っている。
だから正直に告白すれば、僕はこの『海街diary』に出てくる鎌倉にはちょっと住めないな、と思っている。もちろん、それは否定的な意味ではない。この作品に出てくる鎌倉はそういった猥雑さを排したことで、とてつもなく優しく、そして強靭な磁場を備えた空間として成立している。そしてその淀みのなさに、自分はちょっと住めないな、と憧れるのだ。
吉田秋生という作家を語るときは、かつてこの作家が用いた「川」というモチーフを中心に考えるとその変遷がクリアに浮かび上がってくる。
かつての吉田秋生は当時のアメリカン・ポップカルチャーの絶大な影響のもと、戦後日本的「成熟と喪失」を正しく引き受けた作家だった、と言えるだろう。同時代の少年マンガが戦後日本的未成熟の肯定に開き直り(反復される強敵との戦いで成熟を隠蔽しながら、実は幼児的遊戯を継続し続けるバトルマンガと、終わりなき日常をてらいなく描き続けるラブコメマンガ)、先行する先鋭的な少女マンガ(24年組等)がむしろヨーロッパ的意匠とファンタジーへの傾倒で戦後少女文化ならではの深化を見せていったのとは対照的に、吉田は同時代の少女マンガ家としては珍しく戦後日本人男性の「成熟と喪失」の問題を正面から引き受けていたのだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
あたらしい駅のかたちについて、彼は想像することもできない『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』宇野常寛コレクション vol.16【毎週月曜配信】
2020-04-06 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回取り上げるのは、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』です。ビッグ・ブラザーならぬ「リトル・ピープル」のモチーフで現代的な〈悪〉の問題を描きかけた前作『1Q84』に続き、大ベストセラーとなった本作。はたしてそこに、自らの問いに応える回答はあったのか? 国民作家・村上春樹の挑戦と挫折を通じて、戦後の文学的想像力の限界を考えます。 ※本記事は「楽器と武器だけが人を殺すことができる」(メディアファクトリー 2014年)に収録された内容の再録です。
〈文芸春秋は18日、村上春樹さんの新作小説「色彩を持たない多崎(たざき)つくると、彼の巡礼の年」を20万部増刷することを決め、累計発行部数が100万部に達したと発表した。 12日に発売されてから7日目。文芸春秋は「文芸作品では最速でのミリオン到達では」としている。村上さんの作品では前作「1Q84 BOOK3」が発売から12日目に100万部に到達している。「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」はネット書店での予約などが多かったことを受け、発売前から増刷を重ね、計50万部で売り出された。発売初日にも異例の10万部の増刷を決めたが、売り切れ店が続出。15日にも20万部の増刷を決め、6刷80万部に達していた。〉(産経新聞2013年4月18日)
村上春樹の新作長編『色彩を持たない多崎つくると、 彼の巡礼の年』が発売直後からベストセラーになっているという。 僕もまた、村上春樹の愛読者のひとりだ。僕の代表作『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)は村上春樹論でもある。「リトル・ピープル」とはこの本が刊行された当時の春樹の最新作『1Q84』に登場する超自然的な存在にして「悪」の象徴だ。この『1Q84』という小説に、僕は不満を覚えた。正確にはこれまでの村上春樹の長編小説に比べて、あまり想像力を刺激されなかった。そしてそのことが、僕がその本を書く動機になった。
春樹は2008年、おそらくは『1Q84』執筆初期に行われたインタビュー中の発言にてこう述べている。
〈「僕が今、一番恐ろしいと思うのは特定の主義主張による『精神的な囲い込み』のようなものです。多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない。オウム真理教は極端な例だけど、いろんな檻というか囲い込みがあって、そこに入ってしまうと下手すると抜けられなくなる」〉(毎日新聞 2008年5月12日 僕にとっての〈世界文学〉そして〈世界〉)
リトル・ピープルとはまさに、人々を「精神的な囲い込み」にいざなう社会構造の象徴だ。このリトル・ピープルに対抗するために主人公とヒロインたちが行動を起こす──それが『1Q84』の物語の骨子だ。しかし『1Q84』は完結編であるBOOK3で、それまで中心にあったこの主題──リトル・ピープルの時代への「対抗」という主題──を大きく後退させて(事実上放棄して)しまう。前半に物語を牽引したリトル・ピープルとそれを奉じるカルト教団はほとんど姿を見せず、主人公の「父」との和解と、ヒロインの一人との再会がクローズアップされる。主人公=中年男性の自己回復と自分探しの物語が全面化し、時代へのコミットメントという主題は後退するのだ。僕はここに村上春樹の想像力の限界を感じて、そして前述したあの本(『リトル・ピープルの時代』)を書いた。現代=リトル・ピープルの時代へのコミットメントのかたちを模索する、という春樹から引き継いだ主題については、まったく別の作品群を用いて考え抜いた。
しかしその一方で、僕は春樹自身がいつか、それも近いうちにこの問題に彼なりの回答を示してくれるのではないかと期待していた。もちろん、これは僕の勝手な期待であり、作家が答える必要もなければ、答えないことで責められる必要もない。だから、僕は続く村上春樹の新作長編『色彩を持たない多崎つくると、 彼の巡礼の年』を一読したとき、個人的に落胆はしたがこれを批判しなければならないとは思わなかった。だから発売当日にこの本を買って読み終えた僕は、その日の夜に放送するこの春から担当することになったラジオの深夜放送番組で、この本はそもそも肩慣らし投球のようなもので、『ねじまき鳥クロニクル』や『海辺のカフカ』のような総合小説を期待してはいけないと釘を刺したうえで分析を始めた。
そう、『色彩を持たない多崎つくると、 彼の巡礼の年』は発売されたことだけで「事件」となる社会的インパクトとは裏腹に、作品自体はいわゆる「小品」だ。 Wikipediaからあらすじを引用しよう。
〈多崎つくるは、木元沙羅と交際中だが、なかなか関係は進展しない。その原因として沙羅は、高校時代の友人から絶交されたことについてのわだかまりがあるのではいかと考えて、つくる自身が当時の友人たちに会って直接話をすることで、事態を打開するように勧める。そこでつくるは、名古屋とフィンランドに住む友人たちのもとを一人ずつ訪ね、絶交の真意を知る。そのうえで、あらたに沙羅との関係を進展させようと決意する。〉
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
鳥は重力に抗って飛ぶのではない 『風立ちぬ』 宇野常寛コレクション vol.15【毎週月曜配信】
2020-03-30 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回取り上げるのは、2013年夏に公開された映画『風立ちぬ』です。東日本大震災以降、「いまファンタジーを描くべきではない」とし、宮崎作品の中でもっともファンタジー要素の薄い作品となった本作。「美しい飛行機(=ゼロ戦)をつくること」を夢見た主人公・堀越二郎を通してえぐり出された、宮崎駿という作家の中核にあるものとは? ※本記事は「楽器と武器だけが人を殺すことができる」(メディアファクトリー 2014年)に収録された内容の再録です。
この夏公開された宮崎駿の新作長編アニメ映画『風立ちぬ』は、試写の段階から数多くの作家や批評家、編集者等の絶賛を集めていた。アニメ監督の細田守、特撮監督の樋口真嗣など試写で観た専門家の中には宮崎駿の最高傑作だと評する声も少なくない。この文章を書いている7月某日の時点ではまだ専門家の評価は出そろっていないし、興行成績の行方も分からない。しかし宮崎駿の5年ぶりの監督作品ということもあり注目度は極めて高く、今年最大の話題作になることは間違いないだろう。(かくいう僕も試写で数週間前に鑑賞している。)
論を進める前に、簡単にその内容を要約しよう。東日本大震災以降、宮崎駿は「いまファンタジーを描くべきではない」とする旨の発言を行なっている。その発言通り本作『風立ちぬ』は宮崎作品の中でもっともファンタジー要素の薄い作品となった。ゼロ戦の設計者として知られる軍事技術者・堀越二郎の半生を、堀辰雄の同名小説に着想を得て脚色したという本作の舞台は戦前から戦中にかけての時代である。主人公の二郎は比較的裕福な家庭に生まれ、優しい母親に慈しまれて育ち、弱いものいじめを見過ごさない高潔な精神をもった少年として登場する。二郎はこの少年期から飛行機の魅力に捉われている。しかし近眼の二郎は自分がパイロットにはなれないことを知り、その夢は飛行機をつくる技術者になることに傾いてゆく。とくに二郎はイタリアの技術者カプローニへの憧憬を募らせるようになり、いつかカプローニのような「美しい飛行機」をつくることが目標になってゆく。 そんな二郎が学生の折、関東大震災を経験する。このとき二郎と偶然出会うのがヒロインの菜穂子だ。二郎は菜穂子とその侍女の避難を誘導し実家まで送り届ける。その後、二郎は希望通り飛行機の設計者になり、戦闘機の開発に従事するようになる。そしてドイツ留学から帰国後に避暑地にて菜穂子と運命的な再会を果たし、恋に落ちる。菜穂子は重い結核にかかっていることを告白するが、二郎はそれを受け入れてふたりは婚約する。その後、二郎は主力戦闘機(のちのゼロ戦)の設計者に抜擢され、仕事に没頭する。一方の菜穂子の病状は悪化し、先が長くないことを悟った彼女は病院を抜け出して無理を押して二郎のもとにかけつけ、ふたりは結婚する。ちょうどゼロ戦の開発が佳境にさしかかったころ、ふたりの短い結婚生活が送られることになる。そしてゼロ戦の開発は成功し、菜穂子は間もなく亡くなったことが示唆される。「美しい飛行機」をつくるという夢を叶えた二郎だが、それが戦争の道具として使用され、巨大な殺戮と破壊の象徴になってしまった現実に直面するが、菜穂子の存在を支えに「生きねば」と決意する。
本作については、その完成度を評価する声が集まるその一方で「美しい飛行機をつくる」ことを追求する二郎と、菜穂子との恋愛の二つの物語が乖離して、噛み合っていないという批判も多く寄せられている。たとえば先日、僕はアニメ作家の富野由悠季監督と対談後、食事をしながらこの映画について語る機会があった。宮崎駿と同年齢である富野はこの映画の肝はカプローニの解釈、つまりテクノロジーと文明を巡る物語にあり、菜穂子との恋愛物語は添え物に過ぎないと語った。もちろん、富野はそれを否定的に語ったのではなくそれゆえに同作は傑作だと主張した。しかし、僕の考えは少し違う。僕の考えでは、むしろこのふたつの物語は根底で深くつながっているのだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
〈失われた未来〉を取り戻すために 『STAND BY ME ドラえもん』宇野常寛コレクション vol.14【毎週月曜配信】
2020-03-23 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回は、2014年夏に公開された映画『STAND BY ME ドラえもん』を取り上げます。 原作のエピソードを再構成・アレンジし、のび太の成長物語として『ドラえもん』の(事実上の)完結をなし得た本作。しかし、のび太の成長物語として描かれたことで浮かび上がる、かつて藤子・F・不二雄が描こうとした、現代日本では失われてしまった未来とは何だったのでしょうか。 ※本記事は「楽器と武器だけが人を殺すことができる」(メディアファクトリー 2014年)に収録された内容の再録です。
《札幌市の札幌琴似工業高の社会科教諭・川原茂雄さん(57)が16日、弁護士を招いて集団的自衛権を学ぶ授業を行った。「2学期から憲法を学ぶ前に、憲法が生活と身近にあることを感じてほしい」という考えからだ。大人にも分かりにくい集団的自衛権の問題を、どう高校生に伝えるか。絵や図を多くし、例え話で 身近な事例に近づけて教えた。 授業は、2年生の現代社会。札幌弁護士会の伊藤絢子弁護士(32)が担当した。まず生徒が伊藤さんに仕事や趣味について質問し、空気がほぐれてきたところで、話は本題に移った。川原さんと伊藤さんは、「ドラえもん」を例に話を進めた。米国は「ジャイアン」、日本は「のび太」。安倍晋三首相は集団的自衛権の行使容認で「日本が戦争に巻き込まれる恐れは一層なくなっていく」と胸を張ったが、「のび太が武装して僕は強いといっても、本当に自分を守れるかな」と川原さん。生徒はみな顔を上げ、考えこんだ。伊藤さんは「武装してけんかをするか、何も持たずやられるのか、選択肢は二つじゃないよね」と、話し合いでの解決法を示した。》(朝日新聞7月19日刊)
先日、ラジオのニュース番組にゲスト出演したとき、集団的自衛権をめぐる議論について意見を求められた。札幌市の高校の授業で「ドラえもん」を例に集団的自衛権についてディスカッションが行われ、批判を浴びているのだという。番組を担当する局のアナウンサーは僕に尋ねた。「集団的自衛権の是非はひとまず横においておいて、サブカルチャーの例でこうした話題を説明する授業についてどう思うか」と。 僕は迷わず答えた。「それは当然のことだ」と。戦後社会は、軍事について、戦争について、安全保障について正面から語り、議論し、描くことを忌避する文化空間を維持して来た。戦後社会の繁栄と安定がアメリカの核の傘の下に成り立っていることを隠蔽し、破壊と暴力には恐怖と嫌悪と同じくらい憧れと快楽が伴うという現実をも隠蔽して来た。だからこそ、油断するとすぐに安易に戦争の道を歩みかねない人間には理性による戦争抑止が必要なのだという論理にたどりつくことなく、単に忌避し、隠蔽して来た。しかしサブカルチャーだけが戦争という現実を子どもたちに伝えて来た。 いくら、戦中派の実体験を拝聴しても、いくら社会科見学で戦争の傷跡をめぐっても伝えられない戦争の側面について、人間の業の本質について伝えてくれたのは、ファンタジーや幼児番組のかたちをとったサブカルチャーだった。核という人類には過ぎた力への憧れと恐れは『ゴジラ』が、安保体制下における正義の不可能性は『ウルトラマン』が、そして第二次世界大戦で悪の側に置かれたことで拭えぬ傷を負った男性性の迷走は『宇宙戦艦ヤマト』が、それぞれ結果的に、あるいは自覚的に引き受けていったのだ。 僕たちは戦争のもつほんとうの恐ろしさも、そして魔性の魅力も、サブカルチャーから教わって来た。だから「ドラえもん」が集団的自衛権のたとえに用いられるのは至極当然のことだ。実際、のび太という自力では何もなし得ない非力な主人公は、自分たちの力では平和と安定を守れない戦後日本の似姿に他ならない。
僕は集団的自衛権の安易な行使容認には反対だし、安倍政権の立憲主義を踏みにじる解釈改憲にも批判的だ。しかし、それ以上に、こうしてアメリカの核の傘に守られている現実から目を背け、憲法九条があったからこそ戦後日本の平和が保たれて来た、なんて見え透いた嘘をこの期に及んで振りかざす左翼の愚かさと、それで安倍晋三が止められると思っている能天気さに軽蔑を禁じ得ない。野暮を承知で札幌の高校教諭のたとえ話に突っ込むなら、ジャイアンはアメリカではなくかつてはソビエト、いまは中国であり、そしてドラえもんはアメリカに他ならない。そしてドラえもんの力で幸福(戦後復興と平和)を享受しながらも、それゆえに成長できないのび太=日本が自立するには対米従属の時代を終わらせるしか、ドラえもんにさよならを告げるしかないのだ。もちろん、こうした構造自体がグローバル化が進行し、日本に限らずあらゆる国家にとって一国防衛が現実的ではなくなった今となっては過去のものだ。「その意味においては」ドラえもんで集団的自衛権のたとえとするのはもはや「旧い」のかもしれない。
だから、この夏公開された映画『STAND BY MEドラえもん』を見たときは、ひどく悲しくなった。映画の出来が悪かったわけではない。むしろその逆で、本作が原作のエピソードを巧みに再構成し、アレンジし、今は亡き藤子・F・不二雄がなし得なかった『ドラえもん』の(事実上の)完結をなし得たのはまぎれもない達成だと思う。 本作において、のび太は成長する。ドラえもんに甘やかされてきたのび太は、その環境に甘えることなく、ドラえもんがいなくても強く前向きに生きていける青年に成長する。それもジャイアンのように単に強くなるのではなく、むしろドラえもんに甘やかされたことで得られた環境の中で、自分の持っている「優しさ」を武器に生きていくすべを獲得する。これはまさに、戦後民主主義が目指した価値そのものだったと言えるだろう。アメリカのように強くなるのではなく、日本的な優しさの価値で、武力ではなく文化と経済で、世界に価値を認められる──本作は藤子が生前描き遺したいくつかのエピソードを中心に、それらをつなぎ、そして要所要所をアレンジして、彼にできなかったのび太の成長物語としての『ドラえもん』を見事に完結させたのだ。しかし、いやだからこそ、映画を見終えた僕は悲しくなった。なぜか。それは藤子・F・不二雄が、『ドラえもん』をむしろ完結「させなかった」ことで描こうとしたものが、未来が、この2014年の日本ではほぼ崩れ去ろうとしていることが分かってしまったからだ。そして、この映画が描いているもの、すなわち「戦後的な成熟」のモデルは既にノスタルジィとしてしか成立しない過去の存在でしかないことが分かってしまったからだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
「それでも、生きてゆく」ために必要な『最高の離婚』 宇野常寛コレクション vol.13【毎週月曜配信】
2020-03-16 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回取り上げるのは2013年のテレビドラマ『最高の離婚』です。〈ここではない、どこか〉ではなく〈いま、ここ〉を舞台に現実から半歩だけ浮き上がったファンタジーを描いてきた脚本家・坂元裕二。震災以降、非日常と日常がつながっていることが明らかになった中で、「それでも、生きてゆく」ために必要なものとは……?
※本記事は「原子爆弾とジョーカーなき世界」(メディアファクトリー)に収録された内容の再録です。
最近はじめた趣味は何かと尋ねられると、「歩く」ことだと答えることが多い。僕は高田馬場に住んでいるのだけれども、夏場を中心に友人を誘ってよく、深夜に歩く。最初の頃は早稲田通りから神楽坂を抜けて飯田橋に降り、麹町に抜ける。あるいは明治通りを南下して、新宿・渋谷の眠らない街を横目に恵比寿に向かう。気が向いたときはツイッターやフェイスブックに道中の写真をコメント付きで投稿しながら歩く。そうすると、嗅ぎ付けた読者が僕らを見つけて合流してくれることもある。だいたい、疲れたら深夜までやっている食堂やファミリーレストランを見つけて一服して、電車かタクシーで帰る。自由業の大人だからできる、ちょっと贅沢な遊びだと思う。 そして、東京に住んで今年で七年になるが、趣味で歩くようになってから街の見え方が変わったように思える。僕にとって東京は随分変わった街で、普通に暮らしているとほとんど地理感覚をもつことができない。たとえば僕が住んでいる高田馬場から、江古田や護国寺は実は距離的にはほとんど離れていない。しかし僕らはこれらの街をとても遠くに感じている。実際にはもっともっと距離の離れた渋谷や日本橋のほうを近くに感じているのだ。これは端的に、鉄道のアクセスの問題だ。高田馬場からは山手線や東西線が直通している渋谷や日本橋のほうが、乗換を要する江古田や護国寺よりも(鉄道については)短時間で移動できるのだ。そして、東京は僕に言わせれば極度な鉄道依存の街だ。街の規模自体が大きすぎるのと、自動車所有コストの高さ、そして道路事情の悪さを考えると、生活者のほとんどは鉄道網に依存した都市生活を余儀なくされる。そうすると距離と時間の関係が逆転していく。江古田よりも日本橋を、護国寺よりも渋谷を近く感じてしまう。 これはアニメ作家の押井守がもう二十年近く前にエッセイで書いていたことでもある。当時の僕はその意味が今一つピンとこなかった。けれど、会社を辞めて自由業の物書きになって、ふと思い立って趣味で「歩く」ようになってから押井守が言おうとしていたことの意味が分かるようになった。 同じ街でも、接し方が異なるだけでまったく見え方が異なる。鉄道で移動する東京と、歩いて移動する東京は同じ街のはずなのに別の街、別の世界に見える、のだ。川の流れや土地の起伏に沿って、いかなる文化の街並みが配置されているのか、あるいはそれが広大な敷地をもつ工場や官公庁、学校といったものによって分断され、再編集されているのか。「歩く」ことで見えてくる東京の文脈は鉄道で移動するそれとはまるで異なっている。
そしてこの話をすると、友人知人たちの何割かは確実に二年前のあの日の話をする。あの日、鉄道がほとんど運休して自分は、あるいは自分の親しい誰それは帰宅難民として久しぶりに東京の街を「歩いた」のだと。そして、その話をする彼らは(不謹慎な話だけれど)誰もがどこか楽しそう、に僕には見える。震災によって日常(=鉄道)が一時的に切断された結果、そこに東京の街を歩くという非日常が出現したのだ。それも、僕たちは普段生きている世界とはまったく異なる〈ここではない、どこか〉に連れ出されたのではない。〈いま、ここ〉により深く潜ることで、同じ世界に留まりながら非日常を体験しているのだ。 たぶん、あの二人もそうだったのではないか。その結果、なんとなく付き合うことになって、そしてなんとなく結婚することになったのではないか、と僕は想像する。誰のことかと言うと、テレビドラマ『最高の離婚』に登場した濱崎夫妻のことだ。自動販売機メーカーの営業マンである光生と、彼の営業先の受付嬢だった結夏は、その日までほとんど話したことのないただの顔見知りだったという。しかし、その日、ともに帰宅難民になって自宅まで歩くことになったふたりは路上で一緒になる。心細さからとにかく誰かと一緒に居たい、という感情が発生し、ふたりの距離を近づけていく。そして物語はそんなきっかけで結婚に至ったふたりが、「性格の不一致」から離婚するところからはじまる。(ふたりの)結婚とは、あの日東京の鉄道網が一瞬だけ麻痺した瞬間に発生した非日常的な幻想でしかないのではないか。そんな疑問をふたりが抱くところから、物語ははじまる。ドラマは若い夫婦にありがちな、生活上の小さなトラブルや行き違いを細かく盛り込んで巧みに笑いを誘いながらそんな問いを突き付けてくる。結夏を演じる尾野真千子の大ファンである僕も毎週くすくすと笑いながら、楽しみに番組を観ていた。登場人物のうち、自分は誰それに近いかもしれない、誰それのようなことをやってパートナーを怒らせたことがある、などと友人たちと話すのが楽しかった。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
いま爆弾を、花火に変える方法は――『So long !』 宇野常寛コレクション vol.12【毎週月曜配信】
2020-03-09 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回は2013年に発売されたAKB48の30枚目のシングル『So long !』を取り上げます。新潟県長岡市を舞台に映画監督・大林宣彦が手掛けるMVが制作された本作。被災地と観光地、戦争と戦後のイメージがバラバラのまま刻み込まれた映像は、21世紀における「映画」というメディアの原理的な不可能性を示すものでした。 ※本記事は「原子爆弾とジョーカーなき世界」(メディアファクトリー)に収録された内容の再録です。
《長岡市は、日本一の大河・信濃川が市内中央をゆったりと流れ、市域は守門岳から日本海まで広がる人口28万人のまちです。 (略) 戊辰戦争(1868年)と長岡空襲(1945年)で、2度の戦禍に遭いながらその都度、長岡のまちは、「米百俵」の精神を受け継ぐ市民の力で復興を成し遂げてきました。中越大震災をはじめとした相次ぐ災害にも、「市民力」「地域力」そして「市民協働」のパワーで、新たな価値を生み出す「創造的復興」に取り組んでいます。》(長岡市公式ウェブサイトより)
新潟県長岡市の紋章のモチーフは不死鳥──フェニックスだという。中越地方の中心地であり、花火のまちとしても知られる長岡の歴史は、同時にまちを何度も襲った災厄と、その復興の反復の歴史でもあるからだ。 戊辰戦争の折、当時の長岡藩は幕府と新政府のあいだで中立を保とうとしていたという。しかし、歴史の潮流は長岡の灰色の選択を許さなかった。結果として佐幕派に与せざるを得なくなった長岡は新政府軍の攻撃を受け、城下町が戦地となった結果多くの犠牲者が出た。 太平洋戦争末期には──米軍の空襲目標とされ、1945年8月1日の長岡空襲では市街地の大半が灰燼と化し、その死亡者は1400人以上にも上った。 そしてその度に、長岡はまちの人々の努力で奇跡的な復興を遂げてきた。だから、このまちのシンボルはフェニックスだ。 2004年10月の新潟県中越地震でも、長岡は市の南部を中心に大きな被害を受けることになった。まちの名物である毎年8月の長岡まつりの花火大会では「フェニックス」と題された復興祈願花火が打ち上げられた。これは市民から募った協賛金で打ち上げられた特製の一発だった。その後も、長岡では年末のカウントダウンや毎年10月に行われる「復興の集い」など特別な夜には必ず打ち上げられる花火として定着しているという。 そんな長岡は、2011年の東日本大震災に際して、まっさきに避難民の受け入れを申し出た自治体のひとつだった。震災の発生から5日後には市内36カ所のコミュニティーセンターをはじめ地域会館、文化施設、地域体育館などが避難民の宿泊所として提供されることが決定した。森市長は新聞の取材に「中越地震でお世話になった分を返したい」と話した、という。
そして物語はこうして長岡にひとりの少女が、南相馬から疎開してくることではじまる。そう、AKB48の30枚目のシングル『So long !』のMVは、長岡と南相馬──ふたつの場所を結ぶ物語として、60分強の「長編映画」として発表された。監督は80年代青春映画の巨匠・大林宣彦だ。大林は昨2012年、まさにこの復興のまち・長岡を題材に映画『この空の花』を発表したばかりだった。そして映画『So long !』は事実上『この空の花』のスピンオフ的な作品だと言える。70年近く前の長岡空襲で死んだ少女が、現代によみがえり戦争の記憶を遺すための物語を綴る──『この空の花』の物語に感動し、ヒロインの少女に自分を重ね合わせることで女優を志すようになった長岡の女子高生──それが『So long !』のヒロインのひとり・夢だ。そしてそんな彼女の前に、南相馬から疎開してきた少し大人びた目をした少女が現れる。それが、『So long !』のもうひとりのヒロイン・未来だ。 物語はふたりの少女とその仲間たちの紹介からはじまる。観光ビデオよろしくそれぞれ土着の産業や伝統文化に縁のある家庭に生まれたことに設定された彼女たちの周囲には、長岡の歴史に刻まれた傷や、過去の亡霊が常にまとわりついている。そう、彼女たちの青春は過去の戦争の記憶をめぐる旅として描かれる。なぜか。なぜならば、この映画のコンセプトは戦争の記憶=誰もが共有できる(していた)物語の力で、長岡と遠く離れた南相馬の地を結ぶこと、だからだ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
これは想像力の要らない/必要な仕事だ――2012年12月衆議院総選挙から日本を考える 宇野常寛コレクション vol.11【毎週月曜配信】
2020-03-02 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回は2012年12月に行われた衆議院総選挙を取り上げます。民主党政権が敗北を喫し、現在まで続く第二次安倍政権の始まりとなったこの選挙と同じ時期に、都市部のホワイトカラー層の間で胎動し始めた「夜の世界」の思想と、その背景について論じます。 ※本記事は「原子爆弾とジョーカーなき世界」(メディアファクトリー)に収録された内容の再録です。
二〇一二年一二月の衆議院総選挙は自由民主党の歴史的な大勝に終わり、三年に及ぶ民主党政権は終わりを告げた。この結果を開票速報のニュースで知った僕は、ひとこと「末法の世だな」と思った。この国がいま、とてつもなく大きな暗礁に乗り上げてしまったと感じたからだ。ただ誤解しないで欲しい。僕は安倍晋三政権そのものを否定する気はない。当然のことだが、個別の政策や決定に是々非々で考えている。たとえば僕は安倍政権の掲げるリフレーション政策は基本的に支持しているし、改憲し自衛隊を国軍とすること自体にも賛成だ。しかしその一方でたとえば安倍晋三のナショナリズムについての考え方──「美しい国」という言葉が象徴するそれ──にはひどく時代錯誤なものを感じるし、その改正憲法草案に見られる人権思想の希薄さにはひどい嫌悪すら覚える。しかし、僕が問題にしているのは安倍政権の是非ではない。今回の選挙を通して僕が痛感しているのは、この国をほんとうに分断している争点が選挙という回路においてはまったく機能していないこと、なのだ。
新聞の政治面やテレビの社会面に呼ばれるたびに繰り返し述べていることだが、この国はコンピューターにたとえるのならその基本的なシステム(オペレーションシステム=OS)がその耐用年数を過ぎても放置されてしまっているような状態にあると思う。たとえば「標準家庭」という概念がそれだ。これは総務省が発表している「家計調査」という報告で用いられている言葉で、戦後日本では年金や保険、税、保育園の数などの社会制度、さらには住宅や電力・給湯設備、家電の規格、車のサイズなど、いろいろなものが標準的な家族形態を基準にして企画され、作られてきた。そしてこの「標準家庭」のモデルはいまだに「夫婦と子ども二人の合計四人で構成される世帯のうち、有業者が世帯主一人だけの世帯」──つまり「正社員の父+専業主婦の母+子ども二人」というモデルなのだ。 女性の社会進出、少子化、晩婚化……二一世紀の現在、この国でこうした「標準家庭」が現実から解離し始めていることは誰の目にも明らかだろう。そう、この国はいまだに「戦後」のシステムで動いているのだ。冷戦も、バブル経済も二〇年前に「終わった」にもかかわらず──戦後的システムを成立させていた基礎的な条件が変化したにもかかわらず──そのアップデートを拒否してきたのだ。その結果、経済は停滞し、政治は不安定になり、出口のない閉塞感がこの国を覆っている。 では、どこに突破口があるのか。友人である批評家(濱野智史)は、僕との共著に寄せた文章でこう述べている。
〈この国の希望を考えるというとき、ずっと気にかかっていた言葉がある。「私はこれからの日本に対して希望をつなぐことができない。このまま行ったら「日本」はなくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう」。一九七〇年七月、三島由紀夫が自決する直前に書きつけた言葉である。 この三島の予言は見事に当たっていた。そう多くの人が考えるだろう。たしかに、表向きはそうである。だが、私はまったくそう思わない。それはどういうことか。日本社会の「裏面」を見ればよいからだ。それは政治や経済といった「昼の世界」に対し、社会的に陽の目を浴びることのない「夜の世界」としての、日本のサブカルチャーやインターネット環境である。この十数年、そこでは異様なまでの生成・進化が絶えまなく起こってきた。そこにはいままで誰も発想しなかったような、多様で数奇なアイデアとクリエイティヴィティがある。熱意がある。しばしばその領域は引きこもりのオタクたちが集まる「タコツボ」だと批判されるが、「タコツボ」に棲み分けるからこそ、そこでは異様な進化と洗練が起こるのだ。〉(宇野常寛 濱野智史『希望論』NHKブックス 二〇一二年)
そう、行き詰まり、閉塞した日本はこの社会の半分でしかない。活力に満ちた、クリエティブなもうひとつの日本が、この「失われた二〇年」に既に生まれていたのだ。それが「夜の世界」だ。
■PLANETSチャンネルの月額会員になると…・入会月以降の記事を読むことができるようになります。・PLANETSチャンネルの生放送や動画アーカイブが視聴できます。
-
鎌倉にて――『最後から二番目の恋』宇野常寛コレクション vol.10【毎週月曜配信】
2020-02-17 07:00
今朝のメルマガは、『宇野常寛コレクション』をお届けします。今回取り上げるのは2012年のテレビドラマ『最後から二番目の恋』です。都市生活を相対化するユートピアを描き続けてきた脚本家・岡田惠和が、〈ディストピアとしての現実〉(『小公女セイラ』『銭ゲバ』)へのコミットを経た後にたどり着いた、日常に隣接する涅槃的なユートピアとは……? ※本記事は「原子爆弾とジョーカーなき世界」(メディアファクトリー)に収録された内容の再録です。
日曜日の朝に早く起きて、数年ぶりに鎌倉に出かけた。湘南新宿ラインにゆられて一時間と少し、降りた駅前は観光客でごったがえしていた。これぞ秋晴れと言わんばかりの青空の下、僕はFacebookの自分が立てたイベントページに投稿した。「宇野です、今、駅前の広場に居ます」──おおよそ10分のあいだに、待ち合わせた仲間たちが集まってきた。かつて勤めていた会社の先輩(30代後半)、アドバイザーを務めていた会社の女性(30代後半)、別の仕事で知り合ったテレビディレクター(30代半ば)、非常勤講師を務めていた大学の教え子とその彼氏、ツイッターで知り合ったドラマファンの舞台女優(30代)、僕の読者だという八王子の専業主婦(40代)、個人的に開催しているAKB研究会メンバーの男子学生、そして新潟からわざわざ駆けつけてくれたNHKの討論番組で知り合った自営業者の男性(30代)……傍から見たら、どんな集団に見えていたのだろうと思う。しかし、ほとんどのメンバーが(僕を除いて)初対面であるという状況だったけれど、みんな瞬く間に意気投合して盛り上がり始めた。話題は一つ。ドラマ『最後から二番目の恋』のことだ。僕らは鎌倉を舞台にしたこのドラマの大ファンで、休日を利用してロケ地めぐり──いわゆる「聖地巡礼」にやって来たのだ。 きっかけはほんの思い付きだった。僕がなんとなく、このドラマが好きだ、聖地巡礼に行きたい、とツイッター及びFacebookに投稿したところ、瞬く間に十人以上のメンバーが集まった。中には、僕のツイッターアカウントをフォローしているものの一面識もない人もいた。でも、僕は気にすることなく彼女たちを誘った。このドラマが好きな人に、悪い人はいないと思ったからだ。
【新刊】宇野常寛の新著『遅いインターネット』2月20日発売!
インターネットは世の中の「速度」を決定的に上げた一方、その弊害がさまざまな場面で現出しています。世界の分断、排外主義の台頭、そしてポピュリズムによる民主主義の暴走は、「速すぎるインターネット」がもたらすそれの典型例といえます。インターネットによって本来辿り着くべきだった未来を取り戻すには今何が必要なのか、提言します。
宇野常寛 遅いインターネット(NewsPicks Book) 幻冬舎 1760円