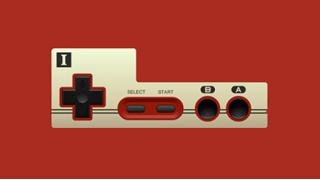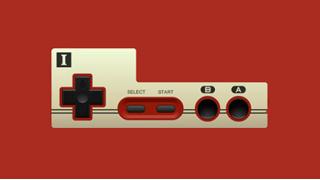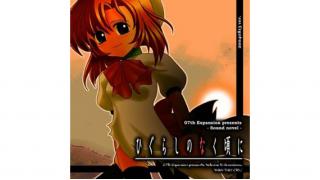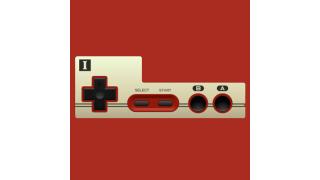-
「同人ゲーム」と「アーケードTCG」が告げた〈拡張現実の時代〉の足音〜『東方Project』『月姫』『ムシキング』『ラブandベリー』〜(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.346 ☆
2015-06-17 07:00
「同人ゲーム」と「アーケードTCG」が告げた〈拡張現実の時代〉の足音〜『東方Project』『月姫』『ムシキング』『ラブandベリー』〜(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.6.17 vol.346
http://wakusei2nd.com
本日は『中川大地の現代ゲーム全史』最新回をお届けします。今回論じるのは2000年代前半。『東方Project』『ひぐらしのなく頃に』『月姫』といった同人ゲーム、そして『ムシキング』『ラブandベリー』といったアーケード・トレーディングカードゲームの隆盛を振り返ります。
「中川大地の現代ゲーム全史」(これまでの配信記事一覧はこちらから )
第9章 和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業
2000年代前半:〈仮想現実の時代〉終期(7)
前回記事:FPSが先導するグローバル・ゲームの転回〜『Halo』『ハーフライフ2』〜
■「同人ゲーム」ムーブメントが担った役割
ただし、パソコンとインターネットの普及によってゲームエンジンなどの開発環境がオープン化し、一定の規格化がなされたゲームジャンルでのコンテンツ制作が活性化されたのは、海外FPSに限った話ではない。国内でも同様の構造によってアマチュアの個人やインディーズ集団によるゲーム制作がエンパワーメントされていく流れは、グローバルな動向とは切り離された回路において、独自のかたちで進行していたのである。
脈絡を遡れば、プログラミングを要さずに個人がゲーム作品を制作できるオーサリングツールとしては、すでにアスキー(現:エンターブレイン)が1986年の時点で、『アドベンチャーツクール』を「LOGin」誌面で発表していた。これを嚆矢として、1990年代初頭にはMSX用の『Dante』に始まる『RPGツクール』シリーズを発売。以来、国産パソコンや家庭用ゲーム機の高機能化に合わせて、同社からはシューティング(STG)やサウンドノベル、対戦格闘など、様々な人気ゲームジャンルの「ツクール」が継続的にリリースされていた。
▲RPGツクール2(アスキー 1996年)
さらに同社が刊行するパソコン誌などの主催により、ちょうど1980年代マイコンブーム期から行われていたゲームプログラミングコンテストの延長線上に、「コンテストパーク」(1994〜1997年)や「アスキーエンタテインメントソフトウェアコンテスト」(1995〜2001年)といったコンテストを開催。各種「ツクール」で制作したユーザーの自作ゲームを表彰し、入賞作がFDDやCD−ROMといった雑誌の付録メディアや、パソコン通信のダウンロードで配布されて遊ばれるというフリーゲームのエコシステムが、インターネット普及以前から根強く築かれていたのである。
ここでのコンテストと、縦スクロールSTGの『ALLTYNEX』(SITAR SKAIN 1996年)シリーズやホラーAVGの『コープスパーティー』(チームグリグリ 1996年)、現代日本風RPG『Moon Whistle』(神無月サスケ 1999年)など、各年度の受賞作が、「ツクラー」と呼ばれる自作ゲームコミュニティ内で注目を集めた。しかしながら、家庭用ゲーム機を主戦場に、商用ゲームが爆発的な進化を遂げていた1990年代の時点にあっては、あくまでニッチなホビーの領域に留まり、かつての中村光一や田尻智の登場のように、ゲームシーン全体へのインパクトを残すほどのケースは、まだ輩出されていなかったと言ってよいだろう。
これに加えて、同じく90年代にはコミックマーケットなどの即売会や「とらのあな」「メッセサンオー」といったショップなど、オタク二次創作系のマンガ同人誌が確立した販路とカルチャーに密着するかたちで、同人ゲームを頒布するチャンネルも大きく発展している。
こちらの土壌では、東京電機大学生の同人サークルに所属していたZUNによる固定画面アクション『東方霊異伝』(Amusement Makers 1995年)を嚆矢とする「東方Project」がスタートしたり、前章に述べたLeafやKeyのアダルトビジュアルノベル作品の登場人物を流用した対戦格闘『THE QUEEN OF HEART』(渡辺製作所 1998年)シリーズに代表される「葉鍵系」の二次創作ジャンルが勃興したりと、特に美少女キャラクターの図像を全面に押し出すタイプの自作ゲームが、とりわけ大きく注目され始めていた。
そしてインターネット以降は、2D対戦格闘の作成エンジンである「M.U.G.E.N」や、シミュレーションRPG用の「SRC」、テキストシナリオと一枚絵を組み合わせるノベル式のAVGのスクリプターである「吉里吉里」「NScripter」など、フリーウェアでの開発環境が相次いで登場。これにより、コミケ文化の中核をなすアニメ的なキャラクターの同人絵師たちや、DTMによる同人音楽の作り手や歌い手たち、さらには文字だけの表現ではなかなか人気を獲得できない同人小説の書き手たちといった、あらゆる同人ジャンルの人材がコラボ可能なメディアとして、同人ゲームのプレゼンスは大きく高まっていったのである。
このように、ツクール系とコンテストが培ってきたフリーゲームの脈絡と、コミケ的な同人創作カルチャーの複合メディア化としての同人ゲームの脈絡が、インターネットというインフラを得て相交わるようにして、00年代以降はかつてない規模と形態で、日本国内でも自作ゲーム発のムーブメントが影響力を獲得していくことになる。これはちょうど同時期の欧米圏では、インターネット以前からのハッカーコミュニティやMOD文化が、インディーゲームシーンの母体になっていったこととも対応する動向と言える。
その最初の開花となったタイトルが、2000年のコミックマーケットで初めて頒布された『月姫』だ。本作は、元々はゲーム開発会社でグラフィッカーとして働いていたグラフィック担当の武内崇と、その中学時代からの友人でWeb小説『空の境界』を発表していたシナリオ担当の奈須きのこを中心に結成された同人サークルTYPE-MOONの手で、NScripterを使って制作されたビジュアルノベルである。基本的な題材傾向はLeafの『雫』『痕』に近い路線ながら、奈須が温めてきた緻密な世界観体系に基づく斬新な伝綺ロマンを、商業作品に匹敵するボリュームとクオリティで展開したことで話題を呼び、口コミやネット上での評価を通じて、従来の同人ゲームとは桁違いのヒットを飛ばす。
そして人気がブレイクした結果、ファンによる二次創作アンソロジーやアニメ化、グッズといったメディアミックスや派生商品の発売が商業ベースで行われるという異例の展開に発展し、コンテンツビジネスの世界に同人ゲーム発の新たなサクセスパターンを確立するに至ったのである。
▲月姫(TYPE-MOON 2000年)
これに続くかたちで、02年には竜騎士07によるサウンドノベル『ひぐらしのなく頃に』(07th Expansion)の頒布が開始される。本作は、もはやAVGとしての展開分岐を排し、恐怖を中心とした情動に訴えかけるための純粋なテキスト演出のメディアとしてNScripterによるノベルゲーム形式を採用した、マルチメディア型のホラーミステリーとも言うべき作品だ。しかし、ユーザーに挑みかかるように出題編と回答編が数年間かけて交互にリリースされたことで、物語のアクロバティックな真相をめぐる議論なども発生。結果的にミステリーという文芸形式が持つ元々のゲーム的な性格を利用する、メタミステリーとしての性格をも帯びていったのが、「ゲーム」としての本作のひとつの特徴だろう。
加えて18禁ゲームではなかったことで、ライトノベルの読者に近い男女中高生を中心とした広範な層に訴求し、コミカライズやアニメ化などを通じて、『ひぐらし』は『月姫』以上のポピュラリティを獲得してゆく。
▲ひぐらしのなく頃に 鬼隠し~暇潰し編(07th Expansion 2002〜2004年)
(参考リンク)『ひぐらしのなく頃に』が到達したところ――「共同性」と「公共性」の相克の果てに(中川大地)
さらに同年、ゲーム会社に就職したZUNがサークル名を上海アリス幻樂団と改め、Windowsプラットフォームでは初めての作品となる『東方紅魔郷』で、4年ぶりに「東方Project」を再開する。『東方封魔録』から『東方怪綺談』にかけての初期作がPC-98向けにリリースされていた時代から、アーケードゲームの『怒首領蜂』(ケイブ 1997年)などと並び、「東方」は同人ゲームでありながら、敵キャラの発射する膨大な弾がまるで花火のように画面を埋め尽くす中をかいくぐっていく「弾幕STG」なるサブジャンルを代表する作品へと発展を遂げていた。
STGとしての「東方」の特色は、無機的な戦闘機を自機にしたSF的な世界観やバックストーリーが主流だったジャンルの王道に反し、日本神話に材を採った東洋風のファンタジー世界を舞台に、巫女や魔女などの美少女キャラクターを自機に据えつつ、ちょうど対戦格闘ゲームのように複数から選択できるようにしたことにある。各ステージのボスとして登場する敵キャラとの戦闘時には、互いのバストアップ図像や台詞テキストによって会話劇が展開するという、やはり対戦格闘に近い演出方法を導入。これにより、あくまで反射神経を競うストーリー性の薄弱なジャンルとしてのイメージを覆し、濃密なキャラクタードラマの器にもなりうるフォーマットとして、縦スクロール型STGのポテンシャルを再発掘したのである。
▲東方紅魔郷(上海アリス幻樂団 2002年)
加えて、敵キャラごとに差別化された弾幕攻撃の視覚効果と、ZUN自身の作曲による高BPMのトランサブルなBGMやSEによる聴覚演出が組み合わさることで、そのプレイ体験はほとんど音ゲーやDJセッション、あるいは舞踏に近いものになってゆく。こうした音楽性の充実もまた、「東方」のもうひとつの特徴であった。
元よりスクロール型のSTGというジャンルは、黎明期の『ゼビウス』の時点から、細野晴臣がアルバム『Video Gme Music』をするなど、アンビエントな音楽体験の生成ツールとして、多くの作り手やゲームミュージックファンによって意識され続けてきた系譜がある。ゆえに同時期には、そんなSTGの即興音楽的なポテンシャルを最大限に突き詰めたタイトルとして、水口哲也の『Rez』(セガ 2001年)のような作品も登場していた。ただしこちらの場合は、自機のシンボルを斜め後方から見下ろす立体的な視点のサードパーソンシューター(TPS)としての骨格を採りつつ、具象的なキャラクター性や物語性を排するミニマルなメディアアート型の演出を特徴としていた。
これとは対照的に、「東方」の場合は同じく音楽体験を強めるインタラクティブな視覚表現の追求でありながら、浮世絵のような独特の平面性を徹底した画面構成の中での弾幕の様式美や過剰な意匠性を強める方向への進化を遂げていったわけである。
【ここから先はPLANETSチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は6月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201506
-
FPSが先導するグローバル・ゲームの転回〜『Halo』『ハーフライフ2』〜(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.333 ☆
2015-05-29 07:00【お知らせ】落合陽一さんの月イチ連載『魔法の世紀』ですが、次回は来月(6月)初旬に配信予定となります。楽しみにしていただいている読者の皆様には大変申し訳ございません。今しばらく、お待ちいただければ幸いです。
FPSが先導するグローバル・ゲームの転回〜『Halo』『ハーフライフ2』〜(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.5.29 vol.333
http://wakusei2nd.com
本日は、隔週連載となった『中川大地の現代ゲーム全史』最新回をお届けします。
今回のテーマは、今や世界のゲーム市場のスタンダードとなった「FPS」。なぜ日本ゲームは覇権を失ったのか? 日本ゲーム市場の特殊性と、FPSというジャンルが成長し得た要因について振り返ります。
「中川大地の現代ゲーム全史」
第9章 和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業
2000年代前半:〈仮想現実の時代〉終期(6)
前回までの連載はこちらのリンクから。
■ ゲームエンジンのオープン化が駆動したFPSの隆盛
日本のゲームが、3DCGの時代に入っても2D時代からのゲームデザインを踏襲しつつ、ストーリーやキャラクター表現などの細部を拡充・複雑化させていく大作シリーズか、ワンオフ的な職人芸やゲームデザイン上のアイディアの新奇性で勝負する佳作に二極化して進化の袋小路に突入していく一方、アメリカを中心とした海外ではテクノロジーの進歩を直接的に投入するかたちでの右肩上がりの成長がリニアに継続していた。とりわけ『DOOM』や『Quake』で確立したFPSというゲームデザインは、本質的な骨格はタイトルによってほとんど変わることがなくとも、パソコン自体の急激なスペックアップに合わせたグラフィックや処理性能の向上を、身体的に実感できるベンチマークのような花形ジャンルとしてスタンダード化してゆく。
メルクマールとしては、閉鎖空間内での撃ち合いだった『Quake』に対して広大なフィールドを舞台にした『Unreal』(エピックゲームズ 1998年)や、単なる撃ち合いではなく一人称視点でできる高度なストーリー表現を追求した『ハーフライフ』(バルブソフトウェア 1999年)が登場し、やがてこのジャンルの3大シリーズと称されるようになるタイトルが、1990年代後半には出揃っている。いずれも始祖の『DOOM』がそうだったのと同様、3Dでの空間描画や物理演算など、ゲームの基幹部分を構成するプログラムエンジンがオープン化され、多くの個人や他社にもライセンス供与されて利用された。単体タイトルに投じられた開発成果がそれだけに留まらず、汎用フォーマットとして共有されて裾野を広げるモーメントを持っていたことが、このジャンルの強みと言えるだろう。これらのゲームエンジンを基盤に、ユーザーが自主制作したMODの集積が製品化されるケースも登場し、例えば『ハーフライフ』のエンジンを流用しながらオンライン対戦に特化した『Counter-Strike』(バルブソフトウェア 1999年)がジャンル史的なインパクトを残している。
FPSがこうしたスケールメリットを獲得した背景には、日本とは異なりパソコンゲーム市場全体が健在であったことや、ハッカーコミュニティの裾野の広さなどが、直接的な要因として挙げられる。ただし、より根底的な条件を問うなら、ゲームの〈仮想現実〉世界の構築において、実写的・自然主義的なリアリズムを志向する西洋近代型の遠近法的な空間認識が、われわれ日本人が想像する以上に強固な規範として根を下ろしている比較文明論的な前提を無視することはできないだろう。つまり、ゲームを進歩させる方向性として、「人間が知覚する現実そのものと見分けのつかない〝見たまま〟の体験に可能なかぎり漸近すべきである」というシンプルな理念が作り手と受け手の双方で自明に血肉化されているために、多くのティベロッパーが同一の方向を競って追求することについて、彼らには一切の迷いがない。
翻って、日本国内のうるさ型のゲームマニアやエッジの立ったクリエイターたちは、宮本茂や飯野賢治などに典型的なように、えてして「美麗な3DCGの進歩は、ゲームそのものの面白さの本質とは関係ない。むしろ2Dドット絵時代のようなローテクな創意工夫の積み重ねによって、誰も見たことのないシステムや視聴覚様式を発明し、多様な遊びの体験を発明し続けることこそが望ましい」といった美学を抱きがちだ。こうした意欲が、1990年代の国産ゲームソフトのカンブリア爆発を促してきたのはこれまでの章で見てきた通りであるが、言うなれば常に個々の作り手たちが、一シリーズごとにリスクを背負って唯一無二の破壊的イノベーションを起こし続けねばらないという強迫観念に等しい。実際的にはそれは、2000年代前半には『ガンパレ』や『塊魂』などを最後に息切れを起こしたという結果からみれば、長くは持続しえない夢想に他ならないものだった。
FPSを中心とする00年代の洋ゲーでは、そうした袋小路に陥ることなく、現実の物理法則という普遍的なレファレンスに準じたゲームエンジンによって、基本的な体験生成のシステムを規格化。その上で、バックストーリーの題材やビジュアルの質感、ゲームとしてのルール設計やレベルデザインの違いといった面での個性化と漸進的イノベーションの余地を残し、個々のタイトルがしのぎを削る競争環境が整う。こうした効率的な水平分業がなされたことで、和ゲー市場の停滞とは対照的な、持続的成長の礎が築かれたのである。
【ここから先はPLANETSチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は5月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201505
-
「ゲーム」からみた「伊藤計劃以後」〜コンピュータゲームのあゆみはフィクションの想像力をいかに変えたか〜(中川大地) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.328 ☆
2015-05-22 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
「ゲーム」からみた「伊藤計劃以後」〜コンピュータゲームのあゆみはフィクションの想像力をいかに変えたか〜(中川大地)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.5.22 vol.328
http://wakusei2nd.com
『虐殺器官』『ハーモニー』『屍者の帝国』のアニメ映画化/連続公開が今秋に迫り、没後6年にして再び注目を集めつつある伊藤計劃。その伊藤計劃の作品の現代性とは何だったのか――『ゲーム史』連載中の中川大地が、「純文学」「SF」「ゲーム」の3つのジャンルをキーワードに考察した論考を配信します。
画像出典:Project Itoh 公式サイト スクリーンショット
初出:S-Fマガジン 2011年 07月号(早川書房)※一部改稿
■ フィクション表現の変化の震源だった「ゲーム」
周知のように、1974年生まれの伊藤計劃は、幼少期にファミコンブームによるコンピュータゲーム産業の立ち上がりを経験し、その発展を血肉化してきた世代の精神性を最も濃密に体現する作家の一人である。デビュー作『虐殺器官』が、小島秀夫監督の『ポリスノーツ』や《メタルギア》シリーズから決定的な影響を受けているように、その想像力は日本ゲームの進化とともに歩んできたものと言える。
したがって「伊藤計劃以後」を展望するための補助線として、本稿ではゲームの発展史がフィクション表現の想像力に与えてきた影響を改めて把捉し直しておきたい。
伊藤個人の作家性に限らず、ゲームというカルチャージャンルの勃興と定着は、ここ20年あまりの日本の社会文化全般にとって、きわめて本質的かつ甚大な影響をもたらした変化の震源地であった。なぜならそれは、高度経済成長を終えて「実用」の領域では劇的な進歩が望めなくなった1970年代後半以降の日本にあって、唯一日進月歩の技術進歩を実感させてくれるコンピュータなる道具が不要不急の「遊び」の多様化を通じて人々の生活の中に入りこんでくるという、かつてない生活体験の変容そのものだったからである。
言い換えればコンピュータゲームは、人々が初めて接した最も純粋なかたちの消費社会の体現物であり、インターネット普及以前にあっては最も実感的に情報化社会なるものの手触りを味わえるマスプロダクトに他ならなかった。
かくして、高度成長期的な進歩への「夢」の名残を背負いながら、まずは「玩具」とカテゴライズされる生活の異物として登場したゲームは、1980年代のファミコンブーム期に《ドラクエ》シリーズのヒットなどストーリイ表現を伴うゲームが一般化したことを機に、しだいに独自のコンテンツ価値を持つ「作品」としての性格を認知されてゆく。特に1990年代以降、隣接するオタク系カルチャーのメディアミックス展開や、プレイステーションの成功によって音楽CDと同じ光学メディアによるパッケージソフト流通の方式が定着すると、この傾向はさらに顕著になものとなる。
こうした著作物性の前面化と、ポリゴン表現によるグラフィックスの3D化によって、この時代の大作ゲームは、急速に先行する総合視聴覚表現である映画を強く意識したものとなっていった。例えば伊藤計劃が最終作のノベライズを手がけた《メタルギア・ソリッド》も、こうした潮流の中で登場してきた「映画的」ゲームの最も代表的なシリーズである。
そしてゲームが産業資本によるメディア・テクノロジーのイノベーションの勢いのままに既存コンテンツジャンルの表現を旺盛に取り込んでいった動きの反作用として、逆にゲーム独自の体験性が旧メディアに輸出されていった例も枚挙に暇がない。
最も素朴な意味ではRPGによる「剣と魔法のファンタジー」の意匠やキャラクターメイキングの作法がライトノベルの成立を促したことや、「努力・友情・勝利」の精神論的なドラマツルギーが制していた少年マンガにおけるカードゲーム的な戦術性の導入、AVGなどにおける繰り返しプレイの経験を劇化した「ループもの」や善悪の規範ではなく等価なプレイヤー同士が不条理なルール設定の中で戦い合う「バトルロワイヤルもの」の流行など、形式・内容の両面でゲームの前提なしには成立しえない表現が1990〜2000年代のフィクションの潮流を牽引した。
つまり批評家の東浩紀が『AIR』や『ひぐらしのなく頃に』など美少女ゲームの影響圏に限定した作品から論じた「ゲーム的リアリズム」や、宇野常寛が諸ジャンルのコンテンツについて社会反映論として展開した「ゼロ年代の想像力」は、より直接的にはまさにコンピュータゲームを通じて形成されていった広範な文化再編の一部として捉え直すことができるのである。
■「文学」から「ゲーム」への移行が意味するもの
以上見たようなジャンルの再編をともなうゲーム発のフィクション変動の意義を、より本質論的な観点から位置づけるなら、それは近代という文明パラダイムの中でリアリズムを基軸とする指導理念の下に諸文化の中核として編成されてきた「文学」という装置の機能と地位が、事実上は「ゲーム」によって置き換えられつつあることを示している。
どういうことか。そもそもリアリズムに基づく純文学とは、先近代の神話や戯作のように単純・荒唐無稽で恣意的・予定調和的に見える幼稚な物語を批判し、現実の複雑さを科学を範とする理性的省察によって描出しようとする精神性から生み出されたものであった。
だが、近代社会が成熟していく過程で国民国家とセットになった理性的自我という観念の虚構性が明らかになるにつれ、しだいに文学は前衛としての役割を失っていく。現実の複雑性を描出しようとする物語批判の動機は、むしろ分裂症的な主体や言語的表層の難解な文体操作によって純文学を延命させようとする修正主義としてのポストモダニズムなどに転化していくが、正味の社会的なインパクトは喪失の一途にあったという他はない。
そうした中で、コンピュータゲームの登場によって20世紀の終わりから人類史上空前の規模でゲームなるものが普及し、フィクションの世界と結合したことは、文学の存立基盤にとっても巨大な意味を持っていたと言える。なぜなら、ゲームと物語は、ともに人間が外界の情報から材を得て虚構的な領域を形成するという現実加工の営みである点は共通していながら、その構成法がまったく異なるものだからである。
物語とは、基本的に人間が知覚経験を通じて得た情報ストックの中から個々人の主観的な認知バイアスによって取捨選択や圧縮を施し、事物の因果を暫定的に関係づけていく解釈作用によってシリアルに形成される、認知コストの低減のための記号化過程である。
対してゲームの場合は、ケイティ・サレンとエリック・ジマーマンによる最近のゲーム研究の標準書『ルールズ・オブ・プレイ』での概念整理に従うなら、窮極的には数学的に表現可能な「ルール」に基づくシステムを要件として備え、現実の時間と空間の中から「魔法円(マジックサークル)」などと称される「遊び」の領域を異化し、ルールの策定者にとっても予測不可能な経験を創発していく「可能性の空間」を生成する営みである。
つまり、ゲームは本質的に非物語的な現実経験の産生エンジンとしてあり、従来の物語では描かれえなかった現実性が自ずと備わりやすい性格を有している。
例えばアクションやシューティングにおいて、制作者の想定外のプレイングがゲームの醍醐味を引き出してきた例は数限りなくあるし、RPGなら通常の英雄物語では描かれないようなザコ敵とのランダム遭遇を避けられなかったり、物語の筋立てとはまったく無関係なパラメータ的事情や選択ミスによって死に至るような理不尽もままある。
そうした物語的な収まりの良さを逸脱する体験性を様々なレベルで有するゆえにこそ、ゲームの伸長は純文学が志向する「物語の中での物語批判」というミッションを別のかたちで置き換え、各フィクションジャンルの想像力にインパクトをもたらす中心源たりえたのではないだろうか。
■「日常化されたSF」としてのゲームと伊藤計劃の作家性
もうひとつ、純文学の中心性と並んで、ゲームによって成立基盤に侵食を受けてきたジャンルが存在する。同時代の支配的な先端技術が開きうる可能性を外挿し、それをフィクション上の世界律として組み直して作劇に活用する文芸手法、すなわちSFである。
すでに述べたように、人々にコンピュータ技術がなしうる「夢」を可能性の段階から体感させる装置であったゲーム機の歴史にあっては、何か大きな技術的イノベーションがあるたびに「まるでSFのようだ」という感慨が決まり文句のように寄せられるというプロセスが繰り返されてきた。これは裏を返せば、SFが純然たるアイディアの力によってセンスオブワンダーを与えることの敷居がきわめて高くなったことを意味する。
実際、80年代に発展して情報技術と身体の関係性の考察を押し進めたという点でコンピュータゲームとは双子のような関係にあるサイバーパンクを最後に、本質的なパラダイムの次元ではジャンルSFは同等以上の潮流を起こせていない。
【ここから先はPLANETSチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は5月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201505
-
大作シリーズの間隙で到達したゲームデザイン進化の極相〜『ガンパレ』『ICO』『塊魂』(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.323 ☆
2015-05-15 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
大作シリーズの間隙で到達したゲームデザイン進化の極相〜『ガンパレ』『ICO』『塊魂』(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.5.15 vol.323
http://wakusei2nd.com
本日は、月2回連載となった『中川大地の現代ゲーム全史』最新回をお届けします。今回のテーマは、PS2発売前後の端境期に登場した『ガンパレ』『ICO』『塊魂』といった異形の佳作たち。そのゲーム史的なインパクトを改めて振り返ります。
「中川大地の現代ゲーム全史」
第9章 和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業
2000年代前半:〈仮想現実の時代〉終期(5)
前回までの連載はこちらのリンクから。
■『ガンパレ』現象で爆発した「汎ゲーム」的な事件性
プレステ2の登場前後でゲーム開発が大規模化し、すでに確立された定番シリーズ以外のヒットが出づらくなる中、まったく新たなゲームジャンルが勃興して多くの追随を生むような頻度は、顕著に衰えを見せ始めていた。1990年代後半の玉石混淆の試行錯誤の時代に、ポリゴン表現やマルチメディア媒体を活かしてなしうる新たなゲームデザインのレパートリーはあらかた出尽くし、もはや画期的な開拓を行える余地が限られてきてしまったためだ。
しかしながら、業界全体の大きな潮流となることはなくとも、中小規模のディベロッパーやクリエイターたちが手がけるタイプの作品の中には、イノベーションのハードルが大きく高まったことを受けて、きわめてアイディア的に研ぎ澄まされたタイトルもまた少数ながら誕生していた。おそらくこの時期は、据え置き型ゲーム機でプレイできるスタンドアローン型のゲームという枠組みでは、「ゲームでしかなしえない体験とは何か」という問いを徹底して追求する斬新な傑作が登場した、最後の歴史的タイミングであった。それはちょうど、文学や美術、音楽といった先行芸術ジャンルが、20世紀後半以降は自らが芸術として成立しうる条件を自己言及的に追求していく段階に突入したのと、同様の史的変遷だったと言えるのかもしれない。
『FFⅨ』や『ドラクエⅦ』が発売された初代プレステの末期、ひっそりと発売された『高機動幻想ガンパレード・マーチ』(SCE 2000年)は、そうした前衛的な作品群の中でも、とりわけ特異なムーブメントを引き起こしたタイトルであった。熊本に本社を置くディベロッパーであるアルファ・システムの制作による本作は、第二次世界大戦後に突如として人類を襲った「幻獣」との戦争が続く世界で、人類の最終防衛線となった熊本にある実在の高校をモデルにした戦車学校を舞台に、人型戦車「士魂号」の小隊に配属された学兵たちの日々の訓練や交流といった学園生活と、襲来する敵との局地戦とを有機的に結びつけて構成された学園・戦争SLGである。
▲『高機動幻想ガンパレード・マーチ』(SCE 2000年)
このゲームの大部分は、実在のモデルを元に描かれた学園と周辺スポットの小さな空間内で、小隊を構成する22人のクラスメイトや教師たちNPC(ノンプレイヤーキャラクター)たちと日常的にコミュニケーションをとりながら訓練や整備などの行動を共にすることで、互いの戦闘能力値や技能、発言力といったパラメーターを高め合いつつ、恋や友情を育んだりできる育成・恋愛シミュレーション的な「学園モード」で過ごされる。AIの制御で自律的に行動するNPCたちはそれぞれプレイヤーと同等のコマンド選択肢をもち、あたかも誰か自分以外の他人が操作しているかのように振る舞う。いわば「擬似オンラインRPG」とでも言うべき仕様だ。
そうした「自由」な日常を寸断する非日常として来襲する「戦闘モード」には、ターン制の戦術級シミュレーションRPG(SRPG)的なシステムが採用されている。が、従来のSRPGとは異なり、操れるのは自分のキャラのユニットのみ。戦場にあってもAIの制御する戦友たちは、あくまで意思を持った他者として行動する。つまり、戦友たちとともにままならない状況の下に置かれるという限定的な視点を提示した。これは、ミクロなキャラの立場や心情に即した日本ゲームらしい思いの馳せ方を、マクロな視点から冷徹に戦況をモデル化する欧米のウォーゲーム的な原理に埋めこみ、レベルの異なる認識を接続する、新たな戦争表現の方法でもあった。
ゲームはこうした「日常」と「戦場」の繰り返しで進められるわけだが、両モードが緊密に連関し、自分の行動がほかのキャラクターとの関係や戦いを通じてマクロな状況を変え、そして自分にも跳ね返ってくるという生々しい手触りは、擬似オンラインRPG的な見立てをさらに超え、あたかもプレイヤーがプレステで稼働する『ガンパレ』という端末を通じて、別世界の〝もうひとつの現実〟にアクセスしているかのような錯覚さえもたらしたのだ。
グラフィックやサウンドなどの演出は、いかにも低予算のマイナーゲームといった体裁ながら、本作が実現した体験の圧倒的なコンティンジェンシー(偶然性)の高さと奥深さは、筋書きの定まった大作ゲームに倦んでいたコアなゲームファン層からの熱狂的な支持を獲得する。宣伝費がほぼゼロに近く、ほとんどの大手ゲームマスコミに存在を認知されない中、むしろその逆境がファン心理に火をつけ、口コミやネットでのボランタリーな〝布教〟を焚き付ける結果になったからだ。ちょうどインターネット上では、パソコン通信の会員制フォーラムなどで培われた文化がスライドするかたちで、より多くの人々が目にするテキストサイトやBBS(電子掲示板)にて口コミが広がる土壌が広がっていたため、既成のメディアによらないムーブメントに拍車をかけたのである。
つまりはゲームの内容と同様、大手メーカーやマスコミの定める意外性のないヒットの傾向に抗い、自分たち自身が発掘して育てたというプリミティブな高揚感を、期せずしてファンたちに提供することができた点が、本作のスマッシュヒットの特徴であった。
そして本作が際立っていたのは、こうしたゲームの内外で起こったプレイヤー主導型のムーブメントをさらにまなざし返すかたちで、開発者サイドが自社の公式サイトを利用して、常識的な広報宣伝サービスの範疇を超えた〝もうひとつのゲーム〟を仕掛けた点にある。
『ガンパレ』のゲーム中には、NPCたちの台詞やインターフェースの演出を通じて、ゲーム上で各キャラクターや世界観上の設定にまつわる「世界の謎」が、断片的にのみ示されるという仕込みがなされていた。これに対応して、公式サイト上にはファンの交流用などのBBSに加えて「世界の謎」専用の掲示板が設置され、本作のゲームデザイナーである芝村裕吏がユーザーからの質問にこまめに応答してゆく。「幻獣はなぜ人類を襲うのか?」「謎めいた台詞でプレイヤーに対して直接語りかけてくるあのキャラクターは何者か?」「この世界はループしているようだが、その真相は?」
日夜寄せられるそんな問いに対して、芝村は単純に回答するのではなく、巧みなヒント出しやはぐらかしによって、プレイヤーに自ら真相を考えさせる方向へと徐々に誘導。これに応答した一部プレイヤーたちとの間で、最終的には期日までに『ガンパレ』に仕掛けられた「七つの論理トラップ」なるお題への正解を言い当てさせる、ウェブ上でのライブ推論ゲームが展開されたのである。
この顛末で特筆すべきは、一見すると『ガンパレ』というゲームの外でユーザーコミュニケーション主導で起きた自然発生的なムーブメントに見えるこの「謎」ゲーム自体が、実はアーキテクトたる芝村が周到に仕掛けた「GPM23」なる儀式魔術であったというフィクショナルな見立てが施され、本作の世界観体系に組み入れられてしまったことである。すなわち「GPM23」とは、「現実世界と並行する〝実在の〟ガンパレード世界の仲間たちを救うために世界を渡ってきた男が、向こうの世界での出来事をモデルにしたゲーム『ガンパレ』を制作・発売。それを呼び水にプレイヤーたちの集合知をネット上で結集することで、その同一存在としてガンパレード世界に〝23人目のクラスメイト〟を発生させ、世界間干渉を行おうとした儀式魔術であった」というのが、「七つの論理トラップ」を突破した果てに小説形式で公式サイト上に公開されて明らかにされた、最終的な〝真相〟であった。まさにゲームで描かれる虚構とネット上でリアルタイムに進行した現実の出来事との垣根を取り払い、プレイヤーたち自身が「何をさせられていたのか」を自ら探求するという、他のメディアではなしえない究極のメタフィクションが実現していたわけである。
前章でみたように『moon』や『serial experiments lain』など、前世紀末にはゲーム機のインタラクティブなメディア特性を活かして虚実を曖昧化し、プレイヤーの存在自身を劇中に引きずりこむ自己言及的なメタフィクション構造をもったジャンル批評的なタイトルは、すでに複数登場していた。本作のケースが特異だったのは、その体験をパッケージゲーム内だけで完結させず、それをめぐるインターネット上での現実のユーザーコミュニケーションに拡張したことによって、よりメタフィクション表現としての徹底性が高まったことにある。
つまり、『moon』ならば「主人公の男の子がゲーム内ゲームの世界に落ちていく」という『はてしない物語』式の古典的な異世界ファンタジー様式のシナリオという、『lain』ならばプレイ中のゲーム機を劇中世界のネット端末に見立てるという、制作者側の用意した嘘をプレイヤーが受け入れる心理的な手心が加わることで、メタフィクションが成立していた。しかしながら「GPM23」における〝真相〟設定では、そうしたフィクショナルな見立てすら排し、「プレイヤーは(あたかも劇中世界に『lain』式にアクセスしているかのような諸々の演出的フェイクがあったのとは裏腹に)あくまでも『ガンパレ』というただのプレステ用のゲームソフトをプレイしていたに過ぎない」という、身も蓋もないリアリズムが貫徹されている。BBS上での「世界の謎」をめぐる議論自体も、同様にただのウェブ上でのコミュニケーション行為に過ぎない。
しかしそうでありながらも、原理的には存在するともしないとも言い切れない感知不可能な〝もうひとつの現実〟の世界で生きる、劇中キャラのモデルになった〝本物〟の仲間たちについては、彼らを実在の人間のように愛した『ガンパレ』ファンたちによる熱狂的ムーブメントのおかげで助けられたかもしれない。そんなプレイヤー個々の心理には依存しない手心抜きの「論理的可能性」を、きわめて展開自由度の高いスタンドアローンゲームと集合的なネットコミュニケーションの併せ技によって、芝村は(入り組んだ世界法則の議論についてこれた人々に対しては)納得的に示してみせたのである。
【ここから先はPLANETSチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は5月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201505
-
「国民的RPG」シリーズが迎えた曲がり角〜『FFX』『キングダムハーツ』『ドラクエVIII』(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.315 ☆
2015-05-01 17:30【お詫び】本日配信の「ほぼ日刊惑星開発委員会」ですが、編集作業に時間がかかってしまい、今朝の午前7時に配信することができませんでした。楽しみにしていただいていた読者の皆様、大変申し訳ございませんでした。さきほどより配信・公開いたしましたので、ぜひ、ご覧ください。今後ともPLANETSのメルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」を楽しみにしていただけますと幸いです。
※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
「国民的RPG」シリーズが迎えた曲がり角〜『FFX』『キングダムハーツ』『ドラクエVIII』(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.5.1 vol.315
http://wakusei2nd.com
本日は、隔週掲載となった「中川大地の現代ゲーム全史」最新回をお届けします。PS2が登場した2000年代前半、『FF』『ドラクエ』という二大タイトルはどのように変わっていったのか? 北米市場との関係、オンラインゲーム化や表現手法の変化のゲーム史的位置付けを考えていきます。
「中川大地の現代ゲーム全史」
第9章 和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業
2000年代前半:〈仮想現実の時代〉終期(4)
前回までの連載はこちらのリンクから。
■『FFⅩ』の到達点と北米圏へのハイブリッド・アプローチ
一方の『FF』シリーズもまた、『ドラクエVII』とは別の意味で臨界を迎えつつあった。プレステ移行ののちはリリーステンポがさらに上がり、『VII』『VIII』『IX』とほぼ毎年のようにナンバリングタイトルが発売されていった勢いは衰えずにプレステ2にも流れ込み、ハード発売の翌01年という最適なタイミングで『X』が発売されるに至る。
▲『ファイナルファンタジーX』スクウェア、2001年
プレステの命運を決定づけた『VII』の制作陣が手がけた『X』は、プレイヤーと主人公とを演出的になるべく一致させようとする「自分の物語」志向の『ドラクエ』シリーズとは対照的に、「他人の物語」に寄り添わせるシリーズ特有の手法をさらに洗練させていく。
『Ⅶ』では主人公クラウドが、プレイヤーに隠された過去の記憶が物語中盤で暴かれていくというかたちで、「自分自身が知らない主人公の秘密」を探求するシナリオ構造を特徴としていたが、『X』では主人公ティーダがいきなり物語冒頭で元いたザナルカンドの世界から別の世界スピラに飛ばされるという構造で、プレイヤーにとって未知の世界を旅するという立場を重ね合わせた。シリーズで初めて声優による台詞芝居が導入され、状況への心象を語る主人公のモノローグが多用される演出が採られたこともまた、元の世界とは異なるルールが支配する異世界への戸惑いや、出会った仲間たちとは共有できない心情をプレイヤーにだけ伝える効果を生んだ。
こうしてプレイヤーの立場をティーダという独自の内面を抱える主人公に寄り添わせる一方で、ティーダには旅の能動的な主体者ではなく、スピラ世界を悩ませる自然災害に似た脅威である「シン」を調伏する使命を負った大召喚士を目指すヒロイン・ユウナのガード役という従者の立場が与えられ、異世界人の立場で事件を観察していく視点を得ることになる。これにより、一本道のシナリオを歩まされる立場をストレスにせず、むしろ主人公の心情にプレイヤーを二重の意味で同期させて臨場感を高めるストーリーテリングに昇華させた点は、本作が見せた円熟味であった。
かくして、「異世界人であるティーダだけが知らないスピラの悲しい理」として、歴代の大召喚士にはシンを完全に倒すことはできず、自らの命を捧げる究極召喚によって数年から数十年単位でのシンの不活動期間である「ナギ節」を得られるばかりであるという真相が、物語中盤でティーダに知らしめられることになる。善悪を超越した仏教的な生老病死の象徴とも言えるようなシンの存在感や、その対処のための循環的な人身御供の必要性を説くエボン教の設定など、ここで示されるアジア的・民俗学的な世界観は、従来のRPGで表現されてきた文芸性の水準を大きく超え出るものだ。
その上で、シナリオはティーダとユウナの恋愛を描きつつ、シンによる死と破壊への一定の諦念を説くエボンの因習を克服し、シンの完全打倒を目指すという近代的な解決の模索へと導かれていく。そしてそのための道を探る主体として、それまで状況の客体だった異世界人ティーダが物語を牽引する立場になるのに加え、彼の出自をめぐる謎がクローズアップされていき、最終的には「相手を慮って真実を隠しながら自らが犠牲になる」側が入れ替わるという作劇で、悲恋と世界の救済を儚く描ききるものになる。
元々の『FF』シリーズの作品性は、海外RPGのシステムやハイファンタジーの意匠題材のうちから『ドラクエ』が採り入れていない先進的な要素の先取りを重ねつつ、1980年代以降の日本アニメや少年漫画などの作劇パターンを採り入れていくというパッチワークの積み重ねによって進歩してきた。ここで『Ⅹ』に至っては、シリーズを通じてのテーマやモチーフをアレンジして突き詰めていくうち、RPGという語りの様式と作劇内容とが高度に調和させた、日本発のオリジナル・ファンタジーとしての、ひとまずの到達点に達したと言ってよいだろう。
そして『VII』以来、3DCGによるムービー演出を追求してきた『FF』の攻勢は、ついに純粋な映像作品の制作にまで至る。『X』発売後の01年中に、シリーズ産みの親である坂口博信を監督に、フルCG映画『ファイナルファンタジー』を日米で公開。ピクサーが1995年の『トイ・ストーリー』を公開して以来、アニメーション映画のカテゴリーではフルCG作品が登場していたが、生身の人間の役者を置き換える質感での実写的なフルCG映画は、世界初の試みであった。
それまでの邦画では、高度な特殊効果(SFX)を活用したスペクタクルなハリウッド映画のような表現をどうしても技術的・予算的に実現することができず、日本映画の積年のコンプレックスであり続けてきた。しかしゲーム作品のムービーCGによって、プレステ時代には『バイオハザード』や『メタルギアソリッド』シリーズのような〝和製洋画〟とも呼べる表現が成立していた。このスタイルの延長線上に、フルCGでならば役者の人種の壁も超えることができるし、本当に日本発で成立するハリウッド映画が作れるのではないか。そうした蛮勇を実行に移したのが、ファミコン時代から「映画的」な表現を追求してきた『FF』シリーズだったわけである。
しかしながら、その意気込みとは裏腹に、過去の『FF』から星の生命エネルギーやシドという人物名といったモチーフを再構築しつつ、地球外生命体との戦いを描くSF作品として制作された映画『ファイナルファンタジー』は、記録的な興行的失敗を遂げることになる。先行する〝和製洋画〟系のゲーム作品と同様、本作はアメリカ映画的な見かけの質感のもと、日本アニメ的なキャラクター表現やストーリーテリングを盛り込んだものとなったが、それが中途半端なパッチワークに終始したためだ。
基本設定を描写しきれない構成の失敗や、最終的に『ナウシカ』『マクロス』など1980年代に流行したエコロジカルな平和主義的解決に落とすなどの未成熟なシナリオは、ハリウッド映画の工学的に構築されたエンターテインメントの快楽原則の域に遠く及ばず、日本ゲームの挑戦は夢と終わる。奇しくもアメリカと日本での公開の合間の時期に9.11テロが起こったことは、本作が描いた価値観の無効を残酷に宣告するかのようでもあった。
結局のところ、この映画の興行的失敗が響き、スクウェアはエニックスとの合併を余儀なくされるのである。
▲FINAL FANTASY ― ファイナルファンタジー ― (スタンダード・エディション) [DVD]ミン・ナ (出演), アレック・ボールドウィン (出演), 坂口博信 (監督)
映画でこそ失敗した『FF』だったが、翌02年、スクウェアはアメリカ文化との融合を図る、また別のアプローチを行っていた。アメリカのキャラクタービジネスの雄であり、日本産コンテンツの古くからの範でもある、ディズニーキャラクターとのコラボレーションを成し遂げた3DアクションRPG『キングダムハーツ』であった。版権管理のハードルがきわめて高いディズニーだが、本作ではドナルド・ダックやグーフィーといったキャラクターたちが、野村哲也デザインのオリジナルキャラクターや『FFVII』のゲストキャラクター陣と共演し、『FF』的なトーンの複雑でシリアスな世界の危機に立ち向かうという、シュールないでたちのハイブリッドが実現。北米市場でも成功を果たし、人気シリーズ化していくことになる。
これは『FF』ブランドの世界展開にとってみれば、映画での失敗を返上し、アメリカ的なキャラクター意匠を拝借しながら日本的なストーリーテリングの中に活かす手法が奏効したケースだと言えるだろう。
▲『KINGDOM HEARTS(キングダム ハーツ)』スクウェア、2002年
■『FF』『ドラクエ』の大転換
一方、『FF』ナンバリングタイトルのリリース・ペーストは衰えることなく、同じく02年には、シリーズ初のオンライン対応タイトルとなる『Ⅺ』が発売される。ちょうどアメリカの元祖二大RPGシリーズとして『ウィザードリィ』と双璧をなす存在だった『ウルティマ』がMMO−RPGの時代を切り拓いていったのと同様、コンシューマー機で発売される初の本格的な大人数同時参加型のオンラインRPGとしての役割を、『ドラクエ』に先んじて果たすことになる。
【ここから先はPLANETSチャンネル会員限定!】 ▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は5月も厳選された記事を多数配信予定です。
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201505
-
任天堂ハードと「ドラクエ」が挑んだ“古き良きゲーム”の再定義〜『ピクミン』『逆転裁判』『ドラクエVII』(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.304 ☆
2015-04-15 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
任天堂ハードと「ドラクエ」が挑んだ“古き良きゲーム”の再定義〜『ピクミン』『逆転裁判』『ドラクエVII』(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.4.15 vol.304
http://wakusei2nd.com
本日は、月2回掲載となった「中川大地の現代ゲーム全史」最新回をお届けします! PS2、ドリキャス、Xboxなど次世代ゲームハードが次々に投入されるなか、かつての「王者」任天堂やドラクエのフィールドでは様々な試行錯誤が行われていました。「ゲームキューブ」「ゲームボーイアドバンス」、そしてプレステで発売された『ドラクエVII』――そのゲーム史的な位置付けとは?
「中川大地の現代ゲーム全史」
第9章 和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業
2000年代前半:〈仮想現実の時代〉終期(3)
前回までの連載はこちらのリンクから。
■ ゲームボーイアドバンスとゲームキューブの明暗〜任天堂ハードが継承したニッチ
国産技術によってゲーム市場を踏み台に総合情報家電のグローバルスタンダードの奪取を狙ったのがSCEのプレステ2、現行のグローバルスタンダード技術に乗りながら日本ローカルなゲーム市場への侵蝕を試みたのがマイクロソフトによるドリキャスのOS提供からXbox投入への流れだったとすれば、徹底して日本独自の“ゲーム屋”としてのローカリティを貫き通す役割を担うに至ったのが、任天堂だということになるだろう。
同社は2001年、ゲームボーイ以来の実に12年ぶの本格的な携帯ゲーム機の更新にあたる「ゲームボーイアドバンス(GBA)」、およびNINTENDO64の後継となる据え置き機「ニンテンドーゲームキューブ(GC)」を相次いで発売する。
▲ゲームキューブ(任天堂、2001年)
まず、シェア競争上の結論から言えば、プレステやサターンに遅れたN64と同様、同世代機であるプレステ2から1年以上ものラグを挟んで登場したGCは、劣勢を覆すことができなかった。ついにROMカートリッジを捨てて任天堂として初めて光学メディアを採用し、その名の通り正方形状のスタイリッシュな筐体デザインによって従来の「玩具」的なイメージからの脱却を図ったGCの基本的な仕様は、プレステ以降のIT家電的な傾向に近づけるものではあった。しかしながら、採用メディアが容量の少ない8cm径の独自規格ディスクであったり、AVラックに納まるようなフラット感よりもSF的な異物感を追求したりなど、あえて機能的合理性に抗ってでもアイテムとしての差別化を残そうとしたため、どちらつかずの中途半端な設計思想が普及の枷になったのは明らかだった。
加えて、ローンチタイトルとしては、本機の3Dグラフィックス性能による波の表現力をプレゼンしようとした水上バイクのレースゲーム『ウェーブレース ブルーストーム』や、コントローラーの左右両方に独自のレイアウトで配置されたアナログスティックを駆使するアクションアドベンチャー『ルイージマンション』といった自社製タイトルがリリースされたものの、GCならではの個性を打ち出せたとは言い難い。『ウェーブレース』は世に数多ある3Dレースゲームの一バリエーションに過ぎなかったし、『ルイージマンション』が要求した操作性も、本質的には例えばプレステ2のDual Shockコントローラーでも実現できるものだ。
つまりは、最初の看板になったタイトルがマリオではなくルイージであったという点に象徴されるように、本質的な部分でのイノベーショナルな特色の希薄さを、変化球的なパッケージングでカバーしようという性格が、歴代任天堂ハードの中でも目立つ機体となったのである。
そのぶん、業界全体にとってのインパクトとして大きかったのは、GBAの方だったと言えるだろう。携帯ゲーム機市場では、長らくマイナーバージョンアップを重ねて確固たる地歩が築かれてきたゲームボーイシリーズに対して、バンダイのワンダースワンなどが挑戦を仕掛けてはいたものの、任天堂の先行者優位には遠く及ばない状況にあった。したがって図式的には、ちょうどファミコンがPCエンジンなど他社の新鋭機の追随を許さないうちにスーパーファミコンへと順当な代替わりが行われた際の市場環境に近い。初期のモデルでは、旧ゲームボーイのゲームソフトも遊べる下位互換性を持っていたことも幸いし、GBAは携帯ゲーム機の標準を継承していくことになる。
立ち位置の面だけでなく、機体性能の面でもスーファミの延長線上にある2Dドットグラフィックの描画が可能だったGBAは、高度な3DCGが主流となった据え置き機でのゲーム開発に、資金的・技術的についていけなくなったディベロッパーにとっての受け皿となることができた。これにより、GBAはGCを大きく上回るサードパーティーの参入を得ることになり、発売タイトル数の上で携帯型ゲーム機が据え置き型ゲーム機を上回っていく状況へのターニングポイントとなったのである。
このようにハードとしてのシェア獲得上は明暗が分かれたと言えるGBAとGCだが、ソフトのラインナップの面では、『ポケットモンスター サファイア/ルビー』や『大乱闘スマッシュブラザーズDX』『どうぶつの森+』など、どちらもほぼ既存の人気シリーズの続編や移植・リメイクが多くを占めた。つまりは、低年齢層・ファミリー層向けに特化する方向に向かったN64時代のニッチを守ることはできたものの、のちのゲームシーンの流れを作るような革新的なタイトルの産出には乏しかったと言える。
その中でも、ゲームデザイン面で出色だったタイトルとしては、GCでは物悲しいCMソングとともに話題を呼んだ群体AIアクション『ピクミン』(任天堂 2001年)が挙げられるだろう。最大100匹集めることができる奇妙な小生物ピクミンたちを率いて、アイテム回収などを目的とするステージ攻略を成し遂げてゆく中で、彼らが集団的に甲斐甲斐しく動き回ったり、儚く敵の原生生物に捕食されたりするさまが感興を呼ぶ体験性は、他に類を見ないユニークさが際立っていた。
▲『ピクミン』(任天堂、2001年)
また、歴代任天堂ハードにおけるキラーソフトとなる『ゼルダの伝説』シリーズでは、『ゼルダの伝説 風のタクト』が投入されている。本作はポリゴン描画されたキャラクターにトゥーンレンダリングを施し、3DアクションRPGとしての完成形を示したN64時代の『時のオカリナ』『ムジュラの仮面』とは一線を画する、絵本のようなビジュアルを追求。さらには海洋のフィールドを主舞台に、風の流れを駆使したアクションを特色とするなど、シリーズ中でも異色のテイストを放つタイトルとなった。
ただし、これらのアイディアが光るタイトルも、任天堂ゲームらしい「王道」感よりは目先を変えた変化球としての印象が強く、スタイリッシュな方向と子供向けの玩具的な方向とが相半ばするGCというハードの中途半端さを上書きする結果になったとも言えるだろう。
一方、過去の名作シリーズの移植やスピンオフ作品などが目立っていたGBAのラインナップだが、後代に続くオリジナル人気シリーズの創始となったのが、カプコン発売の『逆転裁判』(2001年)だ。新米弁護士・成歩堂龍一を主人公に、殺人事件で無実の罪を着せられた被告人たちを、その名の通り裁判で真犯人を暴き立てることで救い出していくという趣向の擬似法廷バトルである。
▲『逆転裁判』(カプコン、2001年)
据え置き機では3DCGによる大作ゲームが全盛の中で、本作は本質的には、ドット絵とテキストで表現される一本道のストーリーをコマンド選択で進めていくという、昔ながらのローテクな推理AVGに過ぎない。しかしながら、関係者への聞き込みや証拠品の収集を行う「探偵パート」と、そこで得た証拠品や情報を証言台に立つ証人たちに突きつけながら尋問を進めていく「法廷パート」とにモードを分け、後者の裁判シーンではケレン味あふれるテンポよい演出証人やライバル検事との丁々発止の言論戦を行うという趣向のインタラクションの工夫を施すことで、まるでRPGのバトルシーンのようなカタルシスが発生。登場人物たちのキャラクターも、ちょうどカプコンが得意としてきた対戦格闘ゲームのように極端に戯画化した造形にすることで、非日常的な快楽性を高めることに寄与した。
こうしたシナリオやキャラクターデザインやシステム演出の調和に加え、掌の上の携帯ゲーム機の小さな画面上で展開されるというチープ感も含めて、裁判中に真犯人が判明して劇的な逆転判決が起こるという荒唐無稽な世界観を違和感なく堪能させることができたのが、本作の白眉であった。
もちろん、GBAの携帯型ゲーム機としてのハードウェア特性そのものが、たとえば『ポケモン』のようなゲームの登場をもたらしたような意味では、『逆転裁判』の作品性にとって必須だったわけではない。実際、本作の体験版が公式サイトのFLASHコンテンツとしてプレイできたように、ゲーム内容自体としては、例えば当時のPCブラウザなど他のプラットフォーム手段でも、決して実現できないものではなかったからだ。
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は4月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201504
-
ドリームキャストの遺産とは〜『シェンムー』『クレイジータクシー』『PSO』(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.294 ☆
2015-04-01 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
ドリームキャストの遺産とは〜『シェンムー』『クレイジータクシー』『PSO』(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.4.1 vol.294
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、月2回連載となった「中川大地の現代ゲーム全史」! 今回のテーマは、「ドリームキャスト」――。あの幻の(?)ハードは、のちのゲーム文化に何を残したのか。当時のハードウェア事情や、『シェンムー』『クレイジータクシー』『スペースチャンネル5』『ファンタシースターオンライン』といった名作タイトルから振り返ります。
「中川大地の現代ゲーム全史」
第9章 和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業
2000年代前半:〈仮想現実の時代〉終期(2)
前回までの連載はこちらのリンクから。
■ プレステ2が推進した「家電」化と「ゲーム離れ」
かつてスーパーファミコンが「国民機」ファミコンの地位を継承したのと同様、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が2000年に投入したプレイステーション2もまた、前世代のトップシェアを握ったプレステとの後方互換性を保った後継機として、順当にその覇権を継承した。
ただしその内実には、プレステ発売当時とのIT環境の違いに応じた、小さからぬ戦略の違いがあった。まだWindows95の登場以前、パソコン等でもCD−ROMメディアの普及期だったプレステの時代には、3DO REALが「マルチメディア機」としての性格を強調しすぎて没落したように、あくまで「ゲーム機」であることを強調することが市場の理解を得るための上策だった。
しかし、Windows登場以降、もはや「マルチメディア」がわざわざ言挙げするまでもない自明の機能として死語化し、パソコンという汎用機の体験は当たり前のものになっていた。四半期ごとにCPUやハードディスク、メモリの数値や搭載する光学メディアなどがスペックアップし、各メーカーのニューモデルが競って家電量販店を賑わせるといった光景が常態化することで、デジタル機器に対する消費者リテラシーも格段に向上する。
そうなると、今度はゲーム専用機が、むしろパソコンの隣接カテゴリーの製品として対比されることの避けられない市場環境が生まれていた。
この状況に対して、SCEは日本を代表する家電ブランドであるソニー・グループとしての総合性を活かすかたちで、世界コンピューター市場に君臨するウィンテル連合への真っ向からの挑戦の道を選択する。プレステの成功でグループ内での存在感を高めた久夛良木健社長の主導のもと、SCEはプレステ2向けに1300億円もの巨費を投じて、東芝との共同で世界初の完全な128ビットプロセッサである「Emotion Engine(EE)」およびGPU「Graphics Synthesizer(GS)」を開発。ゲーム機のCPUといえば、最先端からすれば枯れた仕様の汎用プロセッサをカスタマイズする場合が一般的だったが、同時代のハイエンドパソコンなどを凌駕するピーク性能をもった独自プロセッサを一から作り上げるという、異例の試みがなされたのである。
▲PS2内に組み込まれた「Emotion Engine(EE)」と「Graphics Synthesizer(GS)」
その試みの底にあったのは、EEやGSをワークステーションやAV機器などの共通コアとして搭載して連携可能にし、来たるべきデジタル家電の統合的なホームネットワークの時代の覇権を握るための布石にしようという久夛良木の構想であった。したがって、プレステ2はUSBやIEEE1394(iLink)といった汎用インターフェースを備え、筐体も縦置き・横置きの両様に設置できるというパソコン的な設計がなされ、将来的なメディアネットワーク端末としての拡張も視野に入れた含みが持たされていた。
なお、このように自社ブランドの様々な機器の連携によって総合デジタル家電プラットフォームを築こうという構想は、プレステ2の翌01年、スティーブ・ジョブズ率いる米アップルがMacintoshのメディアファイル再生ソフト「iTunes」と連携する最初の「iPod」を発売し、かつてソニーが世界を席巻した「ウォークマン」の歴史を塗り変えるかのように携帯型デジタル音楽プレイヤーの市場を開拓したことで、急速に現実化への途を歩んでいくことになる。この時点においては、ともにウィンテル体制への挑戦者であるソニーとアップルが、互いにライバルシップをもって同じようなビジネスモデルの構築を目指し、それぞれの得意分野からの尖兵として、プレステ2なりiPodなりを投入していたわけだ。
プレステ2が持っていたデジタル家電化に向けての具体的な仕様として、最も端的な特徴が、対応メディアにDVD−ROMを採用し、DVDビデオの映像再生機能を持っていたことである。
すでにCD−ROM搭載のプレステ時代から、大作ゲームの多くはディスク何枚組ものデータ容量に達していたので、新たな大容量メディアを採用すること自体は当然の漸進的スペックアップであったが、まだパソコン用の光学メディアへの採用もハイエンド機種に限られ、専用のDVDプレイヤーやレコーダーが非常に高額だったタイミングで投入されたことが、プレステ2の存在を特権的なものにした。実売4万円弱という本機の価格は、他のDVD再生手段に比べて段違いに安く、むしろDVDビデオそのものの普及を世界的に推進する役割をすら担うことになったためである。
この意味で、iPodが音楽ソフトの脱CD化の先鞭をつけたとするならば、プレステ2は映像ソフトの脱VHS化という、コンテンツ供給メディアの切り替えのキー製品となることで、アップルとSCEはそれぞれのAVメディア統合戦略の実現に向けての足がかりを確保したのだと言える。
▲iPod(初代)
このようにプレステ2は、ゲーム機であるがゆえの構成のシンプルさと、覇権機プレステの資産をそのまま包摂するスケールメリットによって「最安値のDVDプレイヤー」としての成功を獲得したわけだが、それは反面、本来のゲーム機としての魅力を希薄化してしまう特徴でもあった。
とりわけ発売当初に関しては、ローンチソフトのラインナップが『リッジレーサーV』や『ストリートファイターEX3』など、多くの消費者にとって真新しさを感じさせない既存シリーズの続編が中心で、これといったキラータイトルがしばらく登場しなかったため、「プレステ2は買ったけれどもDVDしか観ていない」といった声が少なからず見受けられた。つまり、ゲームソフトの送り手と受け手の立場からすれば、ゲームジャンル内だけでなく映画やアニメといった映像コンテンツとの直接的な競争を同一ハード上で強いられる厳しい状況の発生に他ならなかった。
加えて、プレステ2の心臓部に採用されたEEやGSといった独自開発のチップは、スペック通りのピーク性能を発揮させることが難しく、ゲームソフトの開発者にとっては高い技術的・資金的ハードルとなった。前節で述べた国産ゲーム市場全体の縮小傾向もあり、プレステ2の仕様は、体力のないディベロッパーに対しての淘汰圧を強めるものでもあったのだ。
結果としてプレステ2は、「デジタル家電」ハードとしての成功とは裏腹に、相対的にソフト面では業界に「ゲーム離れ」への懸念を喚起するという、日本ゲーム市場の皮肉な時代環境を象徴する製品として普及していったのである。
■ ドリキャスが遺したもの1〜早すぎたオープンワールドとしての『シェンムー』
ドリームキャストというハードが辿った足跡を簡潔に言い表すとしたら、それは「フライング」の一語に尽きるだろう。
前章でも触れたように、プレステ2の機先を制すべく1998年末という早期の世代交代を敢行したドリキャスの青写真は、インターネットへのダイヤルアップ接続用のモデムを標準搭載し、来たるべきオンラインゲームの時代を見越してスタートダッシュをかけて普及を図ろうという電撃戦的な展開にあった。そのために、基本的にはマニアハードとしてのイメージを引きずる歴代セガハードの中で、最も国内市場でトップシェアに近づいたセガサターンの地歩を守りつつ、さらにプレステ並みのポピュラリティを獲得しようという姿勢を全面に打ち出すPRを特徴としていた。その最たる展開が、セガの実際の役員である「湯川専務」を起用したCMシリーズであろう。ここでは、子供たちが「セガなんてダッセエよな」「帰ってプレステやろう」などと囃し立てる逆風の中で、冴えない風貌の湯川専務が哀愁を漂わせながらドリキャス販促に務めるという思いきった自虐表現が採用され、大いに話題を呼んだ。
▲ドリームキャスト
▲湯川専務の顔があしらわれたドリームキャストのパッケージ
秋元康のプロデュースによるこのCMの方向性は、かつてプレステが覇権を獲得していく過程で、ゲームそのものの内容を告知するのではなく、ゲームの遊ぶ人々の反応やライフスタイルをキャッチーに活写するスタイルの宣伝展開が奏効したことを踏襲している。その上で、主流となったプレステの小洒落たスタイリッシュさとの差別化として、シェア争いにおけるセガの苦境と捨て身の姿勢を自らネタにすることで、サターン時代のPRキャラ「せがた三四郎」以上にコミカルで脱力した親しみやすいイメージを確立。キモかわいさを狙った人面魚育成タイトル『シーマン』のヒットとも相まって、歴代ハードの中で最もライトユーザー向けの認知を得ることには成功していたと言える。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は4月も厳選された記事を多数配信予定!
配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201504
-
「プレステ2」「Xbox」が告げる〈仮想現実の時代〉の終焉(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.280 ☆
2015-03-12 08:10【お詫び】本日配信の「ほぼ日刊惑星開発委員会」ですが、編集作業に時間がかかってしまい、今朝の午前7時に配信することができませんでした。楽しみにしていただいていた読者の皆様、大変申し訳ございませんでした。さきほどより配信・公開いたしましたので、ぜひ、ご覧ください。今後ともPLANETSのメルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」を楽しみにしていただけますと幸いです。
※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
「プレステ2」「Xbox」が告げる〈仮想現実の時代〉の終焉(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.12 vol.280
http://wakusei2nd.com
好評の大河連載『中川大地の現代ゲーム全史』は今月よりペースアップし、月2回配信でお届けします! 今回は新章となる第9章「和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業」のプロローグです。2000年前後のIT革命、Xboxの登場などグローバル化の荒波のなかで、日本のゲーム産業はどう変わっていったのでしょうか――?
「中川大地の現代ゲーム全史」
第9章 和ゲー成長期の終わり/二極化してゆくゲーム産業
2000年代前半:〈仮想現実の時代〉終期(1)
前回までの連載はこちらのリンクから。
■〈夢の欠片〉としての日本ゲームの終焉
かつて宇宙開発への期待が人類のテクノロジカルな進歩の中核を担っていた〈夢の時代〉、2000年や21世紀といった数字は、そのままSF的な「未来」の世界観を表象する記号に他ならなかった。第二次世界大戦後の経済成長によって、1950〜80年代あたりを生きた先進国の人々は、その時点までの数十年間のスパンの間に、未曾有の科学技術の発展が人類の文明生活を一変させるさまを経験した。そして、その進歩のビフォー/アフターの落差が、ますます拡がりながら未来の時間軸にも折り返されてゆくと信じたのだ。それゆえ、アーサー・C・クラークの『2001年宇宙の旅』に代表されるように、たかだか半世紀以内の間に人類が宇宙へと生活圏を広げたり、意識を持つ人工知能が人類に哲学的な問いをもたらりする、見果てぬ〈夢〉が実現されているはずの「現代」からは飛躍した年代として、2000年代は想像されていた。
そんな想像力が影響してか、メモリ容量の少ないコンピューター黎明期に制作されたプログラムでは、年号処理が2000年以降の使用を想定してしていなかった。したがって、現実の2000年のテクノロジーをめぐっては、様々な情報処理システムが同年になると誤動作を起こすかもしれないという「2000年問題」への懸念が、世界を騒がせるに至った。言うなれば、かつて人々がイマジナリーに抱かれていた00年代の技術への〈夢〉と、現実の〝進歩の遅さ〟との齟齬を示す事象として起こったのが、2000年問題だったと言えるだろう。
第4章までに論じてきていたように、コンピューターゲームとは、テクノロジーの系譜としては、元々は宇宙開発に代表される巨大科学への〈夢〉がハッキングされ、パーソナルな体験の提供物へと解体・民主化されていく過程の徒花として生まれた〈夢の欠片〉とも言える技術産物だ。それゆえ、2000年問題で〈夢〉の頓挫が露呈したのと同様、2000年代前半は、世界の最先端を切り拓いてきた日本ゲームの進歩が、ひとまずの頭打ちを迎えた時代だったと言える。
1980〜90年代にかけては、家庭用ゲームの代替わりに駆動されるかたちで、絶えず新たなゲームジャンルが生み出されてきた。しかし90年代後半にポリゴン表現を用いたゲームのカンブリア爆発的な試行錯誤を経て一通りの文法化がなされたことで、据え置き型ゲーム機でプレイできるゲームデザインの破壊的イノベーションは一段落を迎える。以後は3D空間内のアクションをゲームパッドでいかにコントロールするかという基本的な操作系を一定程度規格化しつつ、主にはハードの更新にともなうポリゴングラフィックの高精細化のような漸進的なイノベーションの段階に入ってゆく。
加えて、右肩上がりの成長を続けてきた国内の家庭用ゲーム市場もまた、1998年を境に縮小に転じていた。内容面のみならず市場規模のうえでも、日本ゲームは高度成長期を終え、バブル崩壊後の経済全体の傾向から10年ほど遅れて下降線を辿り始めていたのである。
その一方で、ゲームと同じく宇宙開発に端を発するもうひとつの技術系譜であったインターネットの急激な普及は、いよいよ時代のモードを変えつつあった。ADSLなど常時接続型の安価なブロードバンド環境も整えられたことで、結局、2000年問題によってもいささかも水差されることなく、IT革命は進行。もはや情報技術が一部の専門家や好事家のフェティッシュの具ではなく、誰もが仕事や生活で日常的に扱う実用インフラとなったことこそ、この時代のゲームにとっての最も重大な環境的前提に他ならない。
なぜならこの変化によって、遊戯の体験を通じて一般家庭に先端的なテクノロジーの息吹をもたらすという、ファミコン以降のテレビゲーム機が担い続けてきたフラッグシップとしての役割が、完全に終焉を迎えてしまったからだ。GUIを備えたパソコンや、1999年に「iモード」をはじめとするネットサービスも始まった携帯電話といった実用機器で、様々なアプリケーションをクリックひとつで使えたり、WWWのサイバースペースを際限なくネットサーフできたりする環境が自明化したことは、コンピューターゲームが〈仮想現実〉として先行提供してきたテクノロジー体験が、同質の生活現実によって追いつかれてしまったことを意味していた。のみならず、人々の可処分時間や金銭を費やす遊戯性の体験としても直接的に競合し、ゲーム市場縮小の一因となった側面さえ否定できない。
つまりは、宇宙開発の〈夢の欠片〉として始まり、「ここではないどこか」の体験を創り続けてきたスタンドアローンゲームの体現する〈仮想現実の時代〉のひとまずの終焉期として、00年代前半は位置づけられるだろう。
具体的な状況としては、据え置き型ゲーム機のハード性能の進歩による3Dグラフィックスの要求クオリティの高まりや投資金額が高額化し、商業的なゲーム開発が大規模化してきたことの影響が大きい。とりわけ、市場を制するゲーム機が00年発売の「プレイステーション2」へと代替わりしたことが決定打となって、体力のある大規模ベンダーしか市場に残れなくなってきた。
▲プレイステーション2(ソニー・コンピュータエンタテインメント)
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
『ひぐらしのなく頃に』が到達したところ――「共同性」と「公共性」の相克の果てに(中川大地) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.276 ☆
2015-03-06 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
『ひぐらしのなく頃に』が到達したところ――「共同性」と「公共性」の相克の果てに(中川大地)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.3.6 vol.276
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは、『現代ゲーム全史』連載中の中川大地による『ひぐらしのなく頃に』論のお蔵出しです。のちの「カゲロウプロジェクト」や「ダンガンロンパ」シリーズ、『僕だけがいない街』(「マンガ大賞2014」2位作品)など、10年代のヒットコンテンツにも大きな影響を与えたと言われる「ひぐらし」。当時としては珍しく、同人作品から出発しアニメ化など多数のメディアミックス展開も行なわれたこの作品のインパクトを改めて振り返ります。
初出:『パンドラvol.3』講談社BOX、2009年
「中川大地の現代ゲーム全史」これまでの連載はこちらのリンクから。
■はじめに〜「放送中止騒動」から考える
2007年9月、京都府京田辺市で16歳の少女が手斧で父親を殺害した事件の発生を機に、当時放映中だったアニメ版『ひぐらしのなく頃に解』に対し、作中の残酷な描写が事件を連想させることなどを理由に、いくつかの放送局で打ち切りや放送自粛の措置が執られた。これを受け、同時期のアニメ『School Days』の最終回放送中止と並んでそれなりに物議を醸したことは記憶に新しい。
もちろん、そのこと自体はアニメやゲームに限らず、その時代時代のサブカルチャー表現が事あるたびに陥ってきた、凡庸なトラブルの一つでしかない。事件と『ひぐらし』に直接的な影響関係などないことが公判の経緯からも明らかであったのは案の定であったし、逆に「何か犯罪があればすぐアニメやゲームをスケープゴートにするマスコミの偏向報道」に憤り、自分たちの愛好ジャンルが置かれている不当な地位の低さを受動的に嘆くオタク側の論調も旧態依然としたもので、取り立てて新たな状況や議論の深まりをもたらすものでなかったことは、今となっては明らかである。
というよりも、世間なんていうのは、そんなものだ。もし『ひぐらし』ファンとして、あの騒ぎでの作品の扱いに不当さを感じ、つい“公憤”めいたものを抱いてしまった人がいたとしたら、逆に自分が興味も利害関係もないローカルな領域の社会的事象について、いかに自分が無理解な「世間」の一部としてしか存在しえないかに思いを馳せてみたらいい。
ただ、一見あまり幸福でないこの“接触事故”が逆説的に示しているのは、02年の夏コミでの原作ゲーム発売以来、基本的にはコアなオタク的感性の極致にあるところから始まり発展していった『ひぐらし』のメディアミックス展開が、見知らぬ世間のまなざしに出会えるだけの広がりの獲得に成功していたという事実だ。だからこそ、あの時点において、『ひぐらし』は一部ファンダムの島宇宙内で評価される狭い共同性の範囲を超え、「中高生への悪影響を懸念される」だけの資格を得はじめていたのだとも言える。
つまり07年の騒動は、『ひぐらし』ムーブメントが、ある意味では社会的な責任を問われるまでの成熟を遂げた、ささやかなメルクマールとしてあったと思ってみるのも、一つの手だと思う。
実際、騒動を受けたあるネットインタビューで、原作者の竜騎士07はこんなことを語っている。
「自分たちの作品はメッセージがくどすぎる、メッセージ性が強すぎる、と言われることが多いんです。批評家の方々にも、「道徳の本じゃないんだから、価値観を強く押し付けるな」と怒られてきた。でも、今回のことで思ったのは、くどいと言われても自分なりのメッセージを書き切ってよかったと思います。京都の子がもし『ひぐらし』をプレイしてくれたら、今回の事件は起こす前に、それが正しい行為であるか考えてくれたのでないかと思うことがあります。」(『OhmyNews』07年11月9日記事「[ひぐらしのなく頃に解]放送中止騒動 竜騎士07さんインタビュー(中)」より)
説教上等……!
生真面目なこの原作者は、ゲームやアニメの立場の弱さを糾弾する前に、無理解・無関心な世間なり社会なりと本気で切り結ぶためには、たとえ批評家風情がいかに表現形式上の洗練のなさを厭おうと、メッセージの鮮明さこそが何よりの武器となることを確信しているのである。
そしてその確信どおり、『解』の正味の作品性に鑑みて、アニメの放送を打ち切った局よりも、OP映像の一部差し替えなどによって放送を続けた局の方が多かった。そんなもう一面の事実に注視してみれば、受け手である私たち一人一人にとって、あの騒動の経験を、より有用なものとして捉え返せるのではないだろうか。
たとえば、放映中止の憂き目に遭ったアニメ版『解』の第12〜13話といえば、「皆殺し編」中盤のクライマックス部分。つまり前原圭一たち主人公メンバーが過去の編で繰り返してきた短絡的な殺人の惨劇の過ちに自発的に気づき、仲間の北条沙都子を苛烈なDVから救い出すため、互いの相談と連帯によって、見事に社会的な勝利を勝ち取るくだりの直後である。具体的には、「部活メンバー」−「学校全体」−「雛見沢連合町会」と、順を追って協力者コミュニティの規模を拡大しながら、市の児童相談所に地道な陳情闘争を行っていくという展開だった。
ここに立ち現れているのは、内輪の幸福を追求する「共同性の論理」が、その共感範囲の線引きを可能なかぎり外へ外へと拡げていくプロセスの果て、容易には共感しあえない他者と出会い、生存資源の配分を調停する「公共性の論理」に直面していくという主題性だ。
そしてこの作中展開は、同人ゲームの小コミュニティから始まって漫画やアニメや実写映画と、空前のメディアミックス展開を遂げた果てに、まったく予期しなかった社会事件に直面することになった、このときの『ひぐらし』ムーブメントの成長過程そのものにも、重ね合わせることができるのだ。
このような具合で、言葉で語られるメッセージに耳を傾けるだけが能ではない。『ひぐらし』というコンテンツには、作品面でも現象面でも、「共同性の論理」と「公共性の論理」の相克を、様々なレベルで見出すことができるのだ。さしあたりはそんなお題でもって、私たちの『ひぐらし』体験の諸相を、段階的に腑分けしていってみたいと思う。
■同人ノベルゲーム発の「メディア・シャッフル」展開
まず、物語を載せる「器(メディア)」のレベルに焦点を当て、外堀を埋めておきたい。
『ひぐらしのなく頃に』という物語作品は、同人制作によるパソコン用の「ノベルゲーム」と総称される種類のデジタルメディアで提供されるコンテンツとして、誕生した。
改めて確認しておけば、ノベルゲームとは、小説形式で逐次的に表示されるテキストを、描写シークエンスに対応した登場キャラクターの絵や背景画、およびBGMや効果音といった視聴覚要素によって演出するというスタイルで、プレイヤーに物語を体験させるソフトの通称である(作品で力点の置かれる演出要素の違いによって「サウンドノベル」「ビジュアルノベル」等と呼称することもあり、『ひぐらし』の場合は「サウンドノベル」をジャンル名としている)。
1990年代後半以降に発展したノベルゲームが歴史的に積み重ねてきたコンテンツ傾向として、タイプの異なる多数の美少女キャラクターそれぞれとの恋愛や交遊を疑似体験する「美少女ゲーム」の媒体に使われるケースがほとんどであった。つまり、目標とするヒロインを「攻略」するため、いかに正しい選択肢を選び続けて思惑通りのシナリオに進んでいくか、という試行錯誤の過程をゲームとして遊ぶわけである。そのため、基本的にプレイヤーは全ヒロインのシナリオ分岐を制覇すべく、何度も繰り返しプレイするのが、こうしたジャンルのソフトにおける当然の受容形態となっていったのである。
さらに、プレイヤーによるこうした能動的な繰り返しの体験性に順応してきた00年代初頭になると、今度はその順応を逆手に取って、「世界が超越的な力によってループしている」ことを劇中の登場人物が自覚していることを示唆するメタフィクション的な描写を行ったり、あえて選択肢を排除することでプレイヤーに無力感を味わわせたりするようなトリッキーな作劇によって、ある種の前衛性を表現したかのようにみえる作品群が登場してきたのである。
以上、少々クドいおさらいとなったが、『ひぐらし』もまた、こうした一連の流れの中に系譜づけられる一作であることは間違いない。「鬼隠し編」から「祭囃し編」までの全8話の連なりを通じて、昭和58年6月近辺の雛見沢世界が何度も繰り返されるという特異な趣向や、その要因となる古手梨花や羽入の存在は、特殊なノベルゲームの発展史抜きには、まず考えられなかった設定だ。つまり、この物語はメディア自体の性格がもたらすきわめて強力なコンテンツ干渉性と、そのユーザーコミュニティの強固な文脈依存性とが帰結した、「共同性の論理」の結晶のような産物と言えるのである。
しかし『ひぐらし』が画期的だったのは、そうしたノベルゲーム的なリアリティへのリテラシーがなければ理解しがたい全体構造と物語の同一性はそのままに、個々の各編を別々の作家・版元から出版してみせた漫画版や、全編をシリアルに配列したアニメ版、そして実写映画版まで、表現特性の振れ幅が極端に広いメディアミックス展開を成功させたことだ。
結果として、メディアとコミュニティの垣根によって従来きわめて狭いレンジでしか受容されることのなかったハイコンテクスチュアルなノベルゲーム的作劇が、ほぼ初めて一般エンターテインメントのフィールドに解放されるかたちとなった。
そうした仕掛けが、最終的にどこまで受け入れられるのかは、各メディアでの展開がまだ途上である現在のところはまだ未知数だ。しかし、すでに従来のノベルゲームのユーザー層からすれば、世代や性別を越えたはるかに多様な文化トライブに属する人々が多様な入り口からファンとなり、裾野が広がっているのは間違いない。
こうしたメディア・シャッフル状況は、もはや単なる「共同性の論理」の拡大の域を越え、幅広い受け手たちの間で『ひぐらし』の物語が「公共性の論理」として機能するような、横断的なインフラを提供しつつあるのではないだろうか。
■「ジャンルの転調」が実現する「真のゲーム的リアリズム」
続いて、物語がまとう「様式(ジャンル)」のレベルに話を進めよう。
『ひぐらし』原作のゲームジャンル名である「サウンドノベル」と銘打たれた初めてのゲームは、1992年チュンソフト発売の家庭用ゲームソフト『弟切草』である。先述の通り、やがてほとんど成人向け美少女ゲームの代名詞のようになっていく90年代後半以降のノベルゲーム全体の傾向とは異なり、この作品は基本的には万人向けのサスペンスホラーであった。しかし、「元祖」であるこの作品が特徴的だったのは、プレイヤーの選ぶ選択肢によって、描かれる物語のジャンル性格そのものが、推理ミステリーから心霊ホラー、スパイ冒険ものやスラップスティックコメディ等々、登場人物の設定から何から根こそぎ変わってしまうという、分裂症的なシナリオ分岐を持っていたことだ。分岐した物語相互に何の関連性もなければ、選択肢を選んだ後の物語の変化にも特に必然性や整合性はない。完成度の高い本格推理ホラーとしてヒットした次作『かまいたちの夜』等に比べて、黎明期ゆえの自由すぎる粗削りな作品だったと言うほかないだろう。
筆者が思うに、本来はチュンソフトの登録商標である「サウンドノベル」の名を継承した『ひぐらし』の物語の転調スタイルは、どこかこの『弟切草』を彷彿とさせる、「面白ければ何でもアリ」な横紙破り的性格への“原点回帰”を果たしているような気もするのである。
というのは、第4話までの出題編に対応して各編の物語を裏返していく後半の『解』のスタイルは、従来のミステリーという物語ジャンルの約束事を、大きく打ち破るものだったからだ。
『解』の冒頭を飾る第5話「目明し編」こそ、出題にあたる第2話「綿流し編」の双子トリックを、犯人側の視点から見るかたちで真相を示していくという、ミステリー的にオーソドックスな「解答」の体を為していた。しかし、続く第6話「罪滅し編」以降の展開は、そうしたストレートな意味での「解答」の体裁を捨て、かわりにノベルゲーム的な「世界ループ」の設定と主題が立ち現れてくる。この点こそ、本作への賛否が大きく分かれるポイントになっているのは、周知の通りである。
確かに、ミステリーという様式的な伝統の蓄積が、物語の構成性を高め、コアなミステリーファンだけでなく、多くの人々にとってもなじみやすいオープンなエンターテインメントの作法として定着している実績は見過ごせない。実際、メディアミックス化が進んでいる『ひぐらし』の前半パートは、そうしたミステリーとしての趣向性の高さに支えられて、大きな支持を得ているのは間違いないからだ。
しかし、だからといってミステリーというジャンルの「大きな共同性」に沿った方が、ノベルゲーム的な世界ループ系の「小さな共同性」よりも普遍的で公共性に近づけるのかというと、事はそう単純ではない。稲葉振一郎が『モダンのクールダウン』において、近代フィクションにおける「(SFやミステリーなどの)ジャンル小説」と「純文学」の理念的な本質性を区別してみせたように、ジャンルの島宇宙の規模が大きかろうが小さかろうが、一定の様式や約束事への同調をはかるという意味で、共同性は共同性である。対して本来の文学の持つ公共性とは、あくまで異なる約束事同士の間を、メタレベルから関係づけることだ。特定の共同性がともすれば陥ってしまう排外性や暴力性に警鐘を鳴らし、その共同性の外部にある他者への共感の芽を担保することこそが、その役目である。
そう考えれば、『解』の展開がミステリーの縛りを捨てて、世界ループものや青春もの、そして明朗な冒険活劇へと、次々とジャンルを転調していったこともまた、明らかだ。ジャンル小説的手法であろうが自然主義的リアリズムであろうが、ひとつの物語ジャンルを採用するとき、それは必ず描写リアリティの性格を規定し、描きうるテーマやストーリーの拘束条件となり、特定の共同性に回収される慣性を帯びてしまうのが、ポストモダン時代のフィクションの宿命である。
だからこそ、描くべきテーマが優先されるものとしてあるとき、『弟切草』という原点の時点で萌芽的に示しされていた、複数のジャンルを並列化できるノベルゲームのメディア特性が威力を発揮する。すなわち、単にプレイの繰り返しで世界をループさせられるというだけでなく、同一パッケージの作品世界に対して、異なるジャンル的リアリティをもつ複数のシナリオで重層的にアプローチすることで、現実のもつ多面性や全体性を体感させる手法が採りうること。
余談になるが、この特性こそ、東浩紀が想定した概念よりもさらにベーシックで一般性の高い、真の「ゲーム的リアリズム」と名づけられるべきものではないだろうか。90年代後半以降の美少女ゲームしか見なかった東の場合、あくまで閉塞したループ世界にプレイヤーの立場を重ね合わせるセカイ系的な感傷(=「感情のメタ物語的詐術」)という特殊な事例にのみ、この概念を限定してしまっていた。しかし、ゲーム史的な観測点のスパンを遡ることで、「リアリズム」と呼称すべき文学的性質がよりハッキリするかたちで概念をアップデートできるのではないかと、もののついでに提案しておきたい。
ともあれ、個々のジャンルの共同性に限定されないメタな立場から、現実なるものの多面性を感得することこそ、すなわち公共性にほかならない。サウンドノベルの忘れられていた原初的性格に則るかたちで、『ひぐらし』というコンテンツがジャンル転調的な作劇手法を採用していたこともまた、本作が「公共性の論理」を志向してゆく諸相の一面であるのは、まぎれもないことではないかと思う。
■「雛見沢症候群」は「ミステリー」を内破する
『ひぐらし』が進めた「様式」破壊の意味を、もうすこし詳しく掘り下げてみたい。
『ひぐらし』が昭和58年の雛見沢村という、祟りへの信仰の残る村落共同体の舞台設定を採用し、凄惨な猟奇殺人事件をめぐるストーリーを展開しているのは、横溝正史に代表される田舎の前近代的な共同体の因習や怨念を犯罪の背景に用いた、典型的な日本ミステリーの類型の踏襲にほかならない。
こうした、戦後の高度経済系長期に確立された横溝ミステリーの王道は、奇異な前近代的風習や、超自然的な祟りの実在を示唆する言い伝えなどによって一見おどろおどろしく殺人事件がカモフラージュされているものの、最終的にはあくまでも動機を持った人間による現実的なトリックとして推理され、すべての謎が解かれるというのがお約束だ。ここから、ミステリーという物語様式の批評的な意味での本質を敷衍すれば、犯罪という前近代的な不条理に対し、近代主義的・人間主義的な理性に基づく論理的な推理によって立ち向かい、屈服するという形式だと定義することができる。つまり、基本的には「幽霊の正体見たり枯れ尾花」的なかたちで、前近代的な共同体社会の迷妄や抑圧性を否定し、人々を啓蒙主義的な理性に基づく近代社会の公共価値に馴致させるためのイデオロギー装置としての骨格を持っている。
ただし、犯罪トリックや犯罪者の描き方によっては、逆に近代合理主義の暴走を、時代に取り残されたマイノリティの側から告発する作品が紡がれる場合もある。笠井潔などの立場によれば、もともとミステリーやSFといったジャンル小説の批評的な存在意義は、突き詰めれば「公共性」を僭称する無自覚な「共同性」でしかない近代の「裸の王様」ぶりを相対化し、自然主義的リアリズムの閉塞を打ち破りうる点にあるとされている。要は古典的な近代−反近代という対立軸のスキームを提示できるフォーマットだということだ。
だが、こうしたミステリーという表現形式が、近代主義の理想を掲げたり、逆にその暴力性を衝いたりするビビッドな機能を保っていたのは、まだ日本各地に田舎の古い共同体社会のリアリティが残っていた、せいぜい1980年代くらいまでのことだろう(だからこそ、『ひぐらし』の舞台は、昭和58年に設定されている)。そうした現実の前近代の圧力がなくなり、古典的な近代主義の理想がもはや理想たりえなくなったポストモダン社会たる現在では、もはやミステリーは愛好者たちの島宇宙内で“ネタ”として安全に消費されるバロックとしてしか存在しえないのだ。
そうした認識に立ったとき、物語を真に受け手の現実に届くものとして機能させようとするなら、ミステリー的な約束事の遵守などは、もはや二の次の問題ではないだろうか。
その意味では、『ひぐらし』の物語の前半の惨劇の原因となる「雛見沢症候群」という、人間の内面的な狂気を描く猟奇ミステリーの醍醐味を台無しにしてしまうSFめいた“反則設定”の導入にさえ、ジャンルのお約束を内破する積極的な意義を見出すことが可能かもしれない。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
▼PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は3月も厳選された記事を多数配信予定! 配信記事一覧は下記リンクから更新されていきます。
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201503
-
『刻命館』『カオスシード』『moon』『たまごっち』——〝逆RPG〟から転じたジャンルの複合と批評的ゲームの勃興(中川大地の現代ゲーム全史) ☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 vol.265 ☆
2015-02-19 07:00※メルマガ会員の方は、メール冒頭にある「webで読む」リンクからの閲覧がおすすめです。(画像などがきれいに表示されます)
『刻命館』『カオスシード』『moon』『たまごっち』――〝逆RPG〟から転じたジャンルの複合と批評的ゲームの勃興(中川大地の現代ゲーム全史)
☆ ほぼ日刊惑星開発委員会 ☆
2015.2.19 vol.265
http://wakusei2nd.com
本日のメルマガは月イチ連載『中川大地の現代ゲーム全史』です。今回は、「ドラクエ」「FF」が一世を風靡して以降、90年代後半の「ポストRPG」の時代のゲーム市場の地殻変動を、ソフト・ハードの両面から振り返ります。
「中川大地の現代ゲーム全史」
第8章 世紀末ゲームのカンブリア爆発/「次世代」機競争とライトコンテンツ化の諸相
1990年代後半:〈仮想現実の時代〉盛期(7)
前回までの連載はこちらのリンクから。
■〝逆RPG〟として始まったジャンルの複合と究極進化〜『刻命館』と『カオスシード』
大手メーカーが3DCGを用いた大作シリーズのゲームデザインや演出手法を確立していく一方で、中小クラスのディベロッパーが手がける実験的なスタイルの作品も、着々と独自の洗練を重ねていった。
とりわけ、ひとつの傾向として指摘できるのが、スーファミ時代に爛熟を重ねてRPGやSLGを中心とするゲームジャンルがいったん飽和状態に達したことを前提に、その構造をシステム的・シナリオ的に捉え返すアイディアで複合させたり、批評的なメッセージ性を込めようとする作風である。
そうした意識がわかりやすく立ち現れているのが、例えばテクモの『刻命館』(1996年)シリーズであろう。そのゲームデザインは、『ウィザードリィ』以降のいわゆる「ハック&スラッシュ」型RPGの構造を引っ繰り返したものである。つまり、冒険者がダンジョンを探索してモンスターを倒したり財宝を探索するという図式を逆さまにし、主人公が直接戦闘はせず「刻命館」に侵入してくる人間たちを捕獲したり狩ったりしていくもので、迷宮の奧で待ち構えるボス側の立場をプレイヤーに体験させるトラップシミュレーションだ。
システム面の逆転のみならず、王位を簒奪された亡国の王子が人間狩りをすることについての倫理的葛藤の如何によってエンディングが変わるなど、シナリオ的にも捻ったダークファンタジーが展開されることになり、文芸面での成熟性も高められることになる。
同様のアプローチから、さらなる究極に到達したのが、『仙窟活龍大戦カオスシード』(ネバーランドカンパニー)である。本作は1996年のスーファミ版『カオスシード 〜風水回廊記〜』を初出に、98年にセガサターンに移植されたタイトルだが、人々から「洞仙」という忌まわしい存在と思われている主人公が「仙窟」と呼ばれるダンジョンを構築して侵入者を撃退するという骨格は『刻命館』と同傾向ながら、それに加えて侵入者と戦闘する部分ではアクションRPG、仙窟防衛のユニット運営面ではリアルタイムSLG、さらに対話式にシナリオが分岐していく部分ではテキストAVGの要素など、2D時代の長編ストーリーゲームで考えられる可能なかぎりのゲームデザインをハイブリッドさせた、きわめて複雑高度な作品となった。
▲『仙窟活龍大戦カオスシード』(ネバーランドカンパニー、1998年)
文芸面では、『刻命館』のようにあからさまに偽悪的なダークファンタジーではないものの、『クーロンズ・ゲート』などと同様、風水を基調にした東洋的な意匠による自然観のもつ力を主人公側の立場として採用して、西洋ファンタジー風の勇者や冒険者が敵になるという図式で、一般的なRPG等の逆を衝こうとする世界観が通底している。
また、シナリオ毎に異なる平行世界に飛ばされるというストーリー展開を通じて、当初の悲劇的な結末を変えていくという、2000年代のサウンドノベルや美少女ゲームで流行していくことになる「ループもの」の構造を、きわめて早い時期に導入していた点も大きな特徴だ。これは、一定のスパンでのプレイの繰り返しを要請される、他の物語メディアとは異なるゲームならではの特性を最大限に活かした作劇手法と言える。2D時代のゲームシステムの究極的な進化を追求した本作の方向性の帰結として、こうした作劇に辿り着いたわけである。
■〝ゲーム〟を批評しだしたゲーム〜『moon』という前衛
以上の2作は、家庭用ゲームの王道となっていたJ−RPGにおける「勇者と魔王」の図式を、あくまでゲームデザインの範疇の中で攻守を入れ替えるところから発想された例にあたるが、その批評意識をさらに先鋭化させて、「プレイヤーが家庭用ゲームを遊ぶこと」そのものへの問いかけへと結びつけていったタイトルも登場する。
その最たる例が、ラブデリックの開発したプレイステーション用タイトル『moon』(アスキー 1997年)である。『ドラクエ』風の勇者が町中の家に入りこんでアイテム探しをするという、誰もがRPGのプレイ時に身に覚えのある風景を実写で再現して「おやめください、勇者さま!」と住民に叫ばせ、「もう勇者しない。愛と平和のRPG」と続けるCMでキャッチーに伝えられているとおり、本作の基本的なコンセプトはRPG(のもつ通俗的なプレイイメージ)への風刺にある。
▲『moon』(アスキー、1997年)
CMで描かれていた風景は、実際のゲームでは、物語の導入部で主人公の少年がプレイする、スーファミ時代の『ドラクエ』『FF』を露悪的に模したようなドット絵表現の「FAKE MOON」と題されたゲーム内ゲームとして表現される。そこで、勇者が悪の魔物を倒しながら宇宙船を手に入れて月に住むラスボスを倒しにいくまでのプロセスがダイジェストして描かれるのだが、「ゲームなんてやめて早く寝なさい」という母親の呼びかけとともに中断しかけたところで、少年がテレビ画面に吸い込まれてゲーム内ゲームの世界に落ちてゆき、姿のない影のような存在となってゲーム本編がスタートする。
これ以降の本編は、擬似スーファミ風のドット絵ではなく、プレステ本来のポリゴン表現を活かした、童話絵風のキャラクター陣やパペット調のアニマルたちなど、より生命感のあるタッチのグラフィックで描かれた「REAL MOON」の世界として区別される。そこでは、少年が「FAKE MOON」のプレイを通じて操っていた勇者が、実はCMで戯画化されていたように町の住人たちに迷惑をかけていたり、罪のないアニマルたちを殺戮していたという真相が明らかになる。そして、自分の分身である勇者の足跡を追いつつ、その不始末を少年が解消してアニマルの霊を取り戻して蘇らせたり、住民の抱える問題を解決したり心を通わせたりすることで、世界に「ラブ」を取り戻していくというのが、本作の基本概要だ。
つまりは、プレステ時代になって実現できるようになった、相対的に精細で深みのある質感の視覚表現での〈仮想現実〉世界を「リアル」と位置づけ、スーファミ時代にRPGのゲームシステムの氾濫とルーティーン化・形骸化によってファンタジーを頽廃させてしまった平板で「フェイク」な体験性を批判するという重層的な表現が採られている。
ただ、それだけであれば、単に視聴覚表現や容量の向上に任せて前時代までになしえた表現のリアリティレベルの低さにツッコミを入れ、〝勇者するRPG〟の暴力性に対して〝愛と平和のRPG〟の牧歌性を称揚する、ゲームの嗜好についてのイデオロギッシュな価値観表明以上のものにはなりえない。
【ここから先はチャンネル会員限定!】
PLANETSの日刊メルマガ「ほぼ日刊惑星開発委員会」は2月も厳選された記事を多数配信予定です!(配信記事一覧は下記リンクから順次更新)
http://ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/201502