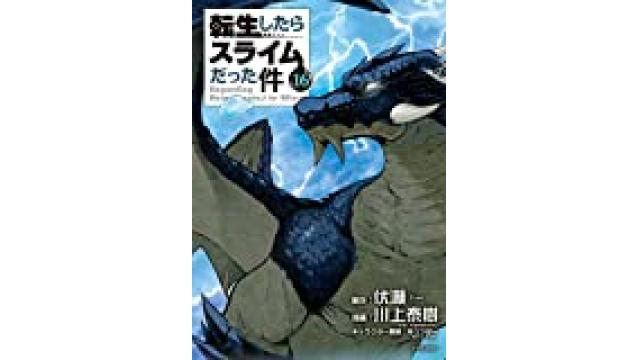-
『氷と炎の歌』、『ダークソウル』、ダークファンタジーの伝統とは。
2021-06-20 16:23300ptドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』、ゲーム『ダークソウル』など、さまざまなメディアで世界的に流行を続けるダークファンタジー。そのジャンルはどのような歴史と特徴を持っているのか、ひと通りのことを解説しました。
『ENDER LILIES』が面白そうだ。
明後日の6月22日、『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』が発売される。「死の雨」によって壊滅した王国を舞台に、少女と騎士の昏い冒険が描かれる、とか。
「2Dグラフィックのマップ探索型アクションゲーム」を意味する「メトロイドヴァニア」と呼ばれるジャンルの作品で、バリバリのダークファンタジーだ。
「メトロイドヴァニア」という言葉は『メトロイド』+『キャッスルヴァニア(悪魔城ドラキュラ)』から来ているのだが、まあ、ようするにそういうゲームであるらしい。
すでに先行版が発売されていて大好評だし、何よりぼくはこの手のダークファンタジーが大好物なので、ぜひプレイしたいと思う。
いま、ゲームの世界に留まらず、映画でもマンガでもダークファンタジーは大流行だ。否、もはや流行というよりメジャーな一ジャンルとして印象した印象すらある。
世界的に見て、そのなかでも最も大きいタイトルはやはり『ゲーム・オブ・スローンズ』だろう。
ジョージ・R・R・マーティンの『氷と炎の歌』を原作に、「七王国の玉座」を狙い合うさまざまな野心家たちの策謀と戦いを、ドラゴンやゾンビといったファンタジー的なキャラクターをも絡めて描写したテレビドラマ市場に冠たる大傑作にして大ヒット作である。
原作も優れた傑作にして世界的なベストセラーだが、その人気が広まったのはやはり映像化されたことが大きいと思う。
また、ゲームの世界では、ダークジャンファジーと呼ぶべき名作が山のように発売されている。
どこからどこまでをそう呼ぶべきなのかは微妙なところだが、たとえば日本のゲームである『ダークソウル』などは、世界的に熱狂的なファンを抱えていて、「ソウルライク」と呼ばれるゲームもたくさん出ている。
『ドラゴンクエスト』の新作もどうやらダークファンタジー風味の作品になるらしい。このダークファンタジーのブームはどこから来ているのか、なるべくわかりやすく解説してみよう。
ダークファンタジーとゴシックロマンス。
歴史的に見れば、ダークファンタジーと呼ぶべき作品は、そのときはそう呼ばれてはいなかったにしても、じつは大昔からあった。
そもそも世界中の神話やお伽噺などがかなりダークな性質を持っていることは広く知られている通りであるわけで、そういう意味では数千年前からダークファンタジーは存在していたということもできるかもしれない。
ただ、それだけではあまりにざっくりした説明になる。より近代的な意味でのダークファンタジーに注目してみよう。
おそらく、いまのダークファンタジーにとって先祖ともいうべき作品があるとするなら、それはいわゆる「ゴシックロマンス」の小説たちだろう。
ウォルポールの『オトラント城奇譚』に始まる18世紀のロマンス小説は、たしかに狭い意味でのファンタジーとはいえないだろうが、その昏い魂を凝らせたような展開の数々、また荒涼たる風景の描写は、非常にダークファンタジー的である。
エドガー・アラン・ポーという例外はあるにしても、その大半がいまの目から見ると冗長で無駄が多いように思えるところも含めて、ダークファンタジーはゴシックロマンスから生まれた、といっても良いものと思われる。
それらの作品については『ゴシックハート』、『ゴシックスピリット』といった解説書にくわしい。
悪の魅力と異国情緒(オリエンタリズム)あふれる『マンク』などは、今日のたとえば『アラビアの夜の種族』の遠い祖先といえるかもしれない。
ただ、これらの作品は一般にホラーの先祖とみなされていて、ダークファンタジーとのつながりを考える人は少ないだろう。
また、その雰囲気はいかにもダークファンタジーと似ているとしても、もっと直接的にいまのダークファンタジーと関係があるというものでもない。
その上、18世紀はあまりにも遠い。したがって、よりダイレクトにダークファンタジーといえる作品たちは、20世紀初頭のアメリカに見ることができるはずである。
100年前のヒロイックファンタジー。
いまの視点から振り返ってみると、エンターテインメントとしてのダークファンタジーの成立は、いまから100年ほど前、20世紀前半の頃なのではないかと思えて来るのである。
『ウィアード・テールズ』などといったアメリカの娯楽雑誌で、いわゆる「パルプフィクション」として誕生した「ヒロイックファンタジー」のうちのいくつかがそれだ。
いまではほとんどは取るに足りない凡庸な作品に過ぎなかったともいわれるヒロイックファンタジーだが、なかには素晴らしい名作もあった。
たとえば、ロバート・E・ハワードやC・L・ムーアなどの作家たちが物した『英雄コナン』や『ジレル・オブ・ジョイリー』などのシリーズがそれである。そのなかでも『コナン』のシリーズはいまに至るも名作中の名作として知られている。
これはいまから一万年以上も昔の時代に、頽廃した文明のなかで活躍した野生児「コナン」を主人公とした物語で、かなりダークでデカダンでエロティックな作品群である。
その即物性というか、ある種、プラグマティズム的な雰囲気も含めて、ある意味では、『コナン』は最初期のダークファンタジーといえるかもしれない。
これもまた、日本では100年以上が過ぎたいまでも新刊として読むことができる。いかに優れたシリーズであるかがわかろうというものだろう。
一方、当時のヒロイックファンタジー作家にはめずらしい女性作家であるムーアは、その傑出した感性で、きわめて官能的なファンタジーを綴った。彼女の「ジレル」や「ノースウェスト・スミス」のシリーズはいまでも読まれている。
また、「ジレル」にしろ「ノースウェスト・スミス」にしろ、「やおい趣味」的なフレーバーが濃厚で、そのような意味でも興味深い作品なのである。
そして、それらの作品よりさらにダークでデカダンな作品を物したのが、クラーク・アシュトン・スミスだ。
-
なぜ男女は蔑み合い、そして非モテはいくらモテても救われないのか?
2021-04-18 03:0150pt
ども。遥か遠くにかがやくあのリア充の星を目ざし、きょうも一歩、また一歩と進んでいる(つもりの)海燕です。
いやー、リア充への道は果てしなく長い。生きているうちにたどり着けるのかどうか、何かもうかぎりなく怪しいところ。でもね、あこがれるよね、リア充。
そういうわけで、きょうはリア充の必須スキルであるところの「コミュニケーション」について解説した漫画を読んでみました。その名も水谷緑&吉田尚記『コミュ障は治らなくても大丈夫』。
これさえ読めばきょうからぼくもリア充だ! と思ったのですが、これがね……じつに何ともいえない気持ちにさせられる本だったのですよ。どういうことなのか、これから説明しますが、ほんとにちょっと説明しがたい読後感でしたね。いやはやいやはや。
まず、この本ではいわゆる「コミュ障」であるにもかかわらず、なぜかラジオアナウンサーになってしまった著者(吉田尚記)が自分の抱える問題点を分析し、克服していく過程が書かれています。
それは良いんですよ。いくつか非常に参考になるところもあって、「ふむふむ」と関心しながら読んでいました。それが違和感がつのってくるのは、著者が芸人たちのコミュニケーションを学び始めるあたりから。
そこには「相手の発言から2秒間以上空けずに話を相手に投げ返すべき」ということが書かれています。いわば「2秒パスルール」ですね。つまり、話の内容は何でも良いんだと。
ただ、2秒以内に相手にパスしつづけることこそが肝心なのであって、そういう意味でコミュニケーションとは協調のゲームなんだということです。
そして、さらに読み進めると「愚者戦略」という言葉が出て来る。これは「人にバカにされても怒らずへらへらしていろ」というような「戦略」です(ほんとにそう書いてあるのよ)。
その名の通り、あえて愚か者の「キャラ」を受け入れることによって、その場を楽しくさせるのだ、ということなんですね。
ここまで読むと、ぼくははっきりと「ちょっと待って」と思ってしまいました。いや、それはあまりに「浅い」コミュニケーションでしょうと。
ただひたすらにバカのふりをして、「いじられキャラ」になって、2秒以内に言葉をパスしつづける。そういうコミュニケーションを続ければ、たしかに気まずくはならないし、その場の空気も崩さないし、楽しく話ができるかもしれない。
でも、それだけですよね。ただ「2秒パス」を続けるだけで人生を変えるような深い話ができるはずはない。もちろん、初対面の相手とはいきなりそんなに深い話はできないし、する必要もないでしょう。
だから、「2秒パスルール」はある限定された条件のもとでは有効だと思う。とはいえ、すべてのコミュニケーションを「2秒パスルール」や「愚者戦略」で切り抜けようとすることには無理がある。
もっとも、著者もそのことは良くわかっているようで、この本のあとがきにはこう書いてあります。
ただ、もしかしたら気になっている人がいるかもしれません。コミュニケーションは自己表現ではなく、会話の時間を繋いでいくゲーム。そして、相手が答えやすい質問をすることが大切。そんなことをしていたら、薄っぺらい関係しか作れないんじゃないの?と。
もう一つ、大切なことを書いていませんでした。和やかな会話をくり返していると、努力しなくてもいつまでも会話が終わらない相手が不思議と現れます。そういう相手とは、いつの間にか、大切なことを打ち明けたり、聞かせあったりすることになります。「この人と友達になろう」って思ったり「私たち、友達だよね」って確認をしなくても、一緒にいて楽な人。それこそ、友達、なんじゃないでしょうか。
でも、一足飛びに友達にはなれません。すべては会話からスタートします。普通の会話を繰り返しているうちに、いつの間にか、そう、なるんです。
なるほど。つまり、この本で解説されているのはすべて親しくない人と「浅くて楽しいコミュニケーション」を行うための方法論であって、「「大切なことを打ち明けたり、聞かせあったりする」深くてマジメなコミュニケーション」はその「浅くて楽しいコミュニケーション」を通して「友達(とか恋人とか)」になった相手とだけ行えば良い、ということなのでしょう。
これは良く理解できる。ただ、「浅くて楽しいコミュニケーション」のことだけを「コミュニケーション」と呼ぶのはやめてほしいけれど。
で、また、本書のAmazonレビューにはこのような文章があります。
自分は馬鹿にされても良い、愚者を装ってでも相手を楽しませる。イジられてナンボなんだ、と。
コミュニケーションは対戦型のゲームではなく参加者全員が協力するゲームだから、みんなが楽しくなれば、(自分も含めた)みんなの勝ちなんだと。
それはその通りなのかもしれないけど、それは本当に「楽しい」のだろうかと思ってしまう。少なくとも私はその場で笑えたとしても、次に同じ相手に会う時に気が重くなっていると思う。(だから私はコミュ障なんだろうけど)
著者はコミュニケーションは出世やお金儲けのような利益を得るための『手段』ではなく、それ自体を楽しむことが目的なんだ、とおっしゃるが、私は読めば読むほど「こんなこと、何か利益でも得られないとやってられないよ…」という気になりました。
これ、吉田さんのコミュニケーション理論に対する非常に本質的な批判だと思うんですよ。
あるいは、吉田さん本人は「2秒パスルール」や「愚者戦略」に基づくスピーディーな心から楽しめる人なのかもしれません。しかし、そういうやり取りを楽しいと思わない人は大勢いるはずです。
そういう人はどうすれば良いのか? そもそも浅いコミュニケーションができなければ深いコミュニケーションを取れる相手を見つけることはできないのだから、とりあえず浅いコミュニケーションのやり方、つまり「2秒パスルール」や「愚者戦略」を学ぶべきなのか? しかし、どうしてもそれがイヤだったら?
何より、ぼく自身、「2秒パスルール」や「愚者戦略」のようなやり方がコミュニケーションの本質だとか奥義だと思われると非常にイヤだな、と思のです。
吉田さんは、コミュニケーションというゲームに参加するプレイヤーたちの共通の敵は「気まずさ」だと書いています。つまり、浅いコミュニケーションにおいていちばん大事なことは相手と気まずくならないことなのだ、ということですね。
そのためにこそ、2秒以内に会話を相手に投げ返したり、真剣な顔をせずへらへらしたりする必要がある。しかし、ほんとうにそうでしょうか? もちろん、ほんとうに「浅い」内容しか理解できない相手とのあいだでは、そのようなやり方を採用するしかないかもしれません。
けれど、もう少し「深い」話ができそうな人が相手なら、たとえ親しい「友達」でなくても、もう少し違うやり方を試してみても良いのではないでしょうか? ぼくはそう思います。
とはいえ、この本は非常に面白いひとつの事実を教えてくれています。つまり、一般にコミュニケーションと呼ばれているものには、じっさいには「深さ」のレベルがあり、「浅い(表面的な)」コミュニケーションと「深い(熟慮を要する)」コミュニケーションはまったく違う性質のものだということです。
で、いささか唐突ではありますが、ここでぼくは非モテ界隈でよく聞かれる話を思い出すのです。つまり、「女は「男らしく」暴力的な男を好むものだ」という話です。無関係に思われるかもしれませんが、まあ、読み進めてみてください。
この話、かぎりなくマユツバではあるのですが、そうかといって否定できない真実の響きを秘めているように思います。というのも、少女漫画などを読むと、よく暴力的としかいいようがないイケメンの「ドS男子」が出て来て、主人公をいじめながら愛の言葉をささやいたりしているからです。
もちろん、それはフィクションであるに過ぎませんが、男性向けの漫画と同じく、現実の嗜好を繁栄している一面はあると思います。
で、それだけだと、まさに非モテの恨み節というか、「どうせ「ただしイケメンに限る」なんだろ?」みたいな不毛な話にしかならないのですが、面白いのは女性のほうも「男は「女らしく」従順な女を好むものだ」と考えている人がたくさんいるということなんですよね。
先ほどの『コミュ障は治らなくても大丈夫』と同じ水谷緑さんに『男との付き合い方がわからない』という本があるのですが、この本ではまさにそういうことが書かれています。
女性から見た男性の真実というか、まさに「ただしイケメンに限る」の裏返し、「ただし従順で貞淑で清楚な可愛い女に限る」というわけですね。
そして、ぼくもひとりの男性として、少なくとも「ただしイケメンに限る」と同じくらいには、この言葉が真実であると感じます。
しかし――ほんとうにそうなのでしょうか? 男性はみながみな、従順で貞淑な女だけを好み、女性はだれもがマッチョな金持ちのイケメンだけを好きになるものなのでしょうか? そうではない選択はすべて「妥協」の産物なのでしょうか?
ぼくはそうは思わないのですよ。本来、男性にしろ女性にしろ、好みは多様だと考えます。つまり、ほんとうは多様な需要があるはずだと思うのです。繊細な男性が好きだという女性がかなりの割合でいてもおかしくないし、気の強い女性が好きな男性だってそれなりにいるはずだと。
それなら、なぜ、奇妙なほど男女の「好み」は一様化している(ように見える)のか? そう、ぼくはその原因こそが「ジェンダーロールの呪い」だと思います。
つまり、じっさいには多様な需要と供給があるはずの恋愛マーケットのプレイヤーたちに「男は男らしいほうが良いに決まってる」とか「女は女らしいほうが良いに違いない」と思わせている「呪い」がある。それが「ジェンダー」なのだと。
ただし、ぼくは一部のフェミニストたちのように「ジェンダーの押しつけは悪なのだから、人をそこから解放しなければならない」といった考え方はしません。それはあまりにも単純すぎる見方に思えます。
じっさいには、ジェンダーにはある種の魅力がある。人はそれをむりやり押しつけられてジェンダーに従うだけではなく、その魅力に惹かれて自らジェンダーロールを演じるようになるのです。つまり、「ジェンダーにはアメの側面とムチの側面がある」ということ。
そのジェンダーの魅力とは、つまり、「ジェンダーロールに沿った行動をしていれば異性からの評価が上がる」ということです。より簡単にいい換えるなら、「男らしく」、あるいは「女らしく」していたほうが、モテやすい。
そういう意味では、非モテの人たちが言うことには、一面の真実がたしかにある。ぼくもたしかにそうだと思います。ただし! それはあくまで表面だけのことです。なぜなら、この世には多様な人間が存在し、やはり多様な価値観を抱いているからです。
「男はこうだ」とか「女はああだ」といわれるときの「男」とか「女」とは、まさにジェンダーロールの仮面に過ぎない。その仮面をかぶっていれば、たしかに異性からの評価は上がるかもしれません。
たとえば、女性は可愛い恰好をして清楚を演じて、そのうえで何かと「すごーい!」と男を立てていれば、モテやすくなるのはたしかでしょうね。ですが、それはやはり「浅いコミュニケーション」の方法論に過ぎないのです。
もちろん、男性が「ただしイケメンに限る」とか「女はマッチョで頼りになる男しか好きにならない」というのも、あくまで表面的な話です。
ようするに、不特定多数からやたらと好意を寄せられるという「モテ」とは「浅いレベルのコミュニケーション」の結果にしか過ぎないということ!
いや、もちろん、より「深い」レベルで他者からモテている人もいるのでしょう。めちゃくちゃに人間的魅力があり、異性(や同性)をやたらに惹きつける、そういう人はたしかにいます。ここではそういう人のことを「本物のモテ」といいたいと思います。
もっとも、そういう「本物」はやはり数少ないものです。大半の「モテる男」とか「モテる女」は、容姿とか収入とか、そういう「ジェンダー的長所」に魅力を依存しているのだと思います。
そして、世の中の「モテ本」などを読むと、たいていは意図して「男らしく」なったり、「女らしく」振る舞ったりすることによってモテよう、ということが書かれている。つまり、「男と女ごっこ」を演じさえすれば労せずしてモテるのだ、ということですね。
この手の恋愛観は男女を問わず見られます。いわゆる「恋愛工学」がそうですね。あれは徹底して女性をバカにして下にあつかう方がモテるのだという理論なのですが、その成功率はともかく、たしかにそれでトライアルアンドエラーを繰り返せば、一定の確率で女性と関係を結ぶことができるようになることはたしかだろうとぼくも思います。
そのような「男らしい」態度を好ましいと考える女性は一定数いるはずだからです。それは男性が「女らしい」女性を好む、とされていることの鏡像です。そう、単に「モテ」を目指すのならそれで良い。
しかし、このやり方にはひとつ問題があります。そのようなある種のジェンダーロールになり切る方法論を使っていると、モテればモテるほど異性が嫌いになっていくということです。
なぜか。それはジェンダーロールにもとづく「浅いコミュニケーション」にひっかかって拠って来る異性がバカにしか見えないからです。
この種のモテ理論は、「どうせ男はこういう女が好きなんだろ」とか「どうせ女はこういう男が好きなんだろ」という、一種の人間に対するニヒリズムが根底にある。
そして、恋愛を、あるいはコミュニケーションをそのような「浅い」ゲームだと認識している限り、「深く」相手を知ることはできない。それは人間を嫌いにもなるだろう、と思うところです。
それでもモテるなら良いだろうと思うかもしれません。そうでしょうか? 昔読んだ本に『モテる小説』という作品があります。この本の主人公は、モテる方法について考えに考えたあげく、最後にはネットで見つけた適当な相手にひたすら性的な誘いのメールを送りつけるようになります。
もちろん、その大半は断られたり無視されることはわかり切っている。それでも一定の割合で誘いに乗る相手はいる。その相手との関係を増やしていけば良い、という理屈なのです。
初めてこの本を読んだとき、ぼくはひとつの根本的な疑問を抱かざるを得ませんでした。「で、それって楽しいの?」と。ぼくにはこの主人公が究極的な本末転倒に陥っているように思われてならなかったのです。
楽しい時間を過ごしたいがために恋愛をするはずなのに、それをただの「退屈な作業」にまで貶めてどうする、と。もっとも、いや、楽しいかどうかという話ではないのだ、という人もいるでしょう。
重要なのはセックスができるかどうかであり、性欲さえ効率良く満たせるならそれに越したことはないのだ、と。そういう人はそれでかまわないのかもしれません。ですが、それを一生続けられる人は少ないだろうとぼくは見ます。
それで「モテ」たとしても、大半の人はどこかでむなしくなるはず。なぜなら、そこには「ほんとうの自分」を自ら開示し、「ほんとうの相手」を知ろうとするという意味での「深いコミュニケーション」が決定的に、そして致命的に欠けているからです。
「深いコミュニケーション」を抜きにして、いくらからだを重ねたところでむなしいのではないか、とぼくは考えます。ただ、それはぼくの個人的な価値観ですから、「女性に求めるものはセックスだけだ」とか、「男性に求めるものは金銭だけだ」というような価値観も否定はしません。
とはいえ、そういう人にはひとつだけいっておきたいことがあります。それは、「あなたがバカにして見下している男(女)は、同じくらいあなたをバカにしていますよ」ということ。
そう、男も女も、互いに対して呪いをかけあっている。男は女に「もっと可愛い女になれ。そうでないと愛されないぞ」と呪うし、女は男に「もっと強い男になれ。そうでないと選ばれないぞ」と呪う。さらにもちろん、同性への同じような内容の呪いもある。
したがって、非モテは基本的にいくらモテても救われません。かれらが救われるためには、本来、「素顔(ほんとうの自分)」での「深いコミュニケーション」が必要なのに、「仮面(偽りの自分)」で「浅いコミュニケーション」を繰り返し、その結果、「モテ」たとしても救いにはたどり着けないわけです。
そもそも非モテが不特定多数からやたらに好意を寄せられるという意味での「モテ」を目指すこと自体が間違えているというしかない。それは非モテがモテることが不可能だからではありません。むしろ、非モテがモテること自体はまったく不可能ではない。
けれど、いくらモテたところで仮面をかぶったままでは人は救われないのです。綺麗ごとをいうようだけれど、やっぱり人は「ほんとうの自分」をさらして生きていかないと幸せになれないのではないでしょうか。
我孫子武丸さんに「人形シリーズ」というミステリの連絡があるのですが、そのなかで主人公の女性が気の弱い男性を好きになって、より「男らしい」男を拒否するんですね。
ぼくは個人的にその描写に説得力を感じました。それはそういうこともあるだろう、と。すべての女性が同じ需要を抱えているはずはない。
でも、ジェンダーは「男らしく、女らしくしたほうがモテますよ。愛されますよ」と誘惑する。それで世の中ではときに互いに深く軽蔑しあったカップルが生まれるわけです。不幸な話。
このディスコミュニケーションは、ジェンダーが要求する仮面をかぶったままの「浅いコミュニケーション」では解決しません。どうしても「深いコミュニケーション」が必要になるはずです。
しかし、「ほんとうの自分」をさらし、「ほんとうの相手」を知ろうとする(もちろん、どんなに知っても知り尽くせるはずがないことをわかったうえでそうする)という意味での「深いコミュニケーション」は、「ザ・男」とか「ザ・女」のようなジェンダーロールを通したやり取りほど簡単ではありません。
「生身の女とは話が通じない」と思っている男性も、「男はバカばっかりで話し合えない」と感じている女性も多いと思いますが、それはどこまでも相手とのあいだに「浅いコミュニケーション」しか行っていないからです。
その不幸なすれ違いを脱するためには、相手と「深いコミュニケーション」を行うしかないでしょう。ぼくはいわゆる「ルッキズム」とか「収入至上主義」が一概に悪いとは思いません。顔や金だって、人間の重要な要素です。
そうではなくて、「そういった価値観で相手を選んで、自分はほんとうに幸せになれるのか?」と考えなければならないということです。
どこまでも「浅いコミュニケーション」しかできない相手と結婚し、一生、仮面をかぶったまま生活する。そんなことに耐えられる人はそう多くはないでしょう。
そうだとしたら、「深いコミュニケーション」にもとづく恋愛ができる相手を探すべきじゃないかな。それは必ずしも見た目とか収入のスペックとはマッチしないかもしれないし、そのやり方では男性であれ女性であれ、「モテ」になることはできないだろうけれど。
でも、それがたぶん「ほんとうに幸せな恋愛」をするための方法論なのではないかと。ぼくはそう思います。おまえがモテないから自己弁護でそんなことをいっているんだろうと思われるかもしれないけれどね!
うん、「浅い」レベルでモテているという意味での「リア充」にはならなくても良い気がしてきた。もっと「深い」レベルで人と話ができる人間になりたい。まずはそれが目標だと、いまは思います。 -
『転スラ』の人気の秘密は「面白さ」を「最小単位」で並列提供する「マルチ・カタルシス・システム」にあり!
2021-03-05 07:0050ptペトロニウスさんがYouTubeで引用していた記事が面白い。例によっていくらか長くなりますが、引用します。
荒木:僕らの世代はなんだかんだで「頑張れば報われる」という右肩上がりを前提で生きてきた。会社に入って、新人時代は給料低くても地道な努力をすれば、いずれ偉くなって処遇もよくなるぞ。そんな「修行モデル」で生きてきたんです。つまり、今はつらくてもいずれペイする、という長期的な採算で帳尻を合わせる前提で頑張ってきた人は多いはずなんです。ところが、バブル崩壊後の不況や終身雇用の崩壊でじわじわとその前提が崩れていき、このコロナでとどめを刺されてしまった。この劇的な前提の転換を冷静に受け止めないといけないですし、子どもたちはもっと純粋にこの前提をインストールしていることを認識しないといけないと思っています。
すると、子どもたちにかけるべき言葉も変えなければいけないということでしょうか。
荒木:そう思います。修行モデルが通用しなくなった世界では、何が大事になるのか。それは、「今この瞬間が楽しいか」という一点ではないでしょうか。例えば、野球に打ち込む子どもに「毎日素振りを100回やりなさい。頑張れば3年後の大会でヒットを打てるはずだから」というロジックはもう響かないと思ったほうがいい。「不確定の未来に向けての努力」は、彼らのストーリーには通用しないんです。素振りの意味を言い換えるならば、「ほら、今日やった分だけ、上腕二頭筋が太くなっているぞ」といった感じでしょうか。
つまり、努力に対する成果の“収支”の確定が、極端に短期になっている。
荒木:おっしゃるとおりです。すると、これからより大事になってくるのは、その都度その場で得られるリターンを自分で発見する能力です。昭和の大流行ドラマ『おしん』のような、耐え忍んで、耐え忍んで、耐え忍んだ先に……という期待感は、今の子どもたちは持ちづらくなっているでしょう。かつて、体育会系の部活で「体罰」が黙認されていたのも、受ける側の生徒たちが「この痛みの先に最高の結果が待っている」という文脈で許容できたからです。大人だって、会社の上司から理不尽なパワハラを受けても、10年後には「あの時の叱責があったから今の俺がある」と美談に変えられた。そのロジックはもう通用しないのだと自覚しないといけませんね。
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00128/00050/
ペトロニウスさんはこの話を「小説家になろう」の作品群と重ね合わせて語っています。よければ聴いてみてください。
https://www.youtube.com/watch?v=shffngyNx6A
ここで語られている「努力に対する成果の“収支”の確定が、極端に短期になっている」。これが、キーワードです。
「小説家になろう」の作品は、しばしば「努力」が描かれていない、と批判されます。努力もしていないのに成功するなんてリアリティがない、と。
しかし、現代において「長年にわたって努力を続けた結果、成功する」という「修行モデル」の物語はもはや説得力がないのですね。
かつては、努力を続けさえすればその果てに「報い」が待っているということが信じられたのでしょう。それは社会全体が「右肩上がり」の成長を遂げていたからです。
だけど、現代ではその成長がほぼストップしてしまっているから、どんなに努力したところで「報い」を得られる可能性は非常に少ない。そこで、「努力に対する成果の“収支”の確定」が、「極端に短期」でしか認識されなくなったわけです。
いま努力したらすぐに成果が欲しい。あるいは、そのような成果しか信じられない。それが、現代の若年層のリアルだと思います。
これに対して、「辛抱が足りない」といった説教をすることはできます。でも、繰り返しますが、そうやって「辛抱」したところで、報われる可能性はほとんどないのが現代社会であるわけです。その種の説教はもはや無効になっているといって良いでしょう。
そこで、LDさんがいう「面白さの最小単位」の話が出てくる。「面白さの最小単位」とは、つまり、「いかに短いスパンで読者に先を読むインセンティヴを与えることができるか」というテーマです。
LDさんがいうには、かつて「紙帝国」がメディアを支配していた頃と現代とでは、メディアのあり方そのものが変化してしまっていると。
たとえば漫画は、「紙帝国」の栄光の象徴であるところの『少年ジャンプ』が最大部数600万部を売り上げていたときには、「ひたすら物語を長大化する」ことが最適戦略だった。なぜなら、ヒット作が出たらそれを延々と長続きさせることが必要だったから
ところが、ソシャゲやネット小説など、他の多数のエンターテインメントと激しく競合しなければならない現代においては、そのやり方は通用しない。そこで、読者に先を読んでもらうため、「面白さ」を「最小単位」で提供する方法論が起こることになる。
これは、たとえばTwitter漫画などを見ていると最もわかりやすいことでしょう。そこではわずか4ページで「面白さ」を提供しなければならない。エンターテインメントの表現のあり方そのものがメディアの変遷にともなって根本的に変わってしまっているわけです。
現代においては、たとえば主人公が延々と「努力」を続け、その結果、大きな「成果」を得るといった「修行モデル」の描写、いい方を変えるなら「面白さの最大単位」を求める方法論は通用しない。
その理由は、そう、「努力に対する成果の“収支”の確定が、極端に短期になっている」からです。
それでは、「面白さの最小単位」とは具体的にどのようなものなのか? 色々考えられますが、最も端的なものは「小さな成功体験」でしょう。「ほら、今日やった分だけ、上腕二頭筋が太くなっているぞ」というそれです。
いま、「小説家になろう」発のアニメ『無職転生』や『転スラ』で描かれているものは、まさにその積み重ねですね。『無職転生』では、ちょっと努力すると、すぐに成功する。『転スラ』に至っては、ほとんど何も努力することなしにひたすら成功だけが繰り返される。
もちろんそこには苦難も失敗もあるけれど、この場合、それは本質ではない。これは、「努力なしに栄光なし」という「修行モデル」の考え方すると、単なる甘ったるいファンタジーであるに過ぎません。「なろうは現実逃避だ」という類の批判が生まれることも無理はないといえるでしょう。
ですが、何度も繰り返しますが、「努力」と「成功(栄光)」をワンセットで考える思考のフレームそのものが、すでに過去のものになってしまっているのです。
こういった「修行モデル」なり「努力神話」のナラティヴはもう現代においては通用しない、とぼくは考えます。
『転スラ』は「面白さ」を「最小単位」にまで煮詰めるために、「努力」というパートをほぼカットした。いわば、「フリ」があって「オチ」があるという方法論から「フリ」の部分を切除してしまった。これが、『転スラ』から非常にスマートな印象を受けるその秘密だと思います。
しかし、「フリ」をカットして「オチ」だけがある、そんな物語が面白いのか? いや、あきらかに面白いのですが、それはなぜ面白いのか? そこがいまひとつうまく言語化できない。
そこで、他者の言説に目を向けてみましょう。飯田一史さんは、『転スラ』の魅力について、このように語っています。
作品内容に目を向けてみよう。『転スラ』は何がおもしろいのか?
用意しているおもしろさの種類が多様なのである。
キャラのかけあいの楽しさもあるし、複雑な物語展開もあれば、主人公リムルなどの転生者たちがなぜ異世界に召喚されたのかといった「世界の謎」もある。大集団同士が戦略を練って戦いあう「戦記」要素もあるし、コミュニティをいかにして導いていくかという「内政」要素もある。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79230?page=2
さすがというか、この意見は非常によくわかる。『転スラ』は「おもしろさの種類」が多彩なのです。よくなろう小説は『ドラクエ』をフォーマットにしているといわれますが、『転スラ』はむしろより現代的なゲームに近い。
ぼくはここでたとえば『ルーンファクトリー』というゲームを思い出します。『ルーンファクトリー』では主人公にはいくつものパラメーター、つまり成長要素が用意されていて、それがいろいろな行為によって少しずつ向上していきます。たとえば、ただ一定歩数を歩いただけでもあるパラメーターが上昇したりする。
『転スラ』はこれと似ているんじゃないか。最初の段階ではシンプルに主人公のレベルアップが「気持ちよさ」を生んでいるんだけれど、どんどんレベルが上がり、視点が高くなるにつれて、べつの「最小単位の面白さ」が開放されていく。
たとえば、主人公であるリムルの成長だけじゃなくて、脇役のだれそれの成長といった要素も入ってくるわけです。あるいは、国家の拡大とか内政の充実といった要素も出てくる。
そして、それぞれの要素で「ちょっとずつ気持ちよくなれる」ようになっている。いわば、マルチ・カタルシス・システム。これが『転スラ』の「面白さ」の根幹にあるものであるように思います。
なろう小説とはつまり「ビデオゲーム疑似体験小説」であるといって良いと思うのですが、『転スラ』にはロールプレイングゲーム要素もあれば、アドベンチャーゲーム要素もあれば、シミュレーションゲーム要素もある。
そして、つねにそのどれかの「ゲーム性」が動いていて、「小さな成功体験」が続く、なので読者は飽きずに見つづけることができる。そういうことなのではないか、と。
そのひとつひとつを取れば、おそらく『転スラ』より優れた作品はあるでしょう。もっとよくできた「成長もの(ロールプレイングゲーム)」もあれば、「内政もの(国政シミュレーションゲーム)」もあるだろうし、「学園もの(教育アドベンチャーゲーム)」もあるに違いない。
しかし、『転スラ』の特徴は、それらの「面白さ」を細かく細かく打ち出してくるところにある。ひとつひとつの「面白さ」は、あるいはカタルシスは小さいかもしれないのだけれど、それが次を読むインセンティヴを生み、いつのまにか「大きなストーリー」に、つまり「最大単位の面白さ」に到達して大きなカタルシスを得るまでになる。
ようするに『転スラ』から得られる教訓はこうです。「面白さは最小単位まで分割し並列せよ」。この作品の本質的な魅力は、たしかに「面白さが多様であること」にあるのだけれど、それだけでは言葉足らずかもしれない。 むしろ「多様な面白さが並行していることによって常に「小さな成功体験のカタルシス」が提供される仕組みができていること」にあるというべきではないかと。
いまでは最初から「最大単位の面白さ」を目指す「修行モデル」のような超長期的な物語スタイルは受け入れられない。しかし、 -
「正義」と「寛容」は矛盾し対立する。
2021-03-04 07:0050pt
きのう、『無職転生』の「低俗の肯定」というテーマに関する記事を書いたわけですが、それからちょっと考え込んでいます。つまり、「低俗を肯定すること」はほんとうに正しいことなのか、と。
この場合の「低俗の肯定」とは、たとえば性的なだらしなさを許容することを差しています。
べつだん、性的にだらしないことを「正しいこと」と見なすわけではない、それはダメなことであるには違いないのだけれど、ダメなことをダメなことと認めた上で、その存在を許すこと。それが、現代社会に最も欠けている視点なのではないか、という話でした。
ぼくは、個人的にこの考え方に強く共感するところがあります。何といっても、現代社会は、というよりインターネットは、あまりにも個人の失敗に厳しすぎる。
芸能人が何かちょっとセックススキャンダルでも起こした日には、再起不能になるまで叩いて、叩いて、叩く、それがインターネット、あるいはソーシャルメディアのスタイルです。
そこには一切の容赦はないし、許容もない、「寛容の美徳」など夢のまた夢というしかありません。
ネットではよく「また××が炎上した」などといいますが、このいい方は誤解を招く余地がある。「炎上事件」はかならずしも「炎上」した本人に責任があるとはかぎらないのです。
もちろん、そこには何かしらの「火種」があるには違いないけれど、その「火種」が完全に倫理的な悪であるとはいい切れないことも多い。「燃えあがらせる」側が何らかの誤解や誤読にもとづいて一方的に怒り狂っている場合も少なくないのです。
じっさいのところ、「炎上」という言葉は、「集団での一方的な袋叩き」というほうが遥かに実態に即していると思います。それが「炎上」と呼ばれているのは、結局は「炎上」させる側が責任を負いたくないからに過ぎないでしょう。
インターネットにはあまりにも「正義」が、いな、「独善」が強すぎる。「自分で勝手に正義の味方だと思い込んだ頭のおかしいネットストーカーたち」が徒党を組んで(ただし、自分の自覚ではたったひとりで)何か問題を起こしたとみなされた個人を攻撃している状態こそが、「炎上」の本質です。
そして、「炎上」に参加した各人は、その後何が起こっても、たとえば自殺騒動に発展しても、決して責任を取ることはありません。この種の「正義の味方」ほど醜いものはないとぼくは思います。
いやー、ひどいですね。ここら辺、『推しの子』という漫画の最新三巻を読んでいただくとわかっていただけると思います。面白いですよ。
さて、そのあまりにも「正義」が過剰すぎるいまのネットに決定的に欠けているのが、 -
『無職転生』はほんとうに「低俗を肯定」しているのか?
2021-03-03 07:0050pt
アニメ『無職転生』を見ています。すでに各所で話題になっていますが、このアニメ版、非常に出来が良い。おそらく2クール続くと思うのだけれど、原作を適度にアレンジしながらそれでいて原作の本質を非常にうまく取り入れている印象です。
もともと原作がよくできた話だけに、ここまでうまく映像に置き換えられると素晴らしいクオリティの作品ができあがる。「小説家になろう」原作作品の理想のアニメ化といっても良いのではないでしょうか。
「なろう小説」のアニメ化としては比較的遅いスタートになったことによって、結果としていままでのアニメ化の知見が蓄積されていたことも大きいのかもしれません。とにかく面白いし、よくできている。未見の方にはぜひ見ていただきたいですね。
さて、この作品についてTwitterで興味深いツイートがあったので、ちょっと長くなりますが、引用させていただきたいと思います。
『無職転生』のアニメ版を見て、やっぱこの作品はなろう小説においての金字塔で、同時に異形でもあるなと改めて思ったので、「何が」傑出しているのかちょっと書き起こしてみます。
『無職』の異様さは、「低俗の肯定」にある。
後発作品では「意図的にフック・サービスとして描く」か、無意識にマイルドにされている性描写が平然と「ここではそういうもの」として置いてある。
親は子供がいても二人目作ろうと毎日お盛んだし、貴族は子供の前でもメイドで性処理する。
とかく作品内のモラルというのは、現代の常識が反映されがちではあるけど、それにしたって性の描写というのは「逃げ」られすぎている。
本来、中世レベルの文化を描くならそこから逃げられるはずもない。『無職』は当然のように描く。女性の自慰も平然と描く。無料連載だったから越えられたタブーだ。
ダメな主人公はダメなまま肯定されるわけではない。
ダメな部分を消して高潔になるわけでもない。
ダメなりに反省し、善く生きようともがき、結果として「許容される」。
この「ダメだけど許容する」という視点が昨今のメディア文化に欠けている視点であるように思うのだ。
ルーデウスは成長する。しかしもと変態中年の精神は変質しない。それでも「報われていい」。
ここには他者への赦しがある。
「ダメだから袋叩きにして排斥してやろう」的なヘイトの対極にある。
俗物の変態に生理的嫌悪感を感じる人もいるだろうが、それでも許されることがこの作品のテーマである。
ちょっと盛りすぎかもしれないが「善人なおもて往生す、いわんや悪人をや」の精神にも通じるのではないだろうか。
https://twitter.com/kakashiasa/status/1365850988792356866
これ、どうなんだろうと思うんですよ。LINEでもちょっと話しあったのですが、「低俗」が肯定されているのは男性陣だけで、女性陣に対してはやはり理想が仮託されているのではないか、と。
たしかに「女性の自慰も平然と描」かれてはいる。しかし、そこで女性の性のセクシュアリティのあり方が十全に「許容」され、「肯定」されているかというと、そんなことはないんじゃないか。
これ、作品を批判するつもりでいうわけではないから誤解しないでほしいのだけれど、『無職転生』の「低俗の肯定」の描写はやっぱり男性中心的なハーレムものの限度を超えてはいないと思うのです。
繰り返しますが、超えなければならないとか、そこが男女平等でなければならないというつもりはまったくないんですよ。ただ、客観的に見たとき、女性のほうの「低俗」が男性ほど「許容」されているかというと、どうしても否定的にならざるを得ないのはほんとうのところなのではないか。
『無職転生』の物語のなかで、主人公ルーデウスの父・パウロは浮気をし、子供を作り、妻と息子を含む家族から「許容」されます。作者もそれを「許容」する描写をしているし、読者もまた「許容」したと思う。
そして、 -
『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』の物語のなかで、黒猫はたしかに「生きている」。
2021-02-27 07:0050pt
昨日、今日で『せんせいのお人形』の第5巻と『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』の第10巻(電子書籍版)が出ました。う、嬉しい。
何年生きていても好きなシリーズの新刊が発売される歓びは消えないなー。もう、ほとんどそのために生きているといっても過言ではない感じ。
ちなみに来月には『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』の第16巻、『ミステリと言う勿れ』の第8巻、『恥ずかしそうな顔でおっぱい見せてもらいたい 赤面おっぱいアンソロジー』の第6巻(ん?)も出るので、楽しみは続きます。わーい。
おもしろいラノベや漫画を読めるのって、なんて幸せなことなのだろう。金銀財宝にもまさるはこれ漫画なり。ぼく、小説や漫画が読めなくなったら何も生き甲斐がないかも。
そのなかでも殊に期待度が高いのは『俺の妹がこんなに可愛いわけがない(16)』。本編は12巻で完結しているので、この第16巻はそのパラレルワールドを描く、いわゆる「黒猫if」編です。
本編ではついに主人公と結ばれることなく終わってしまった黒猫が、このシリーズではメインヒロインを務めていて、前巻ではようやくふたりは恋人どうしになったわけなのですが、まだ最大の障壁は残っている状態。
さて、いったいどのような展開が待ち受けているのでしょうか……。まあ、ここまで来たらもうハッピーエンドは間違いないので、その意味では本編のようなハラハラドキドキのサスペンスはないのだけれど、それでもやはり気になるものは気になる。
思うに、人が「続きが気になる」というときにはふたつパターンがあって、ひとつは純粋に先の展開が読めないとき、そしてもうひとつは、 -
『炎と血』は『ゲーム・オブ・スローンズ』前史を描き出す架空の一大歴史書だ!
2021-02-24 16:2850pt
きょうもファンタジー小説の話ですぞ。ぼくは昔からファンタジーが好きで、いろいろと読んできているのですが、最近になってファンタジーというジャンルそのもののイメージが変わってきているのを感じています。
昨日も書きましたが、いま、ファンタジーと呼ばれているのはつまりはほとんどがゲーム小説なんですよね。
それが悪いとは思いませんが、かつてのようなより純粋な意味でのファンタジーは、ほぼ絶滅に近い状態にあるといって良いのではないでしょうか。あるいは東京創元社あたりで細々と続いている感じ。
まあ、何をして純粋というかはむずかしいところだけれど、世間でいわれるファンタジーブームはじっさいのところ、古典的な意味でのファンタジーの衰退を意味しているようにしか思われません。
もちろん、時代とともに作品の流行が変わっていくことはあたりまえのことだし、どんなに「時よ止まれ!」と願ってもむなしいことはたし -
ファンタジーの大傑作『孤児の物語』は複雑巧緻な迷宮小説だ。
2021-02-23 17:4750pt
ども。「なろう小説」やライトノベルにちょっと食傷して、何となく本格的なファンタジー小説を読みたいなあと思い、いろいろと調べてまわった結果、いま、キャサリン・M・ヴァレンテの『孤児の物語』という本を読んでいます。 これが、凄まじい。一冊6000円もするというとんでもない本なのですが、その価格に見合った内容の深さ、また分厚さ。全二巻に及ぶ大作で、ぼくがいままで読んで来たすべてのファンタジーのなかでも、まず五本の指に入る作品だと思います。
現代のファンタジー小説がよくも悪くもゲームの影響を受けて現実離れしていくなかで、ひさびさに見つけた超本格派ですね。これは凄いよ。まあ、いまどきの小説としてはあまりにも本格的すぎてウケないかもしれないけれど、でもこれはほんとうに大傑作だと思う。
二月にして今年のベスト・オブ・ベスト決定!というより、ここ数年間で読んだ本のなかでも傑出した一作といえるかもし -
「悪役令嬢もの」は少女漫画の王道を裏側から再現する。
2021-01-06 23:1950ptうに。皆さんは「悪役令嬢もの」をご存知でしょうか? まあ、ここを読むくらいの人ならほとんどご存知なのではないかと思うのですが、「小説家になろう」で流行している「乙女ゲームや少女漫画などの悪役の女の子を主人公に据えた物語」のことです。
主人公がその「悪役令嬢」自身に転生するパターンもありますし、また、「悪役令嬢」の近くにいる人物が主人公の場合もありますが、とにかくいままでわき役であり敵役であったはずのキャラクターを主役に抜擢した作品であることは間違いありません。
それらの悪役令嬢はだいたい物語のなかで破滅する運命を抱えていて、どうにかその破滅を避けるため行動することになります。で、どうやらぼくはその「悪役令嬢もの」がとても好きらしいのですね。
まあ、ひと口に悪役令嬢ものといっても膨大な作例があるからそれがすべて好きなのかどうかはわかりませんが、とりあえずいままで読んだ悪役令嬢ものはどれも面白かった。そういうわけで、今日はこの頃読んだ悪役令嬢ものの話をしたいと思います。
定番の『はめふら』こと『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』のことは措いておくとして、まずは『ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん』。
もうタイトルの時点で「何だろうこれは」となってしまいそうな作品なのですが、まさに -
みかみてれん、必勝の百合『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』がすばら。
2021-01-04 21:2150pt
さてさて。いまさらですが、あけましておめでとうございます。正月三が日は図々しくも更新を休ませていただきました。おかげで良い感じにヒマでタイクツな三日間を過ごせました。
いやー、好きなだけマンガとラノベ読んで、ビデオゲームをやるだけの日々プライスレス! ほ、ほら、ぼくってこれが仕事だし? ただ遊んでいるわけじゃないし?
とか、小学生低学年並みのイイワケはやめておきますが(やめていない)、ほんとうに気楽な三日間でした。コロナがなくて甥っ子と姪っ子が遊びに来ていたらこうはいかなかっただろうから、ありがたいことこの上なし。
そういうわけで、この三日間で随分とたくさんネタを仕入れられたのですが、今日はみかみてれんさんの百合小説『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』を紹介しようと思います。
これ! これ良いですよ! まあ、何しろ好き嫌いが分かれるガール
1 / 31
次へ>