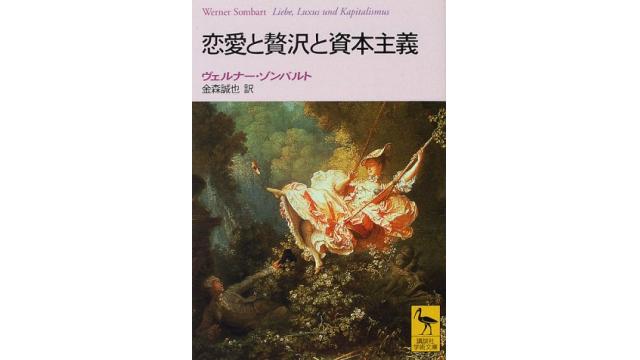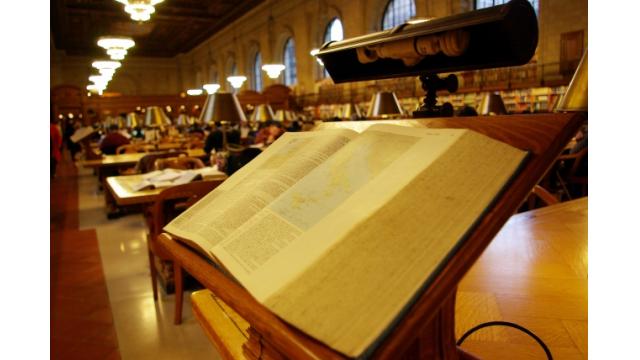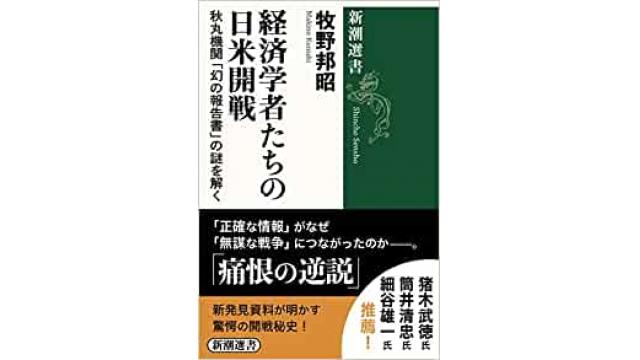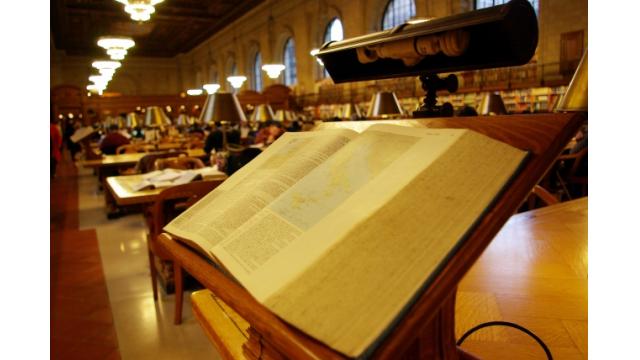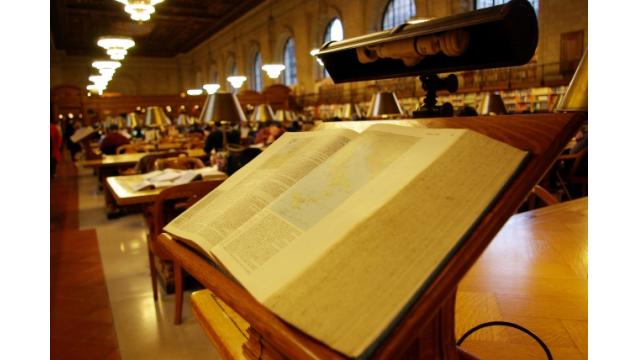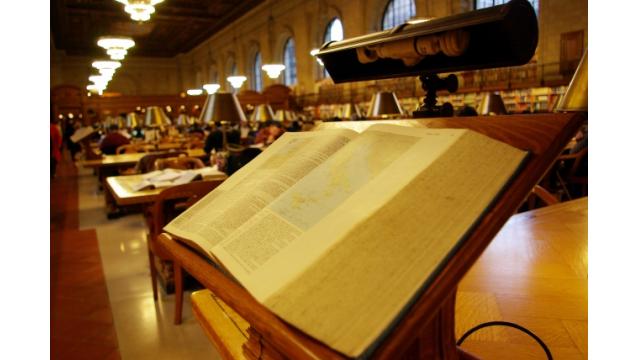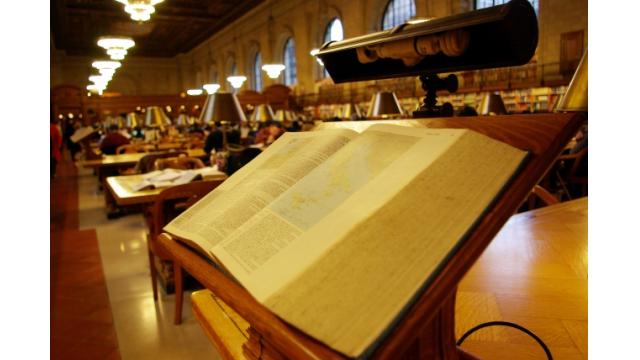-
ベトナム特派員報告
2023-10-20 12:13
億の近道では編集長が出張されたインドからのメッセージが送られたりしたことはあったかと思いますが今回は現在、ベトナムに在住されている四億(ヨンオク)さんからのボランティアの特派員報告をさせて頂きます。 チャイナリスクが意識されてから日本企業は中国への依存度を下げようとしています。生産面では国内回帰の流れがありますし、世界最大の人口を抱えるインドや発展著しいASEANでの生産体制構築があります。 ASEANの中では人口の比較的大きなインドネシア、ベトナム、フィリピンあたりが注目されています。 今回はその中で古くから日本企業が進出してきたベトナムにフォーカスして、現在ベトナム、ホーチミンに在住の四億さんから報告して貰います。 最後までお付き合い下さい。(炎)**************** 億の近道読書の皆さん、こんにちは。 私は一億ではなく四億(ヨンオク)と申します。 億の近道の読書の皆さ -
ヴェルナー・ゾンバルト「恋愛と贅沢と資本主義」の視点(その2)
2023-07-13 21:07
100年以上前の本ですが、タイトルはドイツの経済学者ゾンバルト(1863-1941)の書籍です。 アマゾンリンク ⇒ https://amzn.to/3JCkwmW ゾンバルトによれば、フランスのルイ14世の時代には、国家財政の3割弱が王様の個人的な支出だったそうです。これらの個人的な支出は手工業者や大工の左官仕事に費やされましたが、画家、金属細工屋、ガラスや、彫刻家にも多額の支払いとなりました。マリーアントワネットの衣料費については細かい記述があります。 そこで、思考実験です。 仮に、人類の供給能力が格段に向上したとしたら、どうなるでしょうか。 単なる需給論・均衡論で考えるとモノの価格は限りなくゼロになってしまいます。 なぜならば供給能力が格段に上がれば需要と供給のバランスが崩れてしまい価格が暴落するからです。 株式投資ではこれからのことを考えるのですが、わたしたちの狭い視野で考える -
人間経済科学と賢人たちの教え その24
2022-06-23 16:32
産業新潮http://sangyoshincho.world.coocan.jp/7月号連載記事■その24 日本型経営は「人間社会の進歩の結果」●アナログはデジタルの進化形である。 例えば読者が「アナログ人間」とだれかに言われたとしよう。それをほめ言葉だと受け取るケースはほとんど無いであろう。大概の場合、「あなたはデジタルが分からない旧式の人間だ」と侮辱されたと思うに違いない。 つまり、現在の世の中では、デジタルがアナログよりもすぐれており、アナログがデジタルに進化していくように思われているということだ。しかし、それはまったくの間違いであり。正反対なのだ。 生物進化の一つの完成形と考えられる読者の体を使って確かめてみたい。1.読者の両腕を左右に広げる。2.前を向いたまま左右の手の指先を、それぞれ目の端でとらえる努力をする。 すると、ほぼ手を180度広げた状態でも、左右それぞれの目の端で指 -
"経済学者たちの日米開戦"の著者、牧野邦昭さんと考える。なぜ人は合理的な判断ができないのか? 後編
2022-06-17 19:16
小屋が様々な有識者の方々と対談を行うシリーズ。 今回は、牧野教授との対談、後編をお届けします。■経済思想史的に「日本人がお金を運用しない問題」はどう見える?小屋:僕はお客さんのパーソナルファイナンスの分析をしながら、アドバイスする仕事をしているわけですが、「日本人」という大きい主語で言うと、お金を運用してない人が多いんですね。 ですから、結果的に最初のアドバイスは、十中八九「運用しませんか?」となります。 ところが、十分に資産を持っている人でも、運用、投資と聞くと「怖い」と言う人が少なくないんですね。 日本人はどうしてこんなに運用を怖がるんだろう、と。 合理的に考えると、資産の一部を運用したほうが成長するわけで、経済思想史的に「日本人が運用しない問題」はどう見えていますか?牧野:きっと小屋さんとはそういう話をするんだろうなと思って、少し調べてみました。すると、日本人は元々、運用や投資に -
経済学者たちの日米開戦"の著者、牧野邦昭さんと考える。なぜ人は合理的な判断ができないのか? 前編
2022-06-07 15:54
小屋が様々な有識者の方々と対談を行うシリーズ。 今回は、小屋の高校時代の友人でもある経済学者の牧野さんとの対談をお届けします。 ある日、なんとなくテレビを見ていたら、中学、高校時代の同級生が登場。 それもNHKの歴史番組のメインゲストときたら、驚きますよね? 今回の対談の相手、牧野邦昭さんは小屋さんの中高時代の同級生で、2021年から慶應義塾大学経済学部の教授を務める経済思想史の専門家。 2018年に出版した『経済学者たちの日米開戦:秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く』(新潮選書)は、緻密な事実と資料の積み重ねによる新事実の発見と行動経済学や心理学の研究を引用した大胆な仮説で話題となりました。 テレビで同級生の著作を知った小屋さんは、さっそく通読。「日米開戦に踏み切ってしまったのは、正しい分析がなされていなかったから」「一流の経済学者らが分析した情報はあったが、一般には知られていなかった -
人間経済科学と賢人たちの教え その23
2022-05-26 13:18
産業新潮http://sangyoshincho.world.coocan.jp/6月号連載記事■その23 ノーベル賞経済学者の大罪●アルフレッド・ノーベル 今や世界中の誰もが知るようになったノーベル賞は、1833年にスウェーデンに生まれた化学者、発明家、実業家であるアルフレッド・ベルンハルド・ノーベルの遺産によって創設された。彼は、350もの特許を取得し、中でもダイナマイトの開発で巨万の富を築いたことから、「ダイナマイト王」とも呼ばれた。 遺言で賞を授与するとされた分野は、まずは物理学、化学、医学または生理学の3分野である。さらに4つ目として(理想的な方向性の)「文学」、5つ目は軍縮や平和推進に貢献した個人や団体に贈る「平和賞」である。 実業家であると同時に化学者でもあったノーベルが「科学・化学」関連分野の研究を高く評価していたのは間違い無い。ダイナマイトを含む多数の発明は科学・化学の -
人間経済科学と賢人たちの教え その22
2022-05-20 16:03
産業新潮http://sangyoshincho.world.coocan.jp/5月号連載記事■その22 アダム・スミスと人間経済科学●アダム・スミスと「道徳感情論」 アダム・スミスの名前を知らない読者は多分いないであろう。彼が1776年に発刊した「国富論」は、今でも経済学の聖典として扱われている。スミスが「経済学」の始祖というべき人物であることに異論は無いはずだ。 しかしスミスが、映画ハリー・ポッターの撮影に使われたと言われるグラスゴー大学の道徳哲学(最初は論理学)教授であったことはあまり注目されない。1759年に「道徳感情論」を出版したが、当時はこちらの方が大ベストセラーであり、「国富論」はこの大ベストセラーの内容のうち「人間の経済」に関わる部分をより詳しく解説した別冊として企画されたのだ。 したがって、「国富論」を読むだけでは、アダム・スミスの思想の表面だけを撫でることになってし -
人間経済科学と賢人たちの教え その21
2022-03-26 11:52
産業新潮http://sangyoshincho.world.coocan.jp/4月号連載記事■その21 「現場重視」の日本型経営が競争力の秘密●人間は狂ったサルか? 「人間は狂ったサルである」と表現されることがしばしばある。縄張り争いのために、敵(国)を攻撃して殲滅するだけでは無く、核兵器などというものまで生みだして、敵だけでは無く自国も含めた人類滅亡の危機を招く。 さらには、存在するかどうかもわからない「神」のために凄惨な殺し合いを行う。果ては、自分の信じる神を敬わないからと言って、生きたまま焼き殺したり、車で八つ裂きにしたりする。 このような人類を「正気」だというのは難しいであろう。 それでは、人類が狂っている原因は何か? 人間の知性や思考を、他の動物から際立たせている、極めてよく発達した大脳皮質にあるのだ。もちろん、大脳皮質が発達することによって、人間の高度な文化・文明が進展し -
人間経済科学と賢人たちの教え その20
2022-02-28 16:03
産業新潮http://sangyoshincho.world.coocan.jp/3月号連載記事■その20 事件は現場で起こっている●デジタルは原始的である 一般的に、「アナログ」という言葉は、「時代遅れで古臭くて機能が劣っている」という意味合いで使われることが多い。逆に「デジタル」は「先進的・未来的・挑戦的」なイメージで語られることが殆どだ。 確かに、人間を始めとする生物界、さらには人工の建設物も含む環境はほぼすべてアナログだから、近年登場したデジタルが革新的だと思うのも無理は無い。 しかし、地球誕生以来の生命の歴史を考えれば、「デジタルからアナログ」へ進化してきたと考える方が正しいのだ。 例えば、コンピュータ上で生活する(画面上を動く)生物は、ごく簡単な単細胞生物のようなものであれば、デジタルで十分作成できるのだ。ところが、その生物がコンピュータ上で「進化」していくにつれて、どんどん -
株式相場低迷と日本国の衰退(その1)
2022-02-24 16:11
日本国の衰退が株式市場にも色濃く反映されつつある昨今だ。 世界に類を見ない神武天皇即位以来の2680年にも及ぶ歴史を積み重ねてきた日本国に気概を取り戻させてくれる指導者がいない現状を憂う。 だがその中に次代を担う人々や企業のパワーも感じられる。 過去から現在、そして未来へとつながる国体の行く末に思いを馳せながら日本の株式市場の復活に必要な要素をじっくり考えてみたい。 今や悪質なクレーマーのごとく絶えず吠えまくる臆病なスピッツ犬のごとき隣国。貧した時代に媚びを売りしっぽを振って恭順な態度を示して取り入り餌をもらってお腹を膨らませた途端にその本質を露わにしようとする実際には獰猛な雑種犬とも言える我が物顔の反社勢力的な隣国。 更にはいつの間にか領土を隣接地帯で拡張し世界の火種となりつつあるドーベルマン国家。日本国を取り巻く世界にはこうした犬たちが縄張り争いをいまだに続けている。 かつては餌を
1 / 9
次へ>